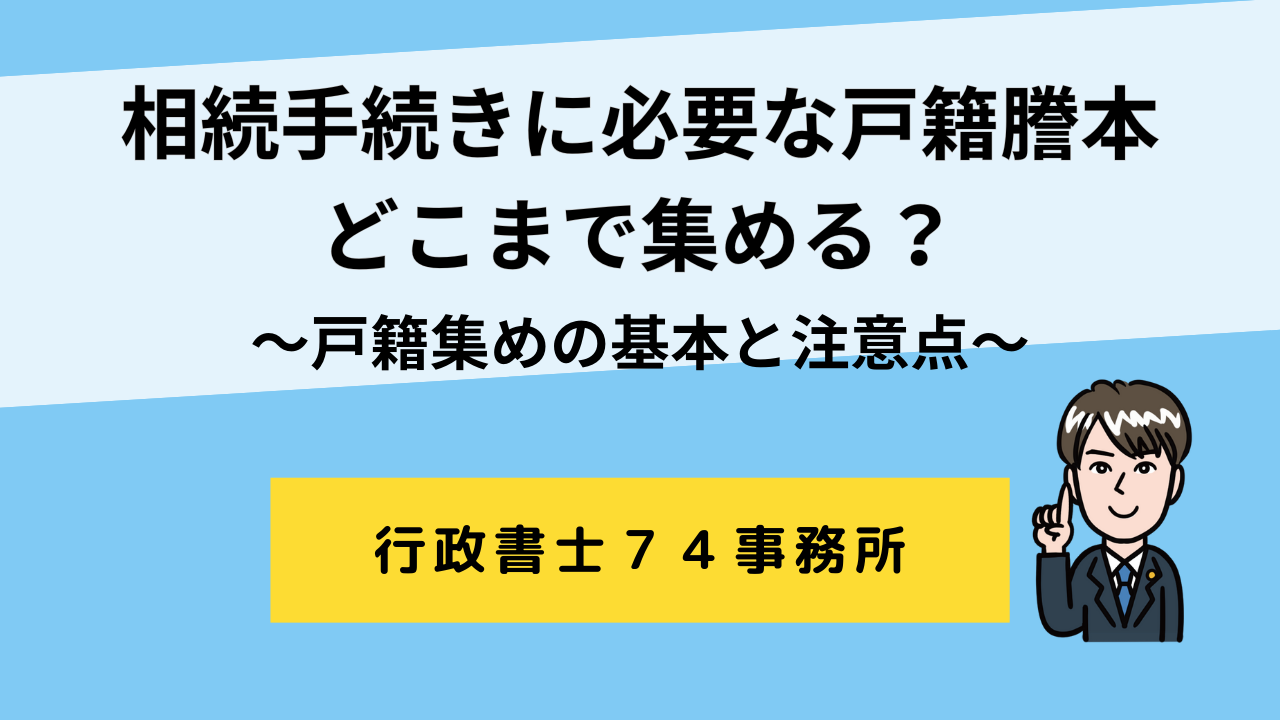はじめに 相続手続きでまずぶつかる「戸籍の壁」
家族が亡くなったとき、多くの人が直面するのが「相続手続き」。
中でも、「戸籍謄本を集めてください」と言われた瞬間、ピンと来ない方も多いのではないでしょうか?
「本籍地って何?」「今ある戸籍じゃだめなの?」「いったいどこまで集めればいいの?」そんな戸惑いの声が非常に多いのが、この戸籍集めです。
この記事では、相続手続きに必要な戸籍謄本について、どこまで・どんなふうに・どうやって集めるのかを、初心者にも分かりやすく解説していきます。
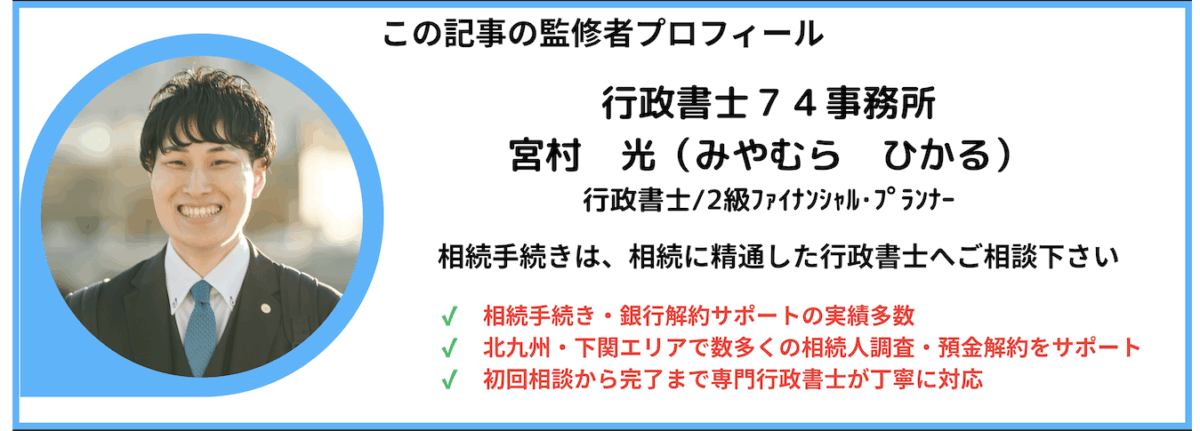
そもそも、なぜ戸籍謄本が必要なの?
相続手続きでは、「誰が相続人なのか」を正確に確定する必要があります。
それを証明する唯一の公的書類が、戸籍謄本(こせきとうほん)です。
例えば…
- 銀行の預金を引き出す
- 不動産の名義変更をする
- 相続税を申告する
といった各種の相続手続きにおいて、相続人を証明できないと手続きが進まないため、戸籍が必須なのです。
集める戸籍は「被相続人」と「相続人」両方必要!
相続手続きで必要になる戸籍は、大きく分けて以下の2種類です。
- 被相続人(亡くなった人)の戸籍
- 相続人(遺族など)の現在の戸籍
それぞれどこまで集める必要があるのか、順を追って見ていきましょう。
①被相続人の戸籍は「出生から死亡まで」全て必要
ここが最大のポイントです。
被相続人の相続手続きでは、亡くなった人の“出生から死亡まで”の連続した戸籍謄本が必要になります。
▼なぜ出生までさかのぼるの?
誰が相続人かを正確に判断するためには、亡くなった方の「家族関係の履歴」をすべて確認する必要があります。
- 実は前の結婚で子どもがいた
- 認知した非嫡出子がいた
- 養子縁組していた
など、戸籍を追わないと分からないことが多く、相続人の漏れを防ぐために、出生からの戸籍が求められるのです。
②相続人全員の現在の戸籍も必要
戸籍の確認が終わったら、次は、相続人全員の“現在の戸籍”を用意します。これにより、
- 自分が相続人であること
- その人が現在生存していること
を証明できます。
兄弟姉妹、配偶者、子どもなど、相続権のある人全員分が必要になります。
実際にはどんな戸籍が必要?
戸籍にはいくつか種類があり、初めてだと混乱しがちです。以下でそれぞれ整理しておきましょう。
| 戸籍の種類 | 内容 | 取得先 |
|---|---|---|
| 戸籍謄本 | 同じ戸籍に記載されている全員分(原則) | 本籍地の市区町村役場 |
| 除籍謄本 | 戸籍から全員が除かれたもの(転籍・死亡など) | 転籍前の役場など |
| 改製原戸籍 | 戸籍制度が改正されたときの旧形式の戸籍 | 過去の本籍地 |
特に、転籍が多い人や高齢の方の場合は、複数の市区町村から戸籍を集める必要があることも珍しくありません。
【例】実際にどんな流れで集めるの?
ここでは、例を挙げて具体的な流れを見てみましょう。
▼ケース:2023年に父(昭和18年生まれ)が亡くなった場合
- 現在の戸籍(死亡の記載あり)を取得
- その前の戸籍 → さらに前の戸籍 → 出生時の戸籍へとさかのぼる
- 生まれた時点の戸籍に「出生」の記載があればOK
- 次に、相続人全員(配偶者・子どもなど)の現在の戸籍を用意
ポイント 1枚では終わらず、5〜10通以上になることも珍しくない!
【集め方】戸籍はどうやって取るの?
❶ 本籍地の市区町村役場で請求(郵送も可)
- 窓口で取得:身分証明書と手数料が必要
- 郵送請求:申請書・本人確認書類のコピー・定額小為替・返信用封筒が必要
❷ どこの本籍かわからない場合
- 最新の戸籍に記載されている「前の本籍地」を手がかりに、たどっていく形で取得
- 時間と手間がかかる場合は、専門家への依頼も検討を
※現在は、広域交付制度が始まり、直系のご家族であれば最寄りの市区町村役場で一括で取得が可能です。
【ここに注意!】戸籍収集でつまずきやすいポイント
● 本籍と現住所は違う
住民票のある場所ではなく、「本籍地」の役所で請求する必要があります。
● 改製原戸籍が読みにくい
旧字や略字で手書きのため、読むのが困難なことも多い。内容の確認にも時間がかかります。
● 相続人が多いと、それぞれの戸籍が必要
兄弟姉妹相続や代襲相続があると、戸籍の数がどんどん増えることも。
その場合は戸籍の取得だけで1ヶ月以上掛かることもあります。
【便利ワザ】戸籍収集をラクにする方法は?
法務局や法務省のオンラインサービスの活用(2024年〜一部開始)
電子申請やマイナンバー活用による戸籍取得も一部地域でスタート。
専門家(行政書士等)に依頼する
「時間がない」「遠方の本籍が多い」場合は、相続手続きの専門家に依頼することで、手間とストレスを大きく削減できます。
まとめ 戸籍集めは“慎重に、早めに”がカギ!
| 要点 | 内容 |
|---|---|
| 誰の戸籍が必要? | 被相続人(出生〜死亡)+ 相続人(現在) |
| どこで取る? | 本籍地の市区町村役場(郵送・窓口) |
| どのくらい必要? | 平均5〜10通以上。転籍が多いとさらに増える |
| 難しいときは? | 行政書士等に相談・依頼もOK |
おわりに 戸籍は「家族の履歴書」
戸籍は、亡くなった方の人生と家族関係を記録した「履歴書」のようなもの。
正確に集めることで、相続の手続きもスムーズになり、トラブル防止にもつながります。
最初は少し面倒に感じるかもしれませんが、ポイントさえ押さえれば着実に進められます。
大切な人の想いをしっかり引き継ぐためにも、戸籍収集は丁寧に、早めに始めることが大切です。
相続人の調査はお任せ下さい!法定相続情報一覧図代行サービス
当事務所では北九州市門司区を中心に相続人の調査のサポートをしております。
『手続きが難しくてできない』『相続手続きをいち早く完了したい』という方は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
当事務所は、相続手続きに専門特化しており、門司区で数少ない相続手続き専門行政書士事務所です。
これまで約5年、北九州市門司区を中心に相続人の調査手続きをして参りました。
必要書類の準備から窓口での手続きを迅速に行い、お客様のご不安を解決します。
お問い合わせは、お電話または下記のお問い合わせフォームよりお待ちしております。
また公式LINEのチャットでのご相談は無料となっていますので、お気軽にご相談くださいませ。
ご依頼の流れ
お電話・下記お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
【お電話の場合】
お電話でお客様のご都合を伺わせていただき決定します。
【お問い合わせフォームの場合】
お問い合わせの内容を確認次第、こちらからご連絡させていただきます。
その際ご面談の日時や場所をお客様のご都合を伺いながら決定します。
お客様のお悩みを伺い、最善の方法でお悩みを解決できるようご提案いたします。
ご面談の内容に納得・合意頂けましたらご契約の手続きをします。
原則、着手金として基本料金をお預かりしております。
(指定銀行口座へお振込み)
残額は業務完了後にお支払い頂きます。
(10万円未満の場合は全額を基本料として頂戴しております。)
着手金のお振込みの確認 若しくは委任契約の合意ができ次第、業務を開始します。
定期的に業務の進行状況等のご連絡をいたします。
業務が全て完了しましたらその旨のご連絡をいたします。
最終的に弊所が行った業務内容についてご説明し書類等の納品をします。
手数料の合計と実費等の精算をしまして3日以内に完了金をお支払いして頂きます。
お問い合わせフォーム
お電話もしくは下記お問い合わせフォームよりご連絡をお願いいたします。
LINEではトーク画面のメッセージからでもご相談可能です。
『相談希望』とメッセージください。