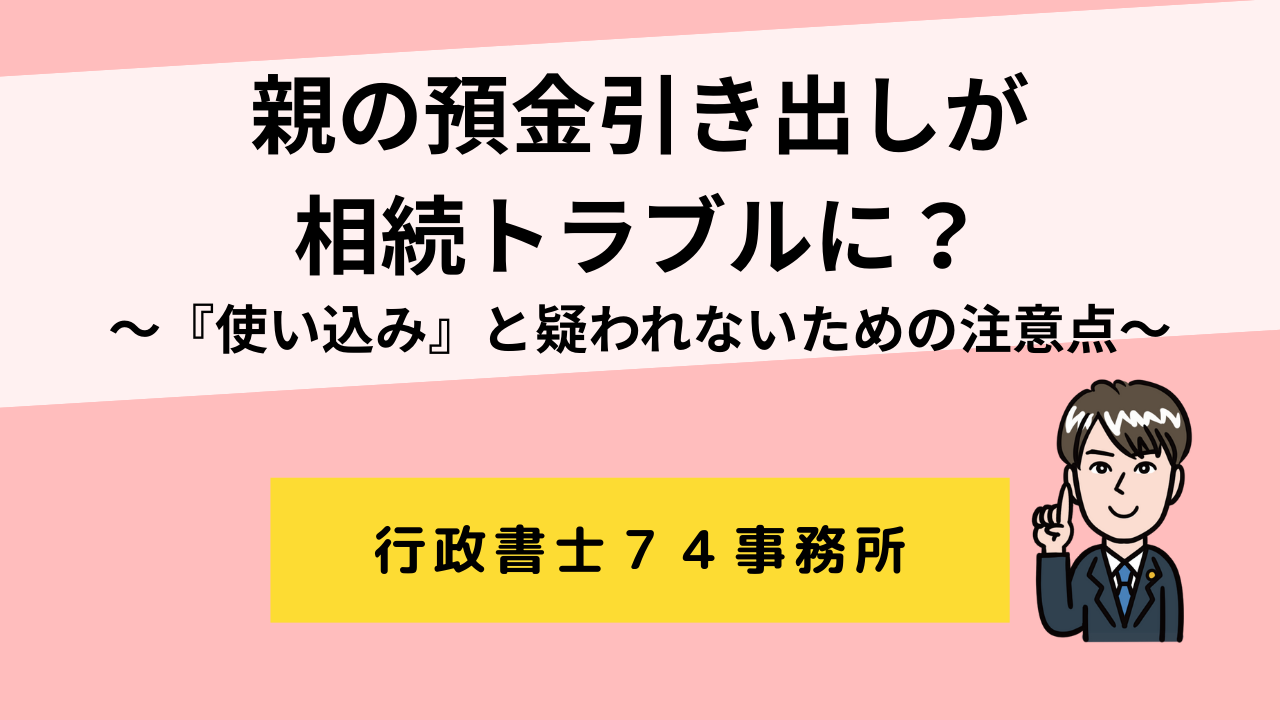はじめに 親の介護や管理のために引き出したはずが…
「親のお金を管理していた」「通院費や生活費のために必要だった」「親の了承も得ていた」
そんな思いで、親の銀行口座から現金を引き出して使っていた人が、親の死後、“使い込みだ”と他の相続人から責められるケースが増えています。
こうしたお金の扱いをめぐる相続トラブルは、「争族(そうぞく)」と呼ばれ、年々深刻化しています。
この記事では、「親の口座からお金を引き出していたらトラブルになった」場合の背景や、法律的な考え方、トラブルを避けるために知っておくべきポイントを、相続の初心者でも理解できるように解説します。
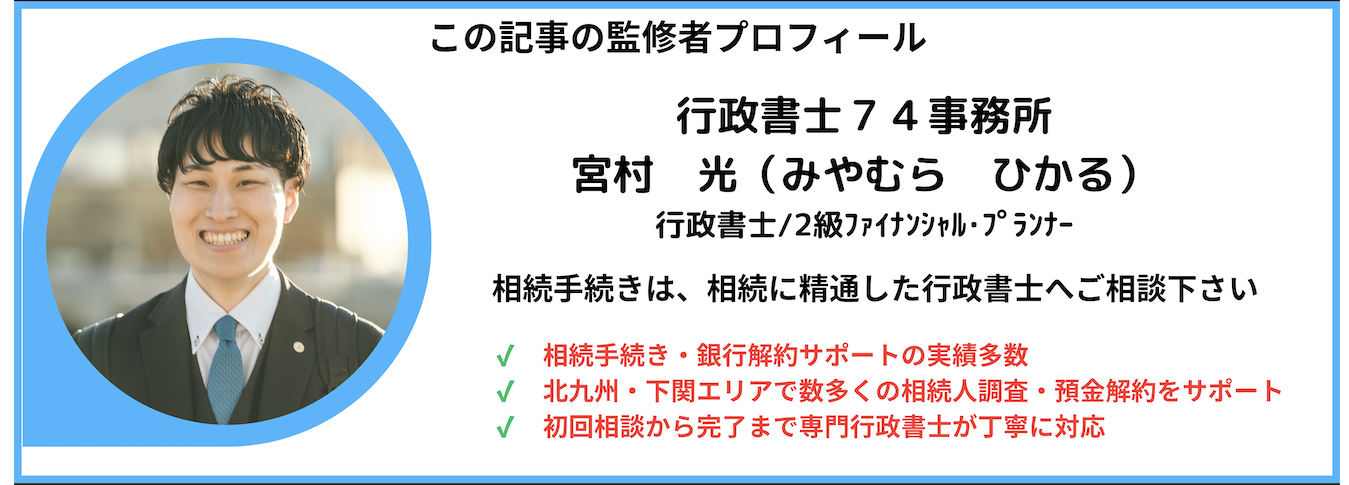
北九州市で銀行相続の手続きが必要な方へ
✔ 忙しくて役所・銀行に行く時間がない
✔ 必要書類が多くて準備できない
✔ 相続人が遠方で手続きが進まない
✔ 専門家に全て任せたい
このようなお悩みは、当事務所がワンストップで解決します。出張費無料で北九州全域に対応しています。
※今すぐ銀行の相続手続きを解決したい方は、お電話にてお問い合わせくださいませ。
生前に親の通帳からお金を引き出すことの意味
親の口座からお金を引き出す行為は、日常的によく見られます。
特に、親が高齢で判断力が弱まっていたり、介護が必要な状態だったりすると、子どもが代わりにお金を管理するケースも少なくありません。
代表的な場面
- 介護施設や病院の費用を支払うため
- 食費や日用品の購入
- 親から「好きに使っていい」と言われていた場合
ただし、こうした行為は、形式上は「他人の口座からお金を引き出している」ことになります。
親の死後、他の相続人(兄弟姉妹など)から見ると、
「勝手に使ったんじゃないの?」
「本当に親のために使ったのか?」
と疑われる原因になるのです。
「使い込み」と見なされるとどうなる?
もし親が亡くなった後に、他の相続人から「これは使い込み(不当利得・不法行為)」だと主張された場合、トラブルは避けられません。
「使い込み」と判断されると…
- 引き出した金額の返還請求をされる
- 遺産分割協議が揉める・長引く
- 家庭裁判所で調停や訴訟になることも
- 相続人同士の信頼関係が崩壊する
本人は親のために使ったつもりでも、証拠がなければ法的には認められないケースもあります。
実際にあったケース 兄が介護していたのに弟から「返せ」と言われた
兄が長年親の介護をしており、親の口座から引き出して生活費や医療費に充てていました。
親も了承していたし、レシートなども残していなかったとのこと。
親が亡くなった後、弟から「亡くなる前の5年間で700万円も引き出していた。何に使ったんだ? 返せ」と追及され、最終的に家庭裁判所の調停に。
兄は「介護の苦労に対する当然の報酬」と考えていたが、法律上は親の死後に発覚したお金の動きは、すべて“相続財産の不当減少”とされかねないのです。
法律的にはどう扱われる?預金は「共有財産」
親が生前に所有していた財産(預貯金・不動産など)は、亡くなった瞬間に相続人全員の「共有財産」となります。
つまり、親が亡くなる前に引き出されたお金については、「その目的・使途・親の同意」が明確でなければ、他の相続人が問題にする余地が生まれます。
ポイント
- 使途が明確でなければ「不当利得」とみなされる
- 預金の引き出しは「委任契約」に基づいていたかが重要
- 相続人が他にいる場合は、特に慎重に扱うべき
よくある誤解とトラブルの例
誤解①「親からもらったから問題ない」
→ 現金や預金は、生前に正式な贈与契約がなければ、「贈与」としては認められません。
口頭だけの「好きに使っていいよ」は通用しない可能性があります。
誤解②「介護したんだから当然」
→ 介護にかかった費用と、対価として受け取った金額が明確でなければ、「過剰な報酬」「私的流用」とみなされる可能性があります。
誤解③「自分が通帳や印鑑を持っていたから」
→ 通帳や印鑑の保管は、「管理を任されていた」だけであり、自由に使える権利があるわけではありません。
トラブルを避けるためにできること
1. 使途の記録を残す
- 領収書、レシート、メモ帳などで「何に使ったか」を記録する
- 親の了承があったことを書面で残す、あるいは録音・日記でも可
2. 家族と情報を共有する
- 定期的に他の兄弟にも「親のお金の使い道」を伝えておく
- 特に大きなお金を動かすときは、事前に相談を
3. 親と正式に「委任契約」や「贈与契約」を交わす
- 公正証書で作成すれば、法的な証拠として強力です
4. 家族信託や成年後見制度の活用
- 将来的に介護や金銭管理が必要になる場合、事前に法的な枠組みを整えておくことで、相続時のトラブルを防げます
相続発生後に「怪しい」と思われないために
相続が発生したあと、「あの人だけ通帳持ってたよね?」「亡くなる直前に多額の引き出しがある」などと指摘されることがあります。
このときに、記録も説明もできないと、「使い込み」とみなされるリスクが高くなります。
たとえ善意でも、「証拠がなければ通用しない」のが法律の世界です。
まとめ お金の管理は「見える化」と「記録」がカギ
親の介護や生活支援のためにお金を引き出すこと自体は、間違ったことではありません。
むしろ、親のために尽くしてきた人が損をするようなことは、本来あってはならないことです。
しかし、「善意」と「法的責任」は別問題。
だからこそ、次のような意識を持つことが重要です。
- 「家族だから大丈夫」は通用しない
- 使い道は記録しておく
- トラブルを避けるには、事前の合意と情報共有が大切
相続のトラブルは、財産が大きい・小さいに関係なく起こります。
平穏な相続のためにも、今から備えておくことが、自分自身と家族を守る第一歩です。
迅速に受け取れる相続預金手続き!銀行の相続手続き代行サービス
当事務所は、北九州市門司区を中心に、銀行の相続手続きに特化したサポートを行っております。
「相続手続きが難しくて進められない」「相続手続きをできるだけ早く完了させたい」とお考えの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。
当事務所では、銀行の相続手続きに特化した専門的な支援を行っており、北九州市内で唯一、銀行相続手続きに専門特化した行政書士事務所として実績を積んでおります。
これまで約5年間、北九州市および下関市内のほとんどの銀行で手続きをサポートして参りました。
必要書類の準備から窓口での手続きまで、迅速かつ確実に対応し、お客様のご不安を解消いたします。
お問い合わせは、お電話または下記のお問い合わせフォームからお受けしております。
また、公式LINEにてチャットでのご相談も無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
ご依頼の流れ
お電話・下記お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
【お電話の場合】
お電話でお客様のご都合を伺わせていただき決定します。
【お問い合わせフォームの場合】
お問い合わせの内容を確認次第、こちらからご連絡させていただきます。
その際ご面談の日時や場所をお客様のご都合を伺いながら決定します。
お客様のお悩みを伺い、最善の方法でお悩みを解決できるようご提案いたします。
ご面談の内容に納得・合意頂けましたらご契約の手続きをします。
原則、着手金として基本料金をお預かりしております。
(指定銀行口座へお振込み)
残額は業務完了後にお支払い頂きます。
(10万円未満の場合は全額を基本料として頂戴しております。)
着手金のお振込みの確認 若しくは委任契約の合意ができ次第、業務を開始します。
定期的に業務の進行状況等のご連絡をいたします。
業務が全て完了しましたらその旨のご連絡をいたします。
最終的に弊所が行った業務内容についてご説明し書類等の納品をします。
手数料の合計と実費等の精算をしまして3日以内に完了金をお支払いして頂きます。
お問い合わせフォーム
お電話もしくは下記お問い合わせフォームよりご連絡をお願いいたします。
LINEではトーク画面のメッセージからでもご相談可能です。
『相談希望』とメッセージください。