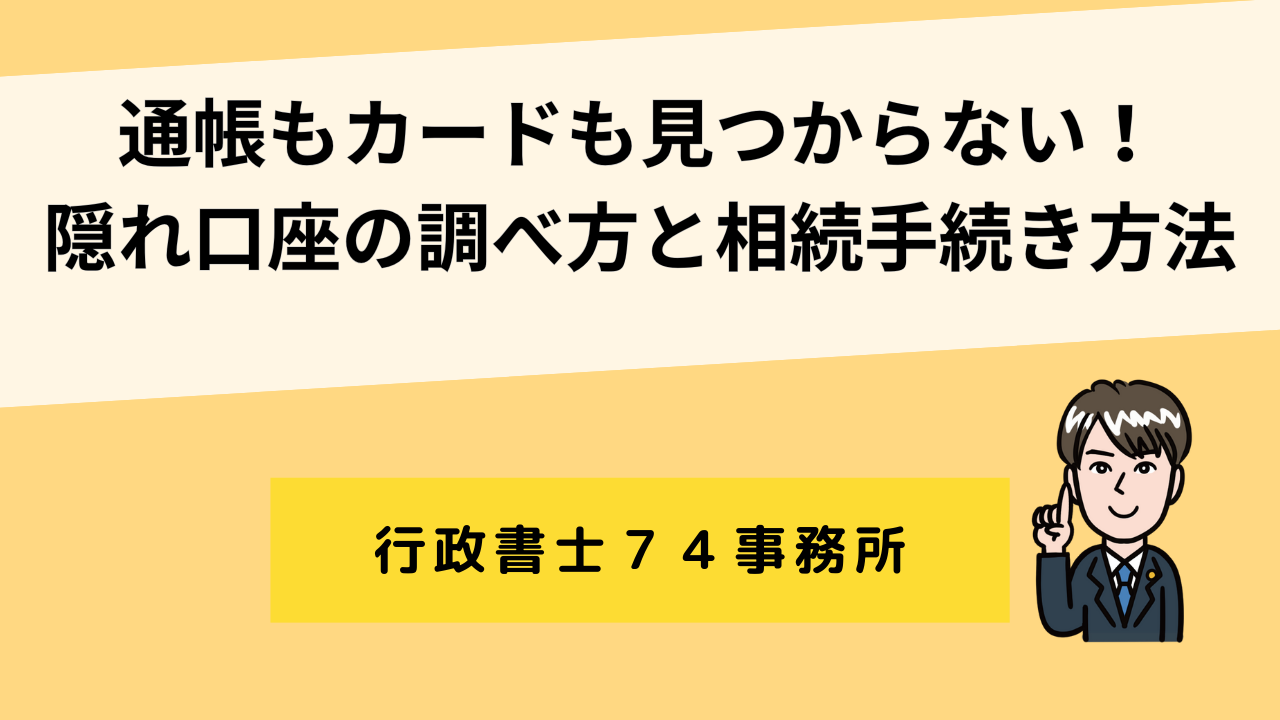相続手続きの中で、意外に多くの人が悩むのが「故人の通帳やカードが見つからない」「口座が隠れているかもしれない」という問題です。
親族や親が亡くなると、通常はその名義の銀行口座やクレジットカードを確認し、必要な相続手続きを進めます。
しかし、故人が生前に残していた口座が見つからないことがあります。
このような場合、どうやって「隠れ口座」を見つけ、どう対応すればよいのでしょうか?
今回は把握できていない隠れ口座の調べ方について解説します。
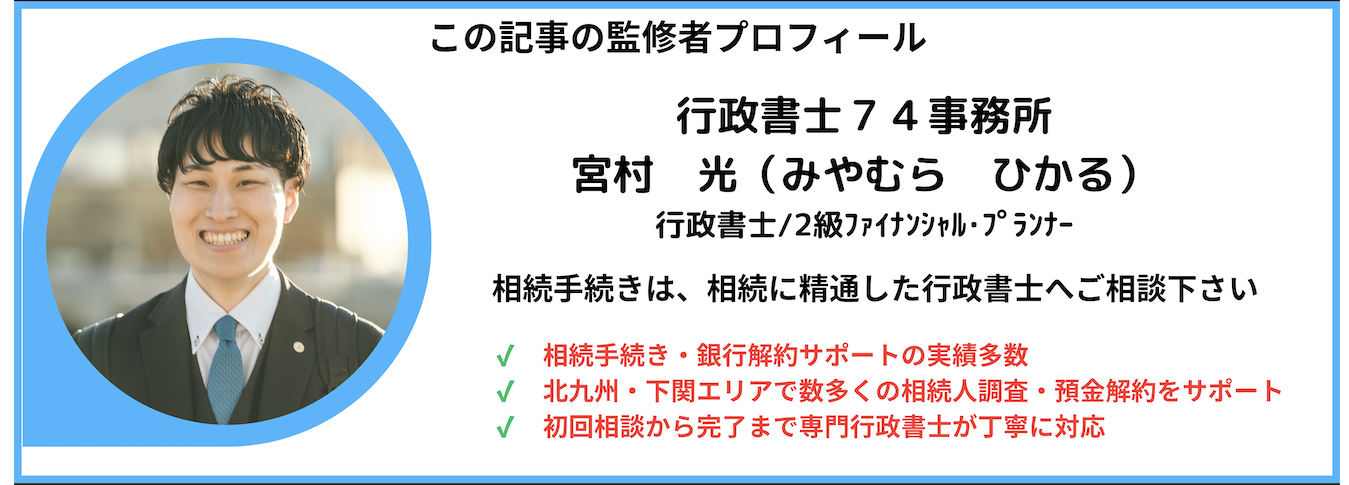
北九州市で銀行相続の手続きが必要な方へ
✔ 忙しくて役所・銀行に行く時間がない
✔ 必要書類が多くて準備できない
✔ 相続人が遠方で手続きが進まない
✔ 専門家に全て任せたい
このようなお悩みは、当事務所がワンストップで解決します。出張費無料で北九州全域に対応しています。
※今すぐ銀行の相続手続きを解決したい方は、お電話にてお問い合わせくださいませ。
1. 隠れ口座とは?
「隠れ口座」とは、故人が意図的に隠していたわけではなく、家族が知らないうちに存在している口座を指します。
例えば、以下のような口座が隠れ口座として問題になることがあります。
- 複数の銀行口座がある場合 故人が生前に別の銀行に口座を開設していたが、家族はその存在を知らなかった。
- クレジットカードの残高がある場合 クレジットカードの明細書やカードが見つからないが、カード会社に未払いの残高がある。
- 預金通帳やキャッシュカードが見当たらない場合 故人が使用していた通帳やカードが見つからないが、口座は実際に存在する。
このように、故人が管理していた口座が見つからない場合、相続人がその口座を特定するためにはいくつかの方法を駆使する必要があります。
2. 隠れ口座を調べるための方法
隠れ口座を調べる方法には、以下のようなものがあります。
(1) 故人の書類やデジタル情報をチェックする
故人が残した書類やデジタル情報に、銀行口座の情報やカードの情報が記載されている場合があります。
まずは、以下のものを確認しましょう。
- 遺品整理 故人の机の中や書類棚、家の中に保管されている通帳やカードの有無を確認します。
- パソコンやスマートフォンのチェック 故人が生前に利用していたパソコンやスマートフォンに、銀行口座やカード情報が保存されていることがあります。
- 電子メールやメモ ネットバンキングやクレジットカードの明細が電子メールで送信されている場合もあります。故人のメールアカウントをチェックしてみましょう。
(2) 銀行やカード会社に問い合わせる
隠れ口座を見つけるために最も重要な方法は、銀行やカード会社に直接問い合わせることです。
問い合わせの際には、以下の情報が必要になることがあります。
- 故人の氏名・住所(亡くなった日も含めて)
- 故人の生年月日
- 故人の死亡届の写し
- 相続人であることを証明する書類(相続人の戸籍謄本や遺言書など)
銀行やカード会社は、口座情報を提供する際に相続人であることを確認するための手続きを求めることがあります。
一般的に、相続人は故人が契約していた金融機関に対して、適切な書類を提出し、情報提供を受けることができます。
(3) 金融機関の「口座の検索サービス」を利用する
いくつかの金融機関では、口座情報が不明な場合に利用できる「口座の検索サービス」を提供している場合があります。
例えば、次のようなサービスが利用できます。
- 口座情報の調査依頼 金融機関に依頼して、故人が名義人となっていた口座が存在するかどうか調査してもらいます。
- 金融機関同士の情報照合 複数の銀行に口座を持っていた場合、金融機関同士で情報を照会し、隠れ口座を見つけることができる場合があります。(事前にマイナンバーで紐付け)
これらのサービスを利用するには、手数料が発生することもありますので、事前に確認しておきましょう。
(4) 相続人が知っている範囲での口座開設履歴の調査
もし故人が生前に金融機関に対して、特定の目的で定期的に入金していた場合、その履歴を基に口座を探すことができる場合があります。
例えば、年金や給与の振り込み先などが考えられます。
この情報を元に、口座の有無を確認する手段として利用できます。
(5) 行政書士に相談する
もし隠れ口座の調査や相続手続きが煩雑で困難な場合、行政書士に相談することをお勧めします。
特に、法的な手続きや口座情報の特定が必要な場合に専門家の助けを借りることで、スムーズに手続きを進めることができます。
3. 隠れ口座が見つかった場合の対応法
隠れ口座を見つけた場合、その後の対応が重要です。以下の手続きを行いましょう。
(1) 口座の凍結手続き
隠れ口座を見つけた場合、まずはその口座を凍結する手続きを行いましょう。
相続手続きが終わるまで、故人の口座からの不正引き出しや取引が行われないようにするためです。
銀行に対して相続が発生したことを通知し、口座の凍結を依頼します。
(2) 相続税の申告
隠れ口座に預金が残っている場合、その預金は相続財産として申告が必要です。
相続税がかかる場合もありますので、必要に応じて税理士に相談し、適切に相続税の申告を行いましょう。
(3) 負債があった場合の処理
もし隠れ口座に負債(ローンやクレジットカードの未払い金)があった場合、相続人がその負債を相続することになります。
負債の整理や支払い方法についても確認が必要です。
場合によっては、弁護士に相談して債務整理を行うことが求められることもあります。
4. まとめ
故人の銀行口座やクレジットカードの情報が見つからない場合でも、いくつかの方法を駆使することで隠れ口座を特定することができます。
書類やデジタル情報のチェック、金融機関への問い合わせ、専門家の支援などを通じて、適切な手続きを進めることが重要です。
もし隠れ口座が見つかった場合、その口座を凍結し、相続税の申告や負債の処理なども確実に行うようにしましょう。
相続は非常に複雑な手続きが多いため、初心者の方は専門家に相談しながら進めると安心です。
相続手続きを丸ごとサポート!銀行の相続手続き代行サービス
当事務所は、北九州市門司区を中心に、銀行の相続手続きに特化したサポートを行っております。
「相続手続きが難しくて進められない」「相続手続きをできるだけ早く完了させたい」とお考えの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。
当事務所では、銀行の相続手続きに特化した専門的な支援を行っており、北九州市内で唯一、銀行相続手続きに専門特化した行政書士事務所として実績を積んでおります。
これまで約5年間、北九州市および下関市内のほとんどの銀行で手続きをサポートして参りました。
必要書類の準備から窓口での手続きまで、迅速かつ確実に対応し、お客様のご不安を解消いたします。
お問い合わせは、お電話または下記のお問い合わせフォームからお受けしております。
また、公式LINEにてチャットでのご相談も無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
ご依頼の流れ
お電話・下記お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
【お電話の場合】
お電話でお客様のご都合を伺わせていただき決定します。
【お問い合わせフォームの場合】
お問い合わせの内容を確認次第、こちらからご連絡させていただきます。
その際ご面談の日時や場所をお客様のご都合を伺いながら決定します。
お客様のお悩みを伺い、最善の方法でお悩みを解決できるようご提案いたします。
ご面談の内容に納得・合意頂けましたらご契約の手続きをします。
原則、着手金として基本料金をお預かりしております。
(指定銀行口座へお振込み)
残額は業務完了後にお支払い頂きます。
(10万円未満の場合は全額を基本料として頂戴しております。)
着手金のお振込みの確認 若しくは委任契約の合意ができ次第、業務を開始します。
定期的に業務の進行状況等のご連絡をいたします。
業務が全て完了しましたらその旨のご連絡をいたします。
最終的に弊所が行った業務内容についてご説明し書類等の納品をします。
手数料の合計と実費等の精算をしまして3日以内に完了金をお支払いして頂きます。
お問い合わせフォーム
お電話もしくは下記お問い合わせフォームよりご連絡をお願いいたします。
LINEではトーク画面のメッセージからでもご相談可能です。
『相談希望』とメッセージください。