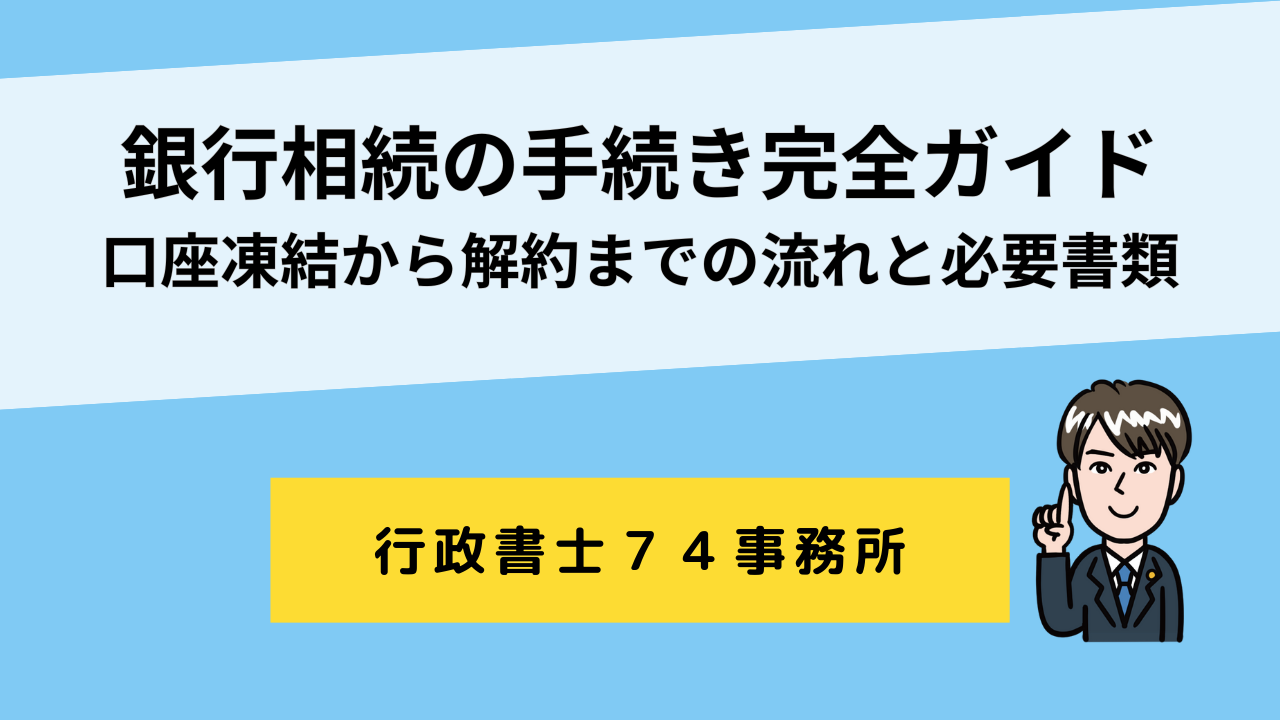親しい方が亡くなると、さまざまな相続手続きを行う必要があります。
その中でも、銀行口座の相続手続き(預金の解約・払戻し)は、必要書類が多く、初めての方にとって非常に分かりにくい手続きのひとつです。
銀行ごとに細かな違いはあるものの、銀行相続には共通する「全体の流れ」と「必要書類」があります。
この記事では、銀行相続手続きの共通部分として、
- 銀行相続の全体の流れ
- 共通して必要となる書類
- 口座凍結の注意点
- 手続きをスムーズに進めるポイント
を、初心者の方にも分かりやすく解説します。
この記事で分かること(銀行相続の全体像)
- 銀行相続手続きの共通する流れ
- 銀行相続で必ず必要となる書類
- 口座凍結から払戻しまでの基本ステップ
- 銀行ごとに異なるポイントの考え方
銀行ごとに相続手続きの細かな違いがあるため、以下では主要な銀行別の相続手続きを解説しています。
銀行相続手続きの全体の流れ【共通】
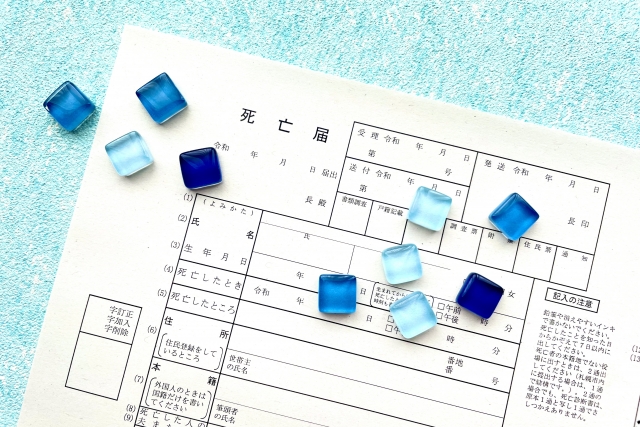
銀行相続は、原則として次の流れで進みます。
- 相続人の確定(戸籍の収集)
- 銀行口座の調査(相続財産の把握)
- 相続放棄の有無を確認する
- 遺産分割協議(誰が預金を相続するか)
- 銀行へ相続手続きの申出を行う
- 必要書類の提出・内容確認審査
- 口座解約・払戻し(相続手続き完了)
① 相続人の確定(戸籍の収集)
まず最初に行うのが、相続人の確定です。
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本等を収集し、法律上の相続人が誰であるかを確認します。
この戸籍収集は、銀行相続だけでなく、すべての相続手続きの出発点となります。
② 銀行口座の調査(相続財産の把握)
次に、亡くなった方がどの金融機関に口座を持っていたかを調査します。
- 通帳
- キャッシュカード
- 引き落とし明細
- クレジットカードの利用履歴
などを手がかりに確認していきます。
手がかりがない場合は、居住地周辺の金融機関に個別に照会する必要があります。
③ 相続放棄の有無を確認する
相続人の中に、相続放棄を検討している人がいないかを確認します。
相続放棄は、家庭裁判所への申立てが必要で、期限は「相続開始を知った日から3か月以内」です。
相続放棄をした人は、最初から相続人でなかったものとして扱われます。
④ 遺産分割協議(誰が預金を相続するか)
相続人が複数いる場合、預金を「誰が・どのように相続するか」を話し合う必要があります。
話し合いがまとまったら、その内容を遺産分割協議書として書面にまとめ、相続人全員が署名・押印します。
この書類は、銀行での払戻し・解約手続きに必須となります。
⑤ 銀行へ相続手続きの申出を行う
遺産分割がまとまったら、各銀行に対して相続手続きを行う旨を申し出ます。
銀行によっては、
- 相続専用窓口
- 郵送手続き
- 予約制窓口
など対応方法が異なります。
⑥ 必要書類の提出・内容確認
銀行から案内された必要書類を提出し、内容の確認・審査が行われます。
不備があると、手続きが止まってしまうため、正確な書類準備が重要です。
⑦ 口座解約・払戻し(相続手続き完了)
書類審査が完了すると、口座の解約・払戻しが行われ、相続人の指定口座へ預金が振り込まれます。
ここまで完了して、銀行相続手続きは終了です。
銀行相続で共通して必要となる書類一覧
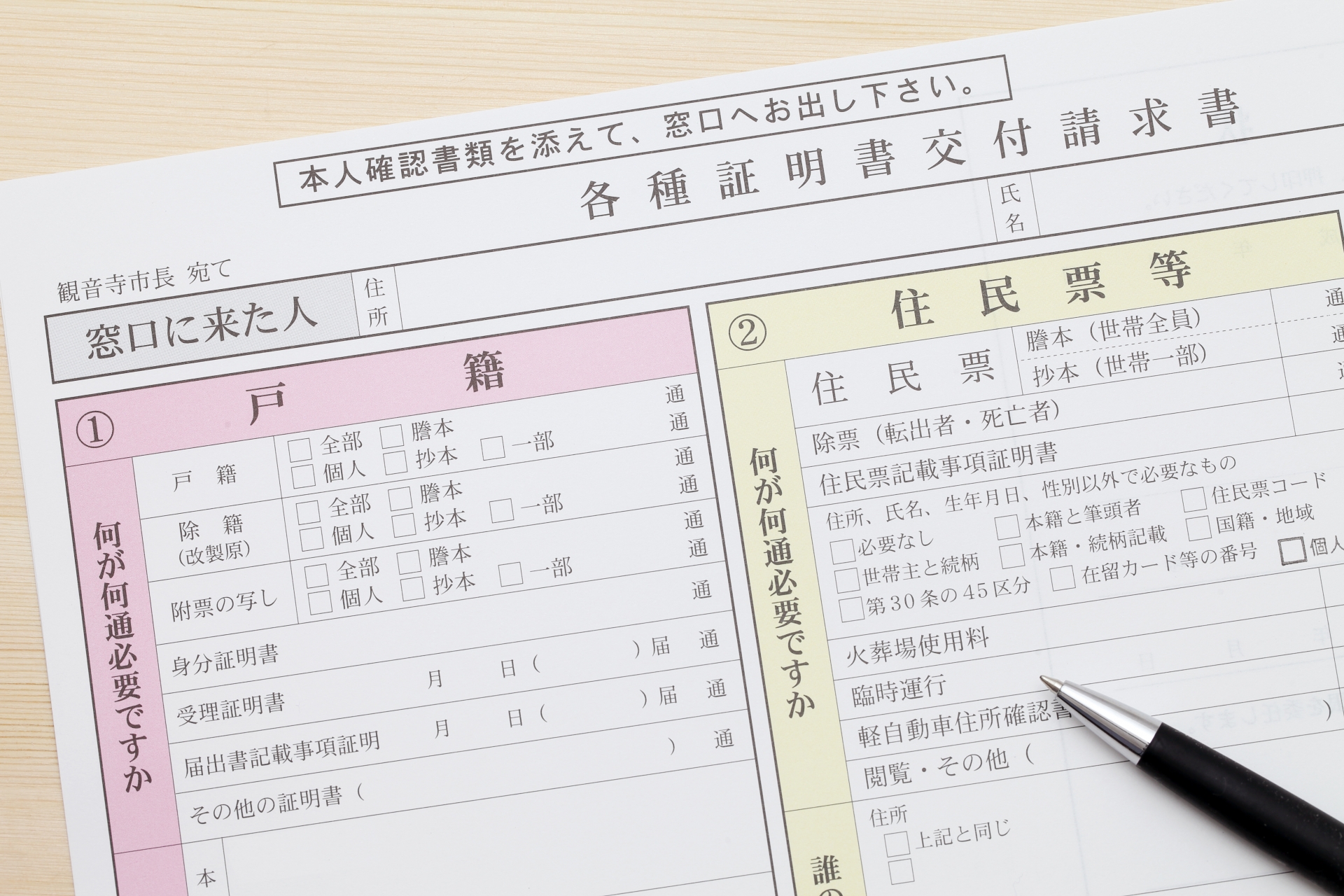
銀行ごとに多少の違いはありますが、一般的に以下の書類が必要になります。
故人に関する書類
- 出生から死亡までの戸籍謄本等
相続人に関する書類
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 代表相続人の本人確認書類
遺産分割協議書・遺言書
- 遺産分割協議書(遺言がない場合)
- 遺言書(ある場合)
銀行所定の相続手続書類
各銀行が指定する書式
銀行口座が凍結されるタイミングと注意点

口座凍結とは何か
銀行が死亡の事実を把握すると、故人名義の口座は凍結され、預金の引き出しや振替ができなくなります。
凍結前に注意すべき支払い・引き落とし
公共料金・家賃・保険料などを故人名義の口座から引き落としている場合、凍結前に支払方法の変更が必要になることがあります。
銀行ごとに異なるポイント(詳細は銀行別記事へ)
銀行相続には共通点が多い一方、次のような点は銀行ごとに異なります。
- 必要書類の原本・コピー要件
- 印鑑証明書の有効期限
- 郵送対応か窓口対応か
- 残高証明書・取引履歴の取得方法
各銀行の具体的な手続きについては、銀行別の記事で詳しく解説しています。
相続税の申告期限と銀行相続の注意点

相続税が発生する場合、申告期限は「死亡した日から10か月以内」です。
銀行相続が遅れると、相続税申告に支障が出る可能性があるため、早めの手続きが重要です。
銀行相続手続きをスムーズに進めるためのポイント
① 必要書類を早めに準備する
銀行での相続手続きには多くの書類が必要ですが、事前にこれらを準備しておくことが手続きのスムーズな進行に繋がります。
特に故人の戸籍謄本や相続人の戸籍謄本などは、役所で取得する必要があるため時間がかかることがあります。
早めに取り寄せておくと、銀行での手続きを早期に開始できます。
② 相続人全員の協力が重要
相続人が複数いる場合、遺産分割協議書を作成する必要があります。
全員が協力し、合意した内容を文書に残すことが必要です。相続人の誰かが相続放棄をする場合も、その手続きを家庭裁判所で行う必要があるため、早めに確認しておきましょう。
③ 銀行の担当者に相談する
銀行での相続手続きに関して不明点がある場合は、早めに銀行の担当者に相談しましょう。
銀行によって必要書類や手続きの方法が異なる場合があるため、事前に確認しておくことが大切です。
また、相続に関する特別な注意事項や期限がある場合もあるため、担当者からのアドバイスを受けるとよいでしょう。
④ 専門家に相談する
銀行の相続手続きをスムーズに進めるためには、専門的な知識とアドバイスを受けることが非常に重要です。
専門家の支援を得ることで、手続きにかかる時間を短縮できるだけでなく、トラブルを未然に防ぐことができます。
まとめ|銀行相続は「共通部分」を理解すると進めやすい
銀行相続手続きは、共通する流れと必要書類を理解することで、全体像が見え、スムーズに進めやすくなります。
不安や疑問がある場合は、早めに専門家へ相談することも検討しましょう。
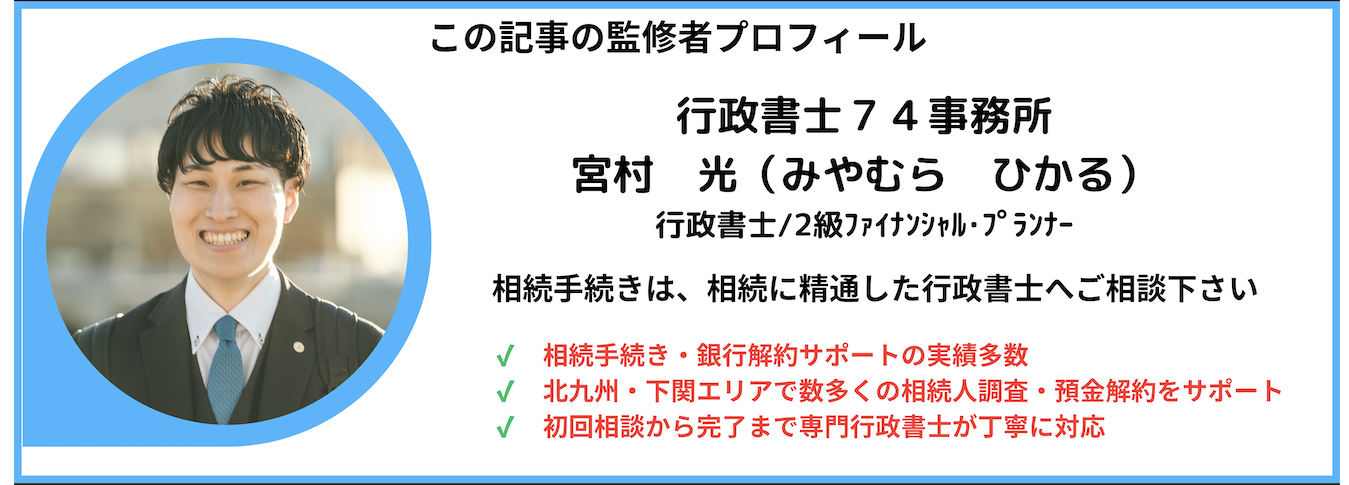
銀行口座の相続・凍結解除でお悩みの方へ
銀行相続の手続きは、必要書類の準備や相続人全員の調整、銀行とのやり取りなど、想像以上に時間と労力がかかるケースが少なくありません。
「何から始めればいいか分からない」
「自分で進めてみたが途中で止まってしまった」
「仕事や家庭の事情で平日に銀行へ行けない」
このような場合は、無理に一人で抱え込まず、専門家に相談することも一つの選択肢です。
行政書士74事務所では、北九州市を中心に、銀行相続手続きに特化したサポートを行っております。
必要書類の整理から銀行窓口での手続きまで、状況に応じて丁寧に対応いたします。
まずは現在の状況をお聞かせください。ご相談内容に応じて、手続きの流れや費用の目安をご案内いたします。
銀行相続手続きの無料相談はこちら
まずはお電話でご連絡ください。
※ご相談だけでも構いません。
※無理な営業や即決をお願いすることはありませんのでご安心ください。
電話が不安な方は、LINE相談も可能です
※「相続相談希望」と送るだけでOK
お問い合わせフォーム
文章で相談したい方はこちら(24時間受付)
『相続相談希望』とメッセージください。