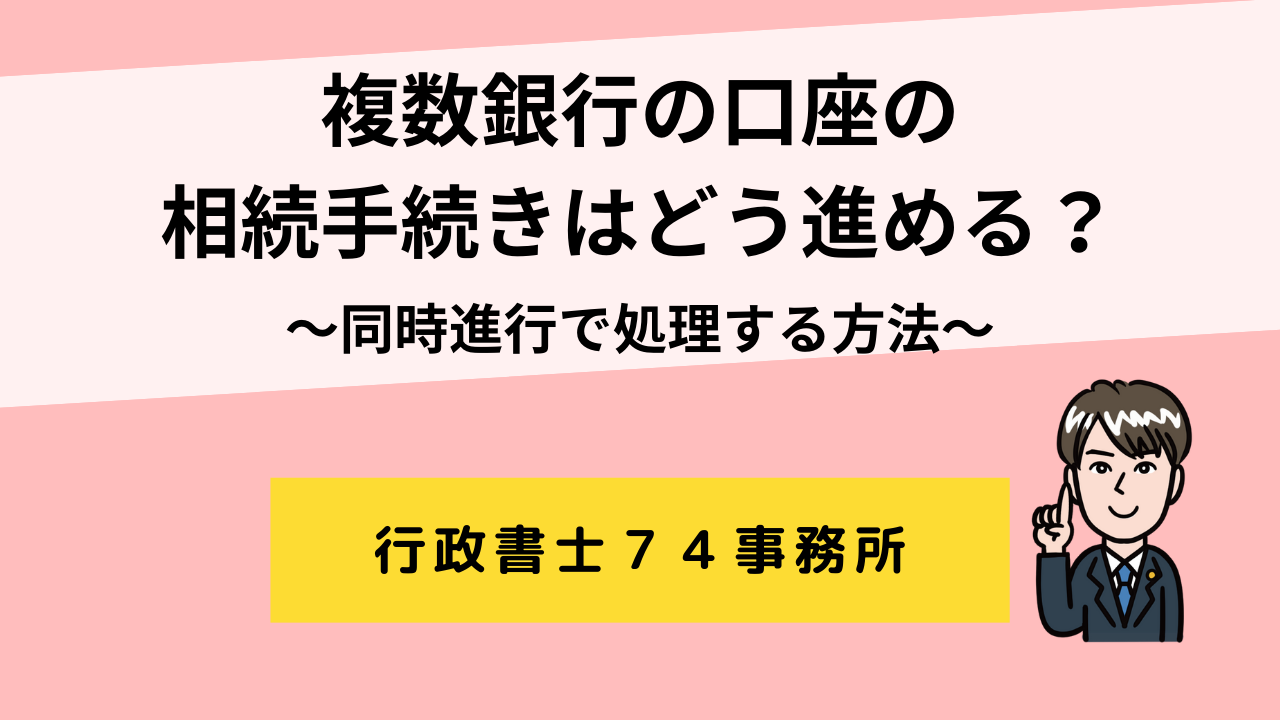親や配偶者など、大切な人が亡くなったとき、悲しみに暮れる間もなく、やってくるのが「相続手続き」です。
中でも特にややこしいのが、「複数の銀行に口座がある場合」の対応。
「どこから手をつけたらいいの?」「手続きって同時に進めていいの?」と悩む方も多いのではないでしょうか。
本記事では、複数の銀行口座を相続する際の手順と、手続きを効率よく同時進行させるためのコツを、初心者向けに分かりやすく解説します。
複数口座の相続手続きが大変な理由
まずは、なぜ複数の銀行口座があると相続が面倒になるのかを理解しましょう。
● 銀行ごとに書類や手順が違う
相続手続きは、銀行によって必要書類や提出方法、所要時間が異なります。
A銀行では通る書類でも、B銀行では受け付けられない…なんてことも珍しくありません。
● 凍結された口座はお金が引き出せない
名義人が亡くなると、銀行口座は即座に凍結され、出金や振込ができなくなります。
葬儀費用や税金の支払いに困るケースもあるため、早めの対応が必要です。
● 手続きを並行して進めないと時間がかかる
1つ1つの銀行とやり取りしていたら、数か月かかることも。
可能であれば、複数の銀行と同時進行で手続きを進めるのが理想的です。
まずは全体像を把握しよう
【STEP1】どの銀行に口座があるかをリストアップ
故人(被相続人)がどの銀行に口座を持っていたのか、確認しましょう。
通帳やキャッシュカード、郵便物をチェックするのが基本です。
チェックリストの例
| 銀行名 | 支店名 | 種別 | 残高 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| ○○銀行 | 北九州支店 | 普通 | 約30万円 | 年金振込口座 |
| △△信金 | 下関営業部 | 定期 | 約150万円 | 貯金用 |
【STEP2】誰が相続人かを確定する
相続手続きには「法定相続人」が必要です。以下の書類で確認します。
- 戸籍謄本(出生から死亡まで連続したもの)
- 除籍謄本(亡くなった方の情報)
- 相続人全員の戸籍謄本・住民票
◆ 銀行口座の相続に必要な書類
銀行ごとに違いはありますが、共通して必要になる代表的な書類は以下の通りです。
基本書類
- 被相続人の戸籍謄本(出生~死亡まで連なるもの)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人の印鑑証明書
- 遺言書(ある場合)
- 遺産分割協議書(遺言書がない場合)
- 相続人全員の実印
銀行ごとの書類(例)
- 各銀行の所定の相続届
- 通帳・キャッシュカード
- 代表相続人単独や代理人が手続きを行う場合は相続人の委任状
1通の戸籍を複数銀行に提出する必要があるため、必要部数取得しておくのがベター。
原本還付ができるかも各銀行に確認しましょう。
同時進行のための5つのコツ
① 手続き優先順位を決める
特に重要な口座(多額の資産がある、公共料金の引き落としがある等)から先に手続きしましょう。
② 進捗管理を「見える化」
Excelやノートで進捗を管理すると混乱しません。
| 銀行名 | 必要書類提出 | 書類確認中 | 手続き完了 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ○○銀行 | 4/5 済 | 4/10 連絡あり | 4/18 完了 | 定期預金あり |
③ 銀行に事前確認の電話を入れる
「書類は何が必要?」「郵送でもOK?」と確認しておくと、無駄足を防げます。公式HPも参考になります。
④ オンライン・郵送手続きも活用
最近では郵送対応やネットバンキングでの手続きが可能な銀行も増えています。
特に遠方の支店にある口座は、無理に行かずとも手続きできることが多いです。
⑤ 法定相続情報一覧図制度を活用する
「1部提出して、また取り寄せて…」という手間を防ぐためには、戸籍をあらかじめ多めに準備しておくのが理想です。
しかし、同じ戸籍を何通も取り寄せるのは、時間も費用もかかって大変です。
そこでおすすめなのが「法定相続情報一覧図制度」の利用です。
この制度を利用すると、法務局が相続人関係を確認したうえで、無料で認証文付きの「相続関係図(法定相続情報一覧図)」を発行してくれます。必要な部数を何通でも取得できるため、とても便利です。
法定相続情報一覧図は戸籍謄本の代わりとして利用できるため、あらかじめ複数部取得しておけば、各銀行での相続手続きもスムーズに進められます。
よくあるQ&A
Q. 亡くなった方が開設していた銀行口座がわからない場合は?
A. 郵便物・通帳・年金の振込口座などから手がかりを探します。
また、マイナンバーの利用による預貯金口座の管理に関する制度を利用して、どの金融機関に口座があるか調べることも可能です(遺族が手続き可能)。
Q. 遺言書がある場合は、遺産分割協議書は不要?
A. 原則として遺言がある場合は遺産分割協議書は不要です。
Q. 相続人が遠方に住んでいる場合はどうする?
A. 郵送で印鑑証明書や委任状の準備をしてもらい、やり取りすればOK。
相続代表者(代表して手続きする人)を決めるとスムーズです。
トラブル防止のために
- 相続人が複数いる場合は、必ず全員の同意を得てから進める
- 1人だけで勝手に進めると、後でトラブルに発展することも
- 紛争が起きていて、協議が難しい場合は、専門家(弁護士)に相談する
まとめ 落ち着いて、ひとつずつ
相続手続き、とくに複数の銀行にまたがる場合は大変に思えるかもしれません。
でも、必要な情報を整理して、書類をまとめて、少しずつ進めていけば大丈夫です。
「今どこまで進んでいるか?」を見える形で管理しておけば、複数口座の同時進行も決して難しくありません。
また、法定相続情報一覧図制度を利用することで、かなりの負担が軽減されますので活用しましょう。
心の整理と一緒に、大切な人の財産も丁寧に引き継いでいきましょう。
もし、それでも相続手続きをするのが難しいという方におすすめなのが、行政書士74事務所の「銀行の相続手続き代行サービス」です。
手間なく銀行口座を解約! 銀行の相続手続き代行サービス
行政書士74事務所では、銀行の相続口座解約手続きをサポートしております。
- 「相続手続きが複雑で進められない」
- 「できるだけ早く手続きを終わらせたい」
- 「平日は忙しくて時間が取れない」
このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所へご相談ください。
当事務所は、北九州市で唯一、銀行相続手続きに専門特化した行政書士事務所です。
これまで5年にわたり、北九州市や下関市の銀行を中心に、数多くの相続手続きをサポートしてまいりました。
相続書類の準備から窓口での解約手続きまで、専門家が一貫して対応いたします。
ご不安を解消し、確実に相続手続きを完了させたい方は、どうぞ安心してお任せください。
現在では、どこの銀行も郵送手続きができるところも増えてまいりましたので、全国対応しています。(一部未対応あり)
まずは、お電話 または お問い合わせフォーム より、今すぐお気軽にご相談ください。
一人で悩む前に、まずは無料相談で今後の道筋を立てて、不安を解消しませんか?
無料相談申込とご依頼の流れは以下より
ご依頼の流れ

お電話・下記のお問い合わせフォームより
お問い合わせください。

【お電話の場合】
お客様のご都合を伺わせていただき決定します。
【お問い合わせフォームの場合】
お問い合わせの内容を確認次第、
こちらからご連絡させていただきます。
その際ご面談の日時や場所を
お客様のご都合を伺いながら決定します。

お客様のお悩みを伺い、最善の方法で
お悩みを解決できるようご提案いたします。

ご面談の内容に納得・合意頂けましたら
ご契約の手続きをします。

原則、着手金として基本料金をお預かりしております。
(業務に迅速に取り掛かるため3日以内に銀行口座へのお振り込みをお願いしています。)
※契約書に署名捺印していただいた方は後払い可

着手金のお振込みの確認若しくは委任契約の合意ができ次第、業務を開始します。

定期的(2週間に1回程度)に業務の進行状況等のご連絡をいたします。

業務が全て完了しましたら
その旨のご連絡をいたします。

手数料の合計と実費等の精算をしまして
5日以内に完了金をお支払いして頂きます。
5日以内にお支払いが難しい場合は、
臨機応変にご対応しますのでご相談ください。
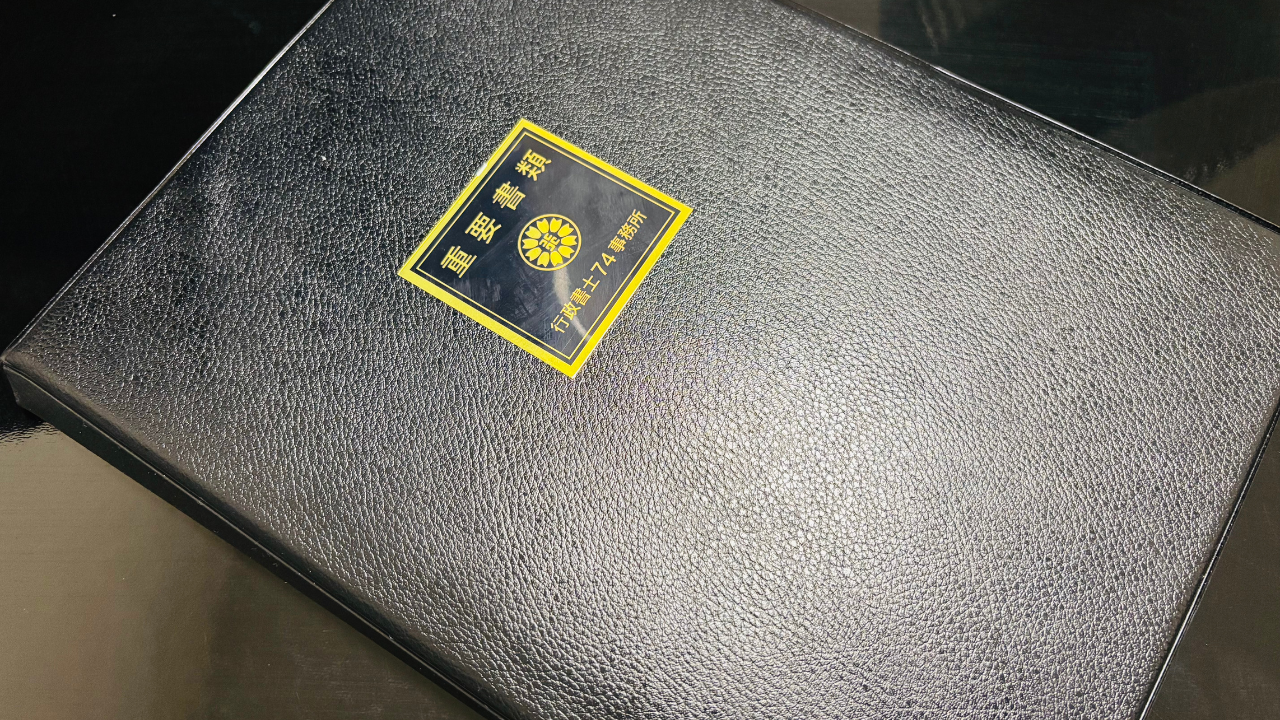
最終的に弊所が行った業務内容について
ご説明し書類等の納品をします。
お問い合わせフォーム
お電話もしくは下記お問い合わせフォームよりご連絡をお願いいたします。
LINEではトーク画面のメッセージからでもご相談可能です。
『相談希望』とメッセージください。