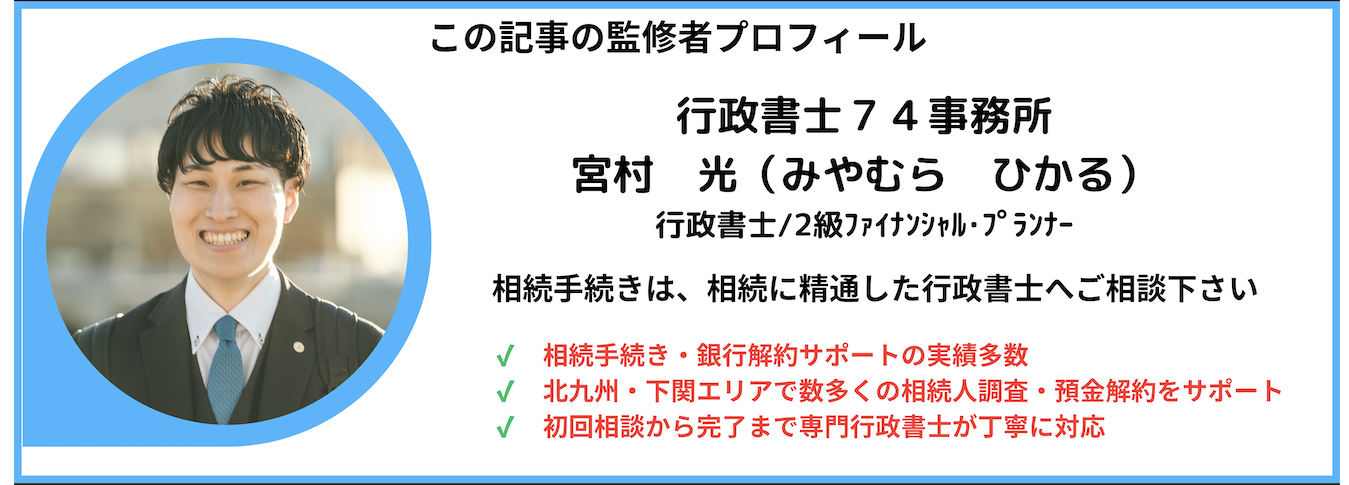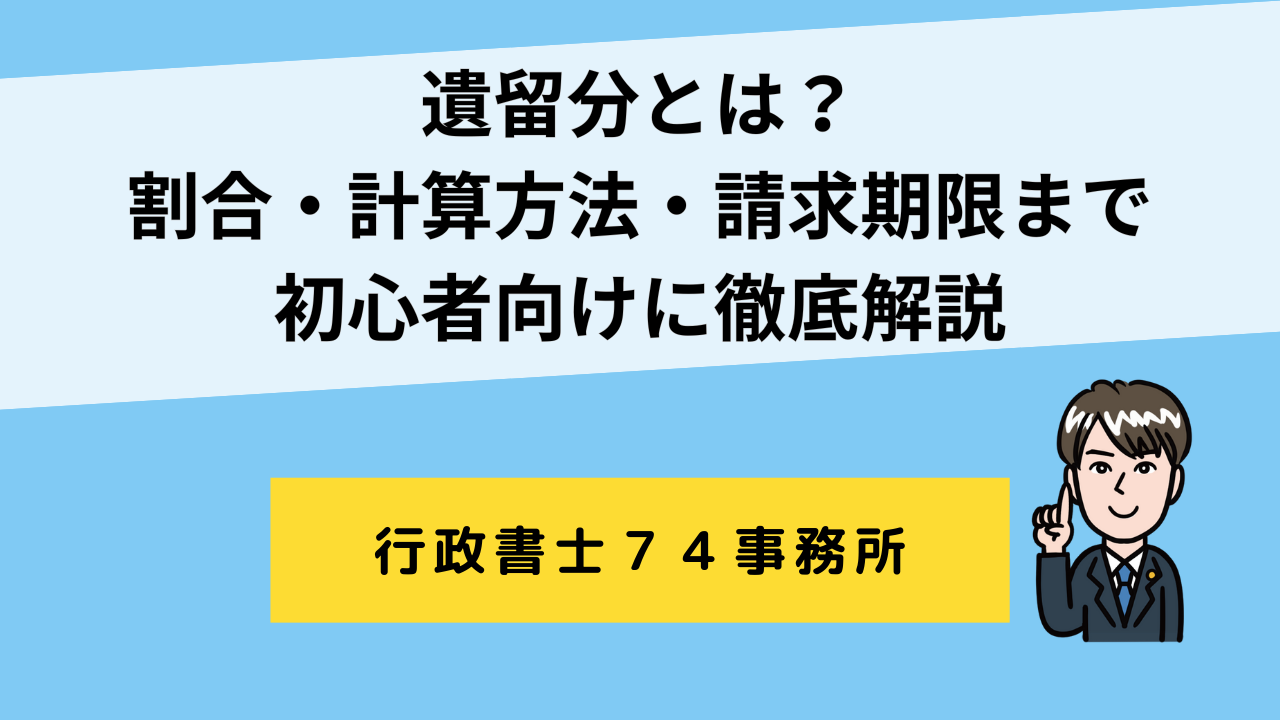はじめに
相続の話になると、「遺言があればすべてその通りになる」と思われている方は少なくありません。
しかし実際には、遺言があっても必ず守られる相続人の権利があります。
それが「遺留分(いりゅうぶん)」です。
遺留分を知らないまま相続が始まると、
- もらえるはずの財産を受け取れなかった
- 期限を過ぎて請求できなくなった
といった後悔につながるケースもあります。
この記事では、相続初心者の方に向けて、遺留分の基本を民法の条文をもとに、できるだけわかりやすく解説します。
遺留分とは?簡単にいうと何?
遺留分とは、一定の相続人に最低限保障される取り分のことです。
たとえ被相続人が「全財産を特定の人に相続させる」という遺言を書いていたとしても、法律上守られる相続人の権利まで奪うことはできません。
そのため、
- 特定の相続人に偏った遺言
- 生前贈与による財産の移転
があった場合でも、遺留分を侵害された相続人は、金銭での請求が認められています。
遺留分が認められる相続人・認められない相続人
遺留分がある人
民法第1042条により、遺留分が認められるのは次の相続人です。
- 配偶者
- 子(代襲相続人を含む)
- 直系尊属(父母・祖父母など)
遺留分がない人
- 兄弟姉妹には遺留分はありません
この点は非常に重要で、兄弟姉妹が相続人であっても、遺留分を請求することはできません。
遺留分の割合はどれくらい?
遺留分全体の割合
民法1042条1項では、遺留分の割合を次のように定めています。
- 直系尊属のみが相続人の場合 → 相続財産全体の3分の1
- それ以外の場合(配偶者や子がいる場合) → 相続財産全体の2分の1
各相続人の遺留分
相続人が複数いる場合は、この割合を法定相続分に応じて配分します。(民法1042条2項)
たとえば、配偶者と子1人が相続人の場合、遺留分はそれぞれ「4分の1ずつ」となります。
遺留分を計算するための財産とは?
遺留分は、単に「残っている財産」だけで計算されるわけではありません。
基本となる計算方法(民法1043条)
相続開始時に持っていた財産
+ 一定期間内の生前贈与
- 借金などの債務この合計額をもとに、遺留分が計算されます。
生前贈与はどこまで遺留分に影響する?
原則:相続開始前1年以内の贈与
民法1044条では、原則として相続開始前1年以内の贈与が遺留分算定の対象になります。
例外①:遺留分を害すると知っていた場合
贈与した人と受け取った人が、「遺留分を侵害すること」を知っていた場合には、1年より前の贈与も対象となります。
例外②:相続人への贈与は10年
相続人に対する
- 婚姻
- 養子縁組
- 生計の資本
としての贈与は、相続開始前10年分までさかのぼって計算されます。
遺留分が侵害された場合の請求方法
現在の民法では、遺留分が侵害された場合、遺留分侵害額請求として「金銭」で請求します。(民法1046条)
以前のように、「財産そのものを取り戻す」制度ではありません。
誰が支払うのか?負担のルール
民法1047条では、負担の順番が定められています。
- 遺言によって財産を取得した人(受遺者)
- 生前贈与を受けた人(受贈者)
複数いる場合は、
- 同時の贈与 → 価額に応じて按分
- 時期が異なる贈与 → 後の贈与から先に負担
となります。
遺留分侵害額請求には期限がある
遺留分侵害額請求は、いつまでもできるわけではありません。
消滅時効(民法1048条)
- 遺留分侵害を知ったときから 1年
- 相続開始から 10年
いずれか早い方で、請求権は消滅します。
「そのうち話し合えばいい」と放置してしまうと、法的に請求できなくなる可能性があります。
遺留分の放棄はできる?
相続開始前に遺留分を放棄することは可能ですが、家庭裁判所の許可が必要です。(民法1049条)
口約束や私的な合意だけでは、法的な効力はありません。
まとめ|遺留分は早めの確認が重要
遺留分は、
- 自動的に支払われるものではない
- 請求期限がある
- 計算が複雑
という特徴があります。
特に、
- 生前贈与が多い
- 遺言内容に偏りがある
- 相続人同士の関係が微妙
このようなケースでは、早めに専門家へ相談することで、無用なトラブルを防ぐことができます。