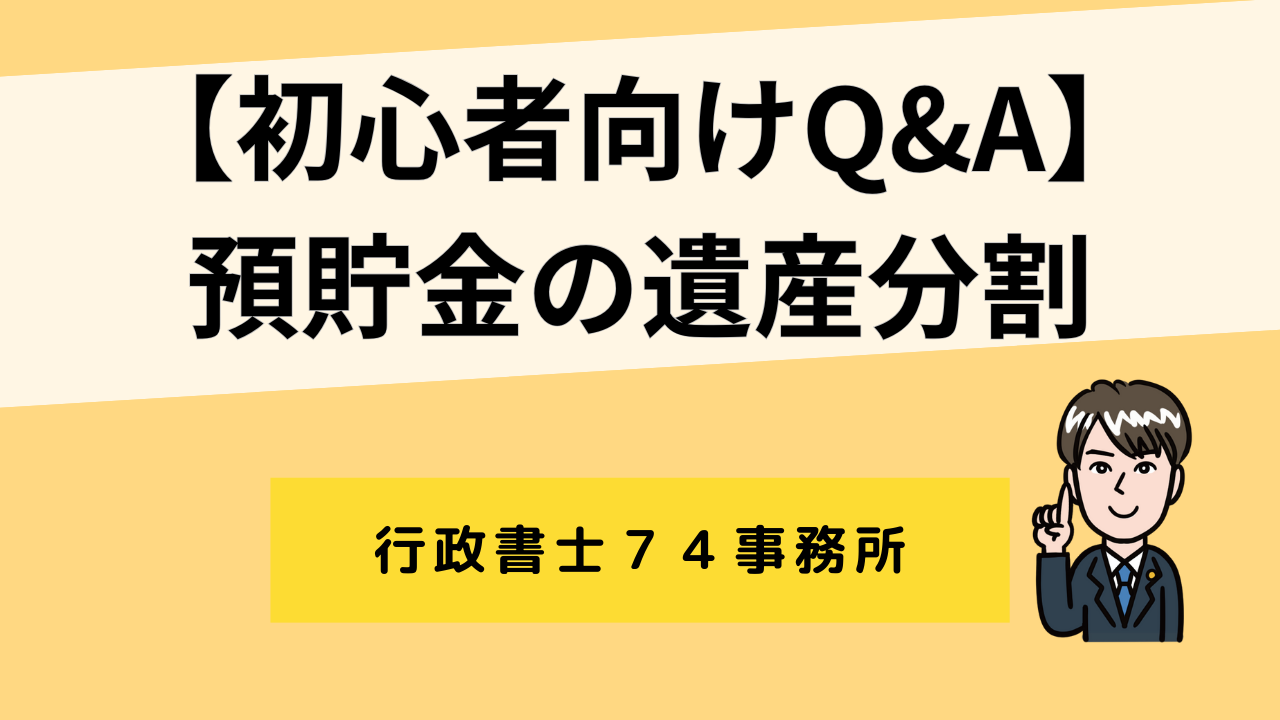相続の手続きが必要になったとき、まず出てくるのが「預貯金をどうやって分けるのか?」という疑問です。
不動産のように登記の手続きがない分、簡単そうに見えて、実は誤解やトラブルの多い分野でもあります。
この記事では、預貯金の遺産分割について初心者の方でも安心して理解できるように、よくある疑問をQ&A方式で解説していきます。
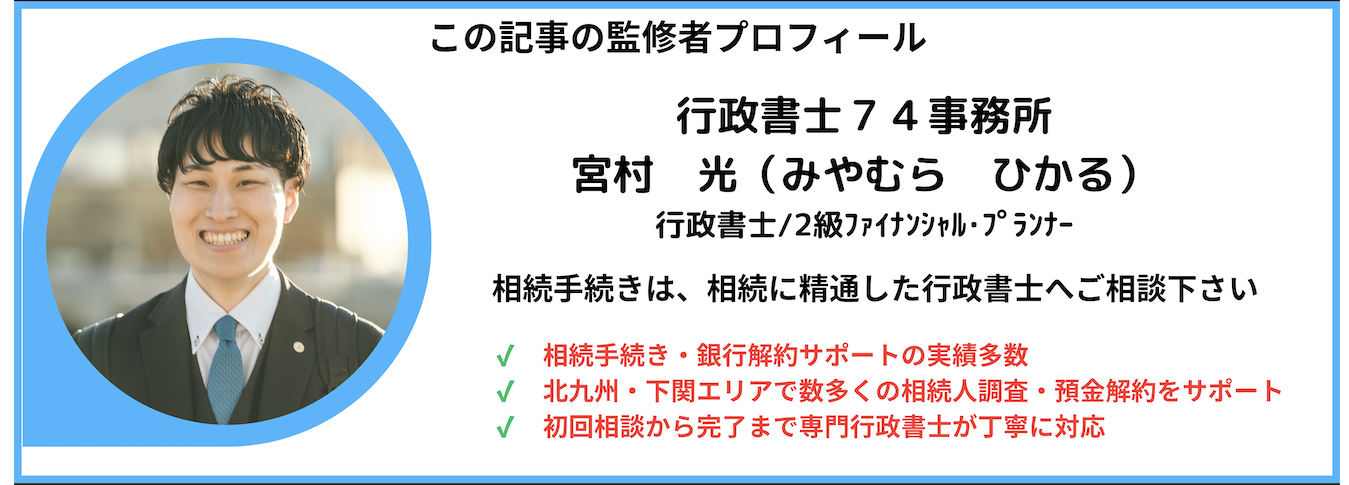
北九州市で銀行相続の手続きが必要な方へ
✔ 忙しくて役所・銀行に行く時間がない
✔ 必要書類が多くて準備できない
✔ 相続人が遠方で手続きが進まない
✔ 専門家に全て任せたい
このようなお悩みは、当事務所がワンストップで解決します。出張費無料で北九州全域に対応しています。
※今すぐ銀行の相続手続きを解決したい方は、お電話にてお問い合わせくださいませ。
Q1. 預貯金も「相続財産」になるの?
A:はい。銀行口座の預金や定期預金はすべて相続財産になります。
預貯金は、亡くなった人(被相続人)の名義で持っていたお金のことで、土地や家と同じように、相続人で分ける対象となります。
銀行口座の残高が1円でも1,000万円でも、それは「相続財産」として扱われます。
Q2. 口座のお金ってすぐに引き出せるの?
A:いいえ。亡くなったことが銀行に伝わると、口座は凍結され、引き出しできなくなります。
金融機関は、本人の死亡が確認されると、その口座を凍結します。
凍結後は、相続手続きが完了するまでお金を動かせません。
これは、不正な引き出しやトラブルを防ぐための仕組みです。
また勝手に引き出すと相続放棄ができなくなる可能性がありますので、絶対にやめてください。
Q3. 凍結された口座のお金はどうやってもらえるの?
A:必要書類を準備し、金融機関に相続手続きを申し込むことで、相続人がそれぞれ受け取ることができます。
具体的には以下の手順が必要です。
- 相続人全員を確認できる戸籍謄本等を集める
- 誰がどのように遺産を分けるかを話し合い、「遺産分割協議書」を作成
- 金融機関に必要書類を提出し、各相続人の口座に振り込んでもらう
これだけ見ると簡単そうに見えますが、必要書類の収集は思っているよりも難しく、銀行によっても取り扱いが異なるので注意が必要です。
Q4. 法定相続分ってなに?
A:法律で決められた「相続人ごとの取り分」のことです。
例)配偶者と子ども1人が相続人の場合
- 配偶者:1/2
- 子ども:1/2
ただし、この法定相続分は「目安」であり、実際には相続人全員で協議して、違う割合にすることも可能です。
Q5. 遺言書がある場合はどうなるの?
A:遺言書の内容が優先されます。
被相続人が生前に遺言書を残していた場合、その内容に従って遺産が分けられます。
特に公正証書遺言の場合は、裁判所の検認手続きも不要で、スムーズに手続きを進めることができます。
ただし、遺留分という最低限の取り分が法律で保障されている相続人もいるため、全員が納得しないとトラブルになることもあります。
Q6. 預貯金の相続手続きに必要な書類は?
A:主に以下の書類が必要です。
- 被相続人の死亡がわかる戸籍(出生から死亡までの連続したもの)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書(全員の署名・実印)
- 金融機関の相続届など所定の様式
※金融機関によって必要な書類が少し異なる場合があります。事前に確認しましょう。
Q7. 複数の口座がある場合は?
A:それぞれの銀行で個別に手続きをする必要があります。
たとえばA銀行とB信用金庫に口座がある場合、それぞれの金融機関で同じような書類を提出して相続手続きを行う必要があります。
多少面倒ですが、まとめて一括ではできません。
Q8. 遺産分割協議って何をするの?
A:誰がどの財産をどれだけ相続するか、相続人全員で話し合うことです。
預貯金も不動産も、相続人全員が話し合って「このように分ける」と合意する必要があります。
その内容を「遺産分割協議書」として文書にまとめて、全員が署名・実印を押すことで正式な協議結果となります。
Q9. 協議がまとまらなかったらどうするの?
A:家庭裁判所の「遺産分割調停」を利用できます。
相続人の中で意見が合わなかったり、話し合いができない状況の場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
第三者である調停委員が間に入って、冷静に話し合える場を提供してくれます。
Q10. 葬儀費用を相続人の一人が立て替えた場合は?
A:協議の中で、その人に優先的に返すように調整するのが一般的です。
例えば長男が100万円の葬儀費用を先に支払っていたら、相続人全員で話し合って「その分を長男に返す」ことを協議書に記載すればOKです。
ただし、誰にも相談せず勝手に支出していた場合、トラブルになることもあるため注意が必要です。
事前に葬儀費用の負担はどうするかということを、相続人間で話し合って進めましょう。
Q11. 相続税はかかるの?
A:一定の金額を超えると課税対象になります。
基礎控除額の計算式は以下の通りです。
3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
例:相続人が3人なら → 3,000万円 + (600万円 × 3) = 4,800万円まで非課税
相続財産がこれを超える場合は、相続税の申告が必要になります。
相続財産の評価額を間違えると、相続税の申告が必要だったということになりかねませんので、具体的な金額はしっかりと各財産の証明書を取得して確認しましょう。
自分で計算するのが難しい場合には、税理士に相談することをおすすめします。
預貯金の相続手続きでお悩みなら
行政書士74事務所は、北九州市門司区を中心に、銀行の相続手続きに特化したサポートを行っております。
「相続手続きが難しくて進められない」「相続手続きをできるだけ早く完了させたい」とお考えの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。
当事務所では、銀行の相続手続きに特化した専門的な支援を行っており、北九州市内で唯一、銀行相続手続きに専門特化した行政書士事務所として実績を積んでおります。
これまで約5年間、北九州市および下関市内のほとんどの銀行で手続きをサポートして参りました。
預貯金手続きの必要書類の準備から窓口での手続きまで、迅速かつ確実に対応し、お客様のご不安を解消いたします。
お問い合わせは、お電話または下記のお問い合わせフォームからお受けしております。
また、公式LINEにてチャットでのご相談も無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
ご依頼の流れ
お電話・下記お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
【お電話の場合】
お電話でお客様のご都合を伺わせていただき決定します。
【お問い合わせフォームの場合】
お問い合わせの内容を確認次第、こちらからご連絡させていただきます。
その際ご面談の日時や場所をお客様のご都合を伺いながら決定します。
お客様のお悩みを伺い、最善の方法でお悩みを解決できるようご提案いたします。
ご面談の内容に納得・合意頂けましたらご契約の手続きをします。
原則、着手金として基本料金をお預かりしております。
(指定銀行口座へお振込み)
残額は業務完了後にお支払い頂きます。
(10万円未満の場合は全額を基本料として頂戴しております。)
着手金のお振込みの確認 若しくは委任契約の合意ができ次第、業務を開始します。
定期的に業務の進行状況等のご連絡をいたします。
業務が全て完了しましたらその旨のご連絡をいたします。
最終的に弊所が行った業務内容についてご説明し書類等の納品をします。
手数料の合計と実費等の精算をしまして3日以内に完了金をお支払いして頂きます。
お問い合わせフォーム
お電話もしくは下記お問い合わせフォームよりご連絡をお願いいたします。
LINEではトーク画面のメッセージからでもご相談可能です。
『相談希望』とメッセージください。