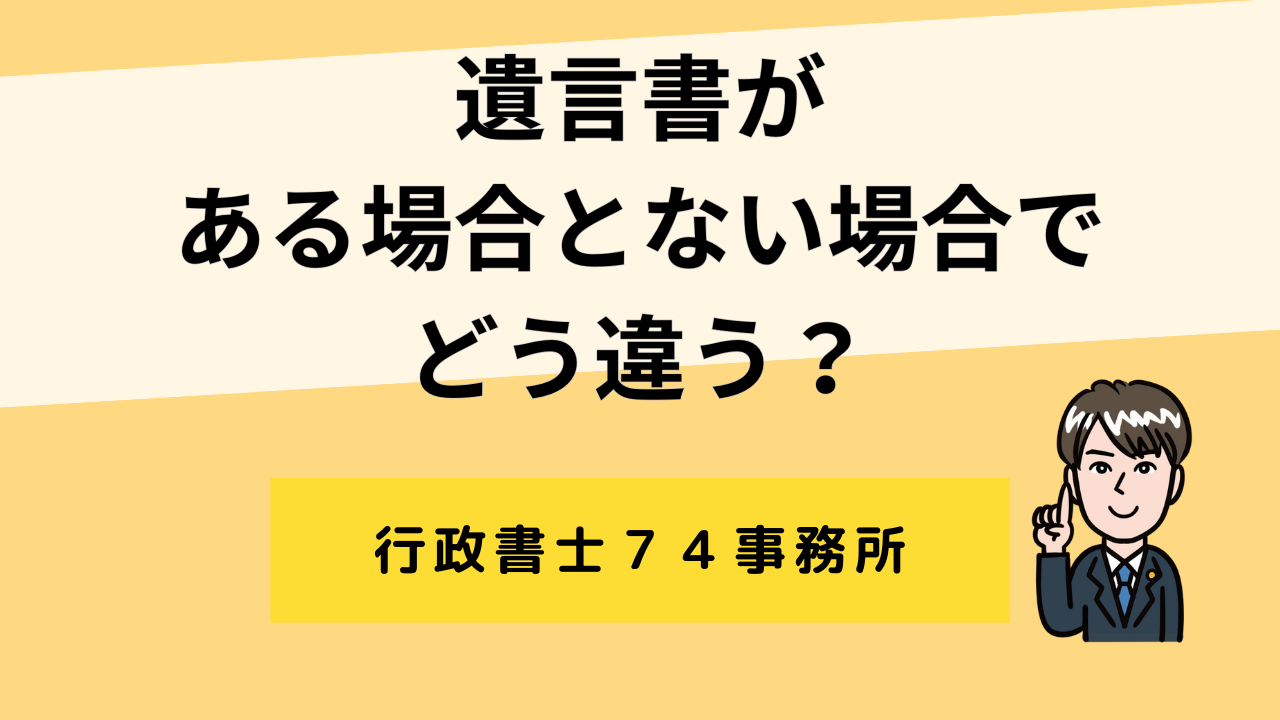はじめに 相続は「遺言書の有無」で大きく変わる
身内が亡くなった後に行う「相続手続き」。
財産をどう分けるか、誰が相続人になるか、どんな手続きを取ればいいのか……不安や戸惑いを感じる方も多いのではないでしょうか。
そのとき、大きな分かれ道になるのが「遺言書があるかどうか」です。
遺言書があれば、基本的にその内容に沿って相続が進みますが、ない場合は法律(民法)に従って、相続人全員で話し合って決める必要があります。
この記事では、遺言書が「ある場合」と「ない場合」で、相続手続きにどんな違いがあるのかを初心者の方にもわかりやすく解説します。
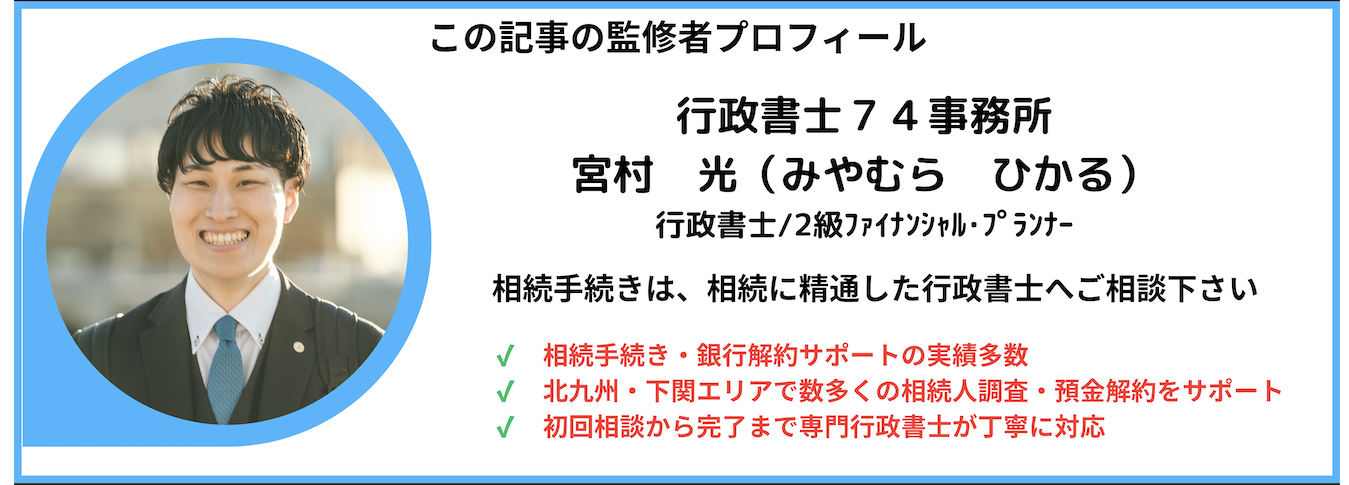
まず知っておきたい 遺言書ってどんなもの?
遺言書とは、亡くなった人が「自分の財産をどう分けてほしいか」などを記した正式な意思表示の書面です。
法的効力があるため、きちんとした形で残されていれば、基本的にはその内容が優先されます。
遺言書には3つのタイプがあります
- 自筆証書遺言:本人が手書きで作成。法務局で保管制度あり。
- 公正証書遺言:公証人役場で作成。最もトラブルが少ない。
- 秘密証書遺言:内容を秘密にしたまま公証役場で認証。
【比較】遺言書がある場合 vs ない場合の相続手続き
以下では、遺言書の「有無」によって、実際にどのような手続きの違いがあるのかを見ていきましょう。
1.財産の分け方(誰が何を相続するか)
| 遺言書がある場合 | 遺言書に書かれている通りに分ける(基本的に自由に指定できる) |
|---|---|
| 遺言書がない場合 | 法定相続分に基づき、相続人全員で話し合って決める |
遺言書があると「特定の人に多く相続させる」や「内縁の妻にも遺産を残す」など、被相続人の意思を反映できます。一方、遺言書がない場合は、法律に従って平等に分けるのが原則です。
2.遺産分割協議が必要かどうか
| 遺言書がある場合 | 原則として不要。ただし、全員の合意があれば遺言と違う分け方も可能 |
|---|---|
| 遺言書がない場合 | 必要。相続人全員で「誰が何を相続するか」を話し合って決める |
遺産分割協議には、全相続人の同意と実印、印鑑証明書が必要。ひとりでも反対すると手続きが進まないため、揉める原因にもなりがちです。
3.家庭裁判所の関与(検認の有無)
| 遺言書がある場合 | 自筆証書遺言:検認が必要/公正証書遺言:検認不要 |
|---|---|
| 遺言書がない場合 | 検認不要 |
自筆証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所で「検認」という手続きが必要になります。これは、内容の有効性を確認し、改ざんを防ぐためのものです。
公正証書遺言であれば、検認が不要なため、手続きがスムーズです。
4.相続手続きのスピード感
| 遺言書がある場合 | 比較的スムーズに進められる(特に公正証書遺言) |
|---|---|
| 遺言書がない場合 | 話し合いや書類準備に時間がかかる可能性が高い |
「誰が何をもらうか」が遺言で決まっていれば、相続人間での争いが起きにくく、手続きも迅速。一方、遺言がない場合は協議が長引いたり、連絡が取れない相続人がいると、手続きが数ヶ月〜1年以上かかることもあります。
【実例で比較】こんなに違う!手続きの流れ
▼遺言書がある場合(公正証書)
- 死亡届提出、火葬許可など初期手続き
- 戸籍の収集(相続人の確認)
- 公正証書遺言を開示
- 遺言の内容に従って財産を名義変更(銀行・不動産など)
- 相続税の申告(必要な場合)
遺産分割協議が不要なため、相続人が遠方にいても手続きしやすい!
▼遺言書がない場合
- 死亡届提出、火葬許可など初期手続き
- 戸籍の収集(相続人の確認)
- 財産調査
- 相続人全員で遺産分割協議
- 遺産分割協議書の作成と押印
- 各種名義変更
- 相続税の申告(必要な場合)
遺産分割協議がまとまらないと次に進めない。相続人の数が多いほど難航。
【注意点】遺言書があっても完全ではない?
「遺言書があるから大丈夫」と思いがちですが、いくつか注意点もあります。
● 相続人の遺留分に注意
遺言で特定の人に全財産を与えると書いてあっても、法律で守られた最低限の取り分(遺留分)が他の相続人には認められています。
相続人は「遺留分侵害額請求」という権利を行使することができます。
● 内容があいまいだとトラブルに
「長男に任せる」「家は好きに使ってよい」など、法的に不明確な表現は無効になることもあります。
【まとめ】遺言書があるかどうかで、ここまで変わる!
| 比較項目 | 遺言書あり(特に公正証書) | 遺言書なし |
|---|---|---|
| 財産の分け方 | 遺言書に従う | 法定相続分を目安に協議が必要 |
| 遺産分割協議 | 原則不要 | 相続人全員の合意が必要 |
| 家庭裁判所の手続き | 自筆証書のみ検認が必要 | 不要 |
| 手続きの手間・期間 | スムーズ | 時間がかかる可能性大 |
| トラブルのリスク | 少ない(内容が明確なら) | 高め(揉める可能性あり) |
おわりに 遺言書は「家族への最後のメッセージ」
相続手続きは、単なる書類上の問題ではなく、家族の関係性や気持ちにも深く関わるものです。
遺言書があれば、家族間の争いを未然に防ぎ、スムーズな手続きを助けてくれます。
逆に、遺言書がないと、「こんなはずじゃなかったのに…」と後悔するケースも少なくありません。
自分の思いを伝える手段として、また、残された家族の負担を減らすためにも、生前から遺言書について考えておくことが、これからの時代にはますます大切になってくるでしょう。
そういうときは、相続の専門家に任せることも1つの手段です。
相続のプロと作る!公正証書遺言 作成支援サービス
当事務所は、下関市・北九州市を中心に、相続専門の行政書士事務所として、遺言や相続に関するさまざまなサポートを行っております。
「一人で遺言書を作成するのは不安…」「手続きが複雑でよくわからない…」とお悩みの方もご安心ください。
相続に強い行政書士が、お客様に寄り添いながら丁寧にサポートいたします。
当事務所では、お客様に代わって
- 遺言書の原案作成
- 公証人との打ち合わせ
- 証人の手配
などをすべて一括で対応いたします。
ご相談・お問い合わせは、お電話または下記のお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。
また、公式LINEにて無料のチャット相談も受け付けております。
「ちょっと聞いてみたい」という内容でも構いませんので、お気軽にご利用ください。
ご依頼の流れ
お電話・下記お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
【お電話の場合】
お電話でお客様のご都合を伺わせていただき決定します。
【お問い合わせフォームの場合】
お問い合わせの内容を確認次第、こちらからご連絡させていただきます。
その際ご面談の日時や場所をお客様のご都合を伺いながら決定します。
お客様のお悩みを伺い、最善の方法でお悩みを解決できるようご提案いたします。
ご面談の内容に納得・合意頂けましたらご契約の手続きをします。
原則、着手金として基本料金をお預かりしております。
残額は業務完了後にお支払い頂きます。
(10万円未満の場合は全額を基本料として頂戴しております。)
着手金のお振込みの確認 若しくは委任契約の合意ができ次第、業務を開始します。
定期的に業務の進行状況等のご連絡をいたします。
業務が全て完了しましたらその旨のご連絡をいたします。
手数料の合計と実費等の精算をしまして3日以内に完了金をお支払いして頂きます。
最終的に弊所が行った業務内容についてご説明し書類等の納品をします。
お問い合わせフォーム
お電話もしくは下記お問い合わせフォームよりご連絡をお願いいたします。
LINEではトーク画面のメッセージからでもご相談可能です。
『相談希望』とメッセージください。