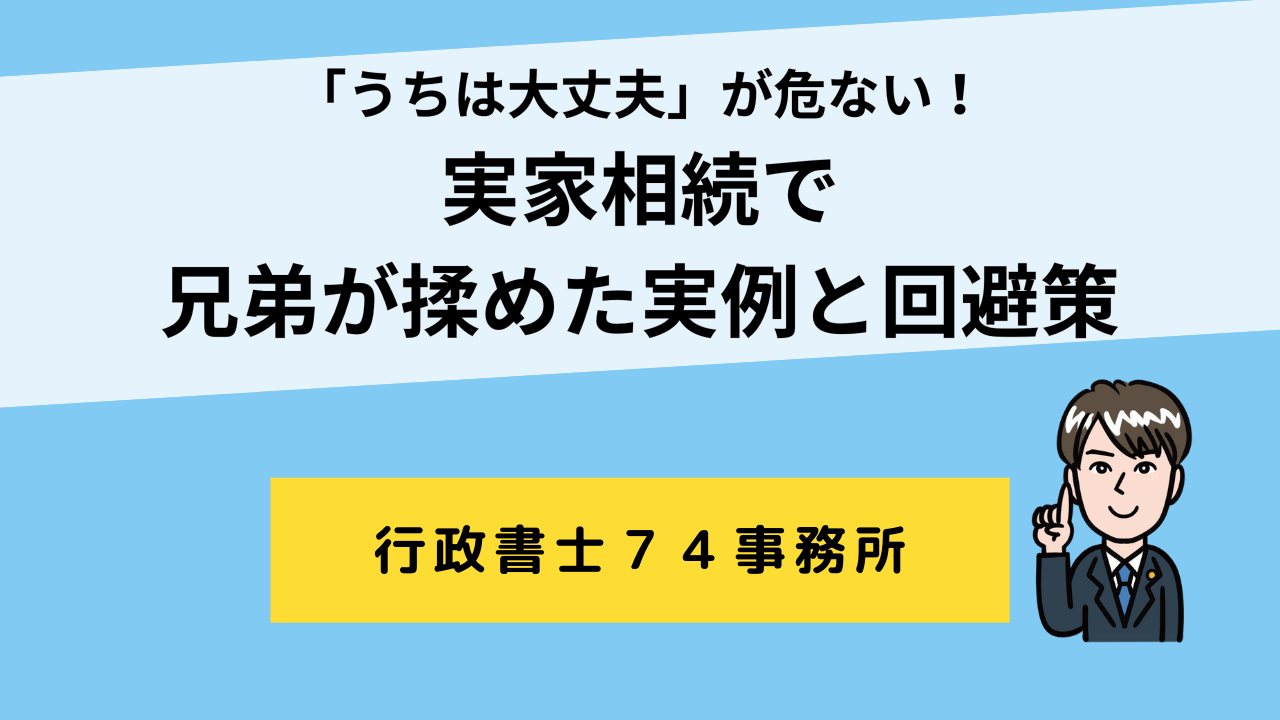はじめに 「実家の相続」がトラブルの火種になる?
相続の場面で最も揉めやすい財産のひとつが「実家」です。
兄弟姉妹で「仲良く分けようね」と言っていたはずが、気がつけば口も聞かない関係に…。
実家には「思い出」や「感情」がつまっている一方で、不動産としての「資産価値」や「維持コスト」も存在します。
そうした事情が複雑に絡み合い、トラブルへと発展してしまうのです。
この記事では、実際にあったトラブルの実例をもとに、実家を相続する際の注意点や回避策をわかりやすく解説します。
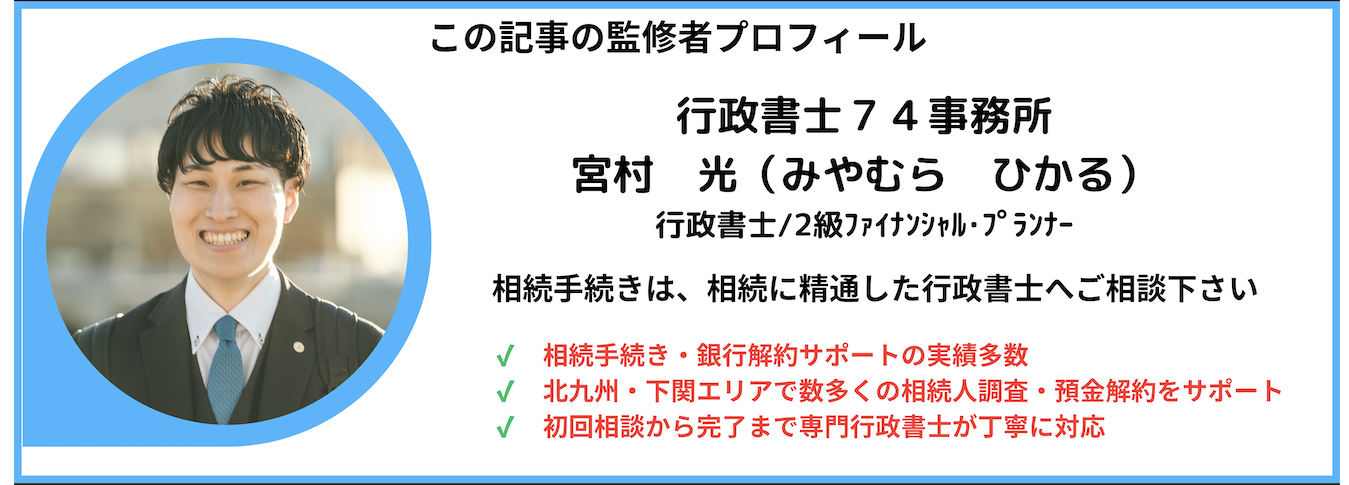
実例① 同居していた兄が実家を独占!妹が納得できず裁判に…
● 事例の概要
兄妹2人。兄は10年以上親と同居し、介護も一手に担っていた。
親の死後、兄は「自分が住み続ける」と主張。
一方、妹は「実家を売却して現金で平等に分けたい」と反発。
話し合いは決裂し、遺産分割調停に発展。
● 何が問題だった?
- 親が遺言書を残していなかった
- 介護の負担を相続に反映させる話し合いができなかった
- 感情論に発展し、「相続の話=兄妹げんか」になった
● 教訓
同居・介護の有無はトラブルの大きな火種になる
事前に親が遺言書で意思を明確にしておくことが重要
実例② 「いずれ自分が住むつもりだった」弟の思いが空回り
● 事例の概要
親の死後、兄弟3人で実家を相続。
弟は「いつか戻って住みたい」と考えていたが、それを兄姉に伝えていなかった。
兄姉は「使わない実家は売却して分けよう」と主張し対立。
結局、売却され弟は涙をのむ結果に。
● 何が問題だった?
- 兄弟間で「事前の意志確認」がされていなかった
- 実家を共有名義で相続し、「誰がどう管理するか」が不明確だった
● 教訓
「想い」は口に出さなければ伝わらない
将来の利用予定があるなら事前に話し合うことが重要
共有名義は、あとあとトラブルを生む可能性大
実家の相続が揉めやすい3つの理由
1. 現金のように「きっちり分ける」ことができない
不動産は「物」なので、単純に分けることができません。
例えば、実家を3人で相続しても、家を3等分するわけにはいかないため、「誰が住む?」「誰が売る?」という話に…。
2. 思い入れや感情が絡む
「生まれ育った家」「介護で頑張った」など、実家には強い感情が結びついています。
そのため、理屈よりも気持ちの衝突が起こりやすくなります。
3. 維持費・固定資産税などコストがかかる
誰も住まない家でも、毎年固定資産税や維持費がかかります。
兄弟で共有したまま放置すると、「誰が負担するか」で揉めるケースが多数。
実家相続で失敗しないための5つの対策
1. 親の生前に「遺言書」を作ってもらう
→ 「誰に何を渡すのか」を明確に書くことで、トラブルの芽を事前に摘めます。
→ 公正証書遺言にしておくと安心。
2. 家族で早めに話し合う
→ 元気なうちに、「実家はどうする?」「誰が住む?」などの意見をすり合わせておきましょう。
→ 親の希望をきちんと聞くことが大切。
3. 共有名義は避ける
→ 共有名義は「売却にもリフォームにも全員の同意が必要」になるため、決め事が進まなくなります。
→ 相続後は単独所有か、現金化して分けるのが無難。
4. 感情ではなく「事実とルール」で話す
→ 「介護してきたから多く欲しい」「同居していたから当然だ」など感情的な主張ではなく、法律や公平性に基づいて協議することが大切。
5. 専門家に相談する
→ 行政書士・司法書士・弁護士などの第三者に入ってもらうことで、冷静かつ中立な話し合いが可能になります。
→ 特に「兄弟の関係が悪化しそうな場合」は早めの相談を。
※遺産分割協議には行政書士、司法書士は参加できません
コラム “実家を残す”ことが必ずしも善ではない?
「先祖代々の土地だから残したい」
「親が苦労して建てた家だから、手放せない」
そうした思いはとても大切ですが、それによって子どもたちが争ってしまうのは本末転倒です。
時代が変わり、空き家のまま放置される実家も全国で増加しています。
「本当に残す価値があるのか?」「子どもにとって負担にならないか?」
そういった視点で考えることも、次世代への優しさかもしれません。
まとめ 実家の相続は「感情」と「現実」のバランスがカギ
実家の相続は、財産というよりも“家族の感情”の問題が大きく関わります。
「うちは仲がいいから大丈夫」と思っていても、いざ相続が始まると関係が崩れるケースは多々あります。
最後にチェック!実家相続で押さえておきたいポイント
- 遺言書を事前に準備してもらう
- 家族で早めに話し合いをしておく
- 共有名義は避ける
- 感情ではなく法律と事実で判断
- 専門家に早めに相談
兄弟の関係を壊さず、実家の相続をスムーズに進めるために。
ぜひ今回の記事を参考に、「いざという時」に備えておきましょう。
そういうときは、相続の専門家に任せることも1つの手段です。
相続のプロと作る!公正証書遺言 作成支援サービス
当事務所は、下関市・北九州市を中心に、相続専門の行政書士事務所として、遺言や相続に関するさまざまなサポートを行っております。
「一人で遺言書を作成するのは不安…」「手続きが複雑でよくわからない…」とお悩みの方もご安心ください。
相続に強い行政書士が、お客様に寄り添いながら丁寧にサポートいたします。
当事務所では、お客様に代わって
- 遺言書の原案作成
- 公証人との打ち合わせ
- 証人の手配
などをすべて一括で対応いたします。
ご相談・お問い合わせは、お電話または下記のお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。
また、公式LINEにて無料のチャット相談も受け付けております。
「ちょっと聞いてみたい」という内容でも構いませんので、お気軽にご利用ください。
ご依頼の流れ
お電話・下記お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
【お電話の場合】
お電話でお客様のご都合を伺わせていただき決定します。
【お問い合わせフォームの場合】
お問い合わせの内容を確認次第、こちらからご連絡させていただきます。
その際ご面談の日時や場所をお客様のご都合を伺いながら決定します。
お客様のお悩みを伺い、最善の方法でお悩みを解決できるようご提案いたします。
ご面談の内容に納得・合意頂けましたらご契約の手続きをします。
原則、着手金として基本料金をお預かりしております。
残額は業務完了後にお支払い頂きます。
(10万円未満の場合は全額を基本料として頂戴しております。)
着手金のお振込みの確認 若しくは委任契約の合意ができ次第、業務を開始します。
定期的に業務の進行状況等のご連絡をいたします。
業務が全て完了しましたらその旨のご連絡をいたします。
手数料の合計と実費等の精算をしまして3日以内に完了金をお支払いして頂きます。
最終的に弊所が行った業務内容についてご説明し書類等の納品をします。
お問い合わせフォーム
お電話もしくは下記お問い合わせフォームよりご連絡をお願いいたします。
LINEではトーク画面のメッセージからでもご相談可能です。
『相談希望』とメッセージください。