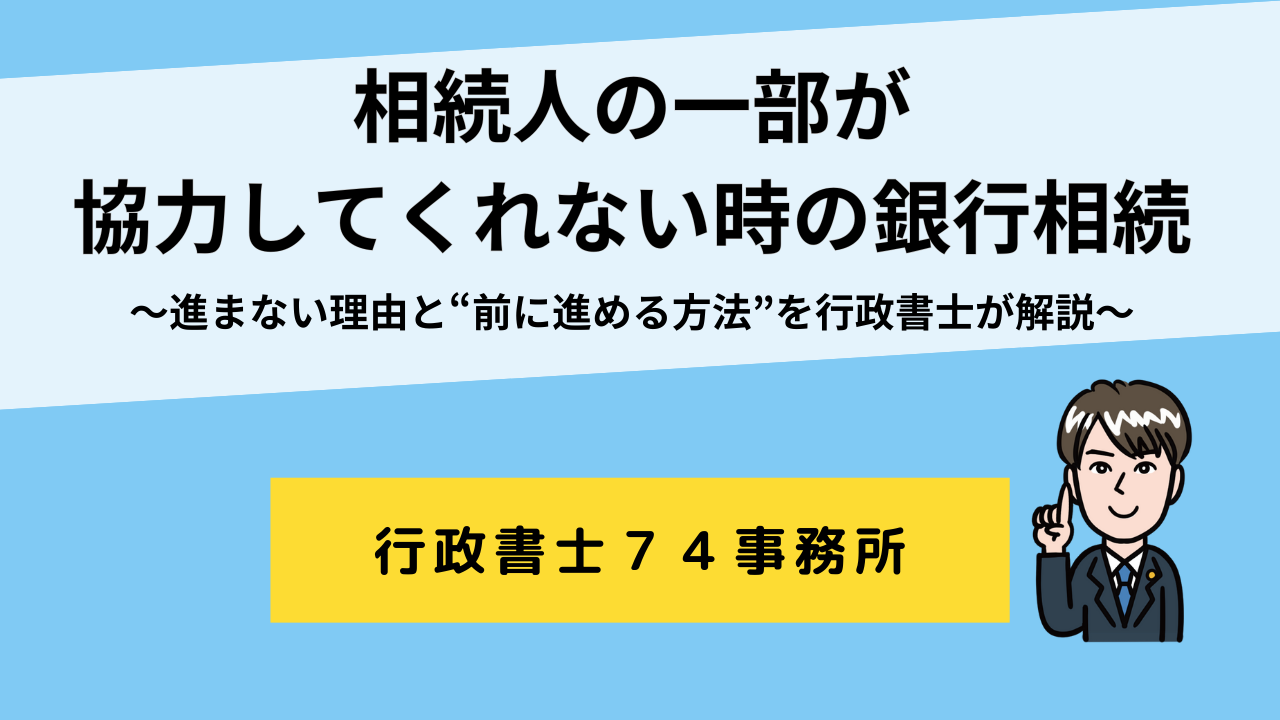銀行の相続手続きでは、相続人全員の署名や印鑑証明書が必要になるため、「相続人の一部が協力してくれない」という状況は非常によく起こります。
- 忙しくて書類に目を通してくれない
- 疎遠で連絡が取れない
- 意見が合わず、書類を書いてくれない
- 相続事情を理解しておらず返事がない
こうした場面は珍しくなく、当事務所でも多いご相談内容の一つです。
この記事では、相続人の協力が得られないケースで、銀行手続きをどのように進めればよいのかを、分かりやすくまとめてお伝えします。
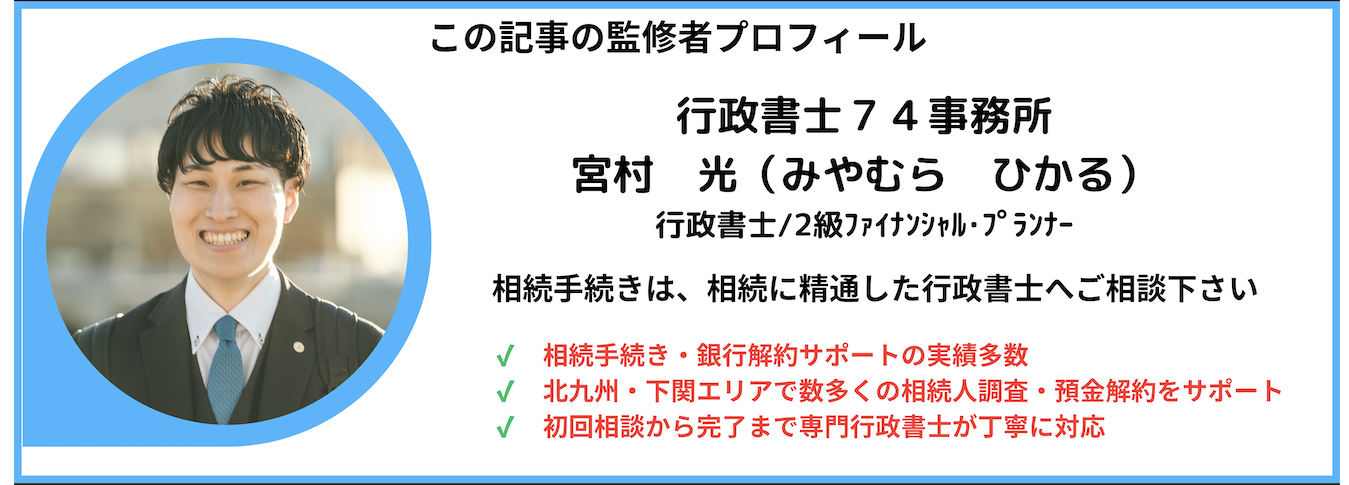
今すぐ銀行の相続手続きを解決したい方は、お電話よりお問い合わせくださいませ。
■ 結論|相続人の一部が協力しないと銀行相続は基本的に進まない
ただし、状況に応じて進める方法はあります。
銀行は、相続財産が「相続人全員の共有」となる性質から、
- 相続人全員の署名捺印
- 相続人全員の印鑑証明書
- 相続人全員の本人確認書類(戸籍謄本など)
をそろえて初めて手続きが進められます。
そのため、誰か1人でも協力しないと、手続きが止まってしまうという仕組みになっています。
しかし、これは「もう何もできない」という意味ではありません。状況に応じた現実的な進め方がありますので、順番に解説します。
■ なぜ相続人全員の協力が必要なのか?
まず、法律上の理由を簡単に整理しておきます。
● 相続財産は“相続人全員の共有”となる
財産を勝手に解約したり払い戻したりすることはできません。
● 銀行には「相続人全員の確認義務」がある
相続人の誰かが抜けている状態で手続きを進めると、後々トラブルにつながるため、銀行も絶対に受け付けません。
つまり、
誰か1人だけ書類を返さない→全員の手続きが止まる
という構図になります。
■ よくある「協力が得られない」パターン
相続人が協力してくれない理由には、いくつか典型的なケースがあります。
① 忙しくて書類に目を通す余裕がない
仕事や子育てで余裕がなく、つい返信が後回しになってしまうパターンです。
② 相続に対する関心が薄い
「自分は関係ない」と思っていたり、
「よく分からないので、放置している」というケースもあります。
③ 疎遠で連絡が取りづらい
兄弟姉妹間での相続では特に多く、
電話やメールをしても返事がこないことがしばしばあります。
④ 取り分に納得しておらず、書類を書かない
財産の分け方について不満があり、書類の返送を拒むケースです。
■ 協力が得られない場合の“現実的な進め方”
ここからは、状況に応じた対応方法をやさしく整理します。
① 書類に負担感を感じている相続人には「分かりやすい説明」を
相続手続きの書類は専門用語も多く、理解しないまま放置している相続人も少なくありません。
● 有効なアプローチ
- 書類の目的を丁寧に説明する
- どの項目に記入すべきかを明確に伝える
- 不安があれば専門家に相談できることを案内する
「何のための書類か分からない」という理由だけで止まっているケースも多いため、丁寧な説明だけで前に進むことがあります。
実際に相続人代表者が他の相続人に説明しても署名捺印をしてもらえなかったという事例で、行政書士が他の相続人の方に丁寧に説明をして不安を解消することで、合意を得たという経験があります。
② 連絡がつかない場合は“文書”での案内が効果的
電話やメールでは反応がなくても、きちんとした文書を送ると返事が来ることがあります。
● 文書に入れるべき内容
- 手続きの必要性
- 法律に基づく相続人の立場
- 全員の手続きが止まっていること
- 期限や目安の案内
相手は「急かされている」と感じると関係が悪化するため、落ち着いた文面で丁寧に伝えることが大切です。
③ 行政書士など“第三者”がサポートに入る
書類の送付や案内を、第三者である専門家がサポートすると、相続人の心理的な負担が軽くなることがあります。
● 行政書士ができること
- 相続人への文書案内
- 必要書類の説明・収集
- 書類作成の代行
- 相続関係の整理(相続関係図の作成 等)
※ただし重要
相続人同士の意見対立が強い“紛争性のあるケース”では、代理交渉は弁護士にしか認められていません。
行政書士が行えるのは、あくまで「事務的な手続きのサポート」に限られます。
この点は誤解されやすいため、きちんと認識しておくことが大切です。
④ 預貯金の払い戻し制度の利用を検討する
相続財産の中に預貯金がある場合、条件を満たせば【預貯金の払い戻し制度】を利用できます。
● 預貯金の払い戻し制度とは?
相続人全員の同意がなくても、一定額(法定相続分 × 1/3、かつ上限150万円)の範囲で、1つの金融機関につき相続人1名が払い戻しできる制度です。
● ただし注意
・あくまで「生活費や葬儀費用を確保するための制度」
・すべての財産を処理できるわけではない
・銀行により書類・審査に差がある
相続全体を進めることはできませんが、とりあえず必要な費用を確保したい場合には有効です。
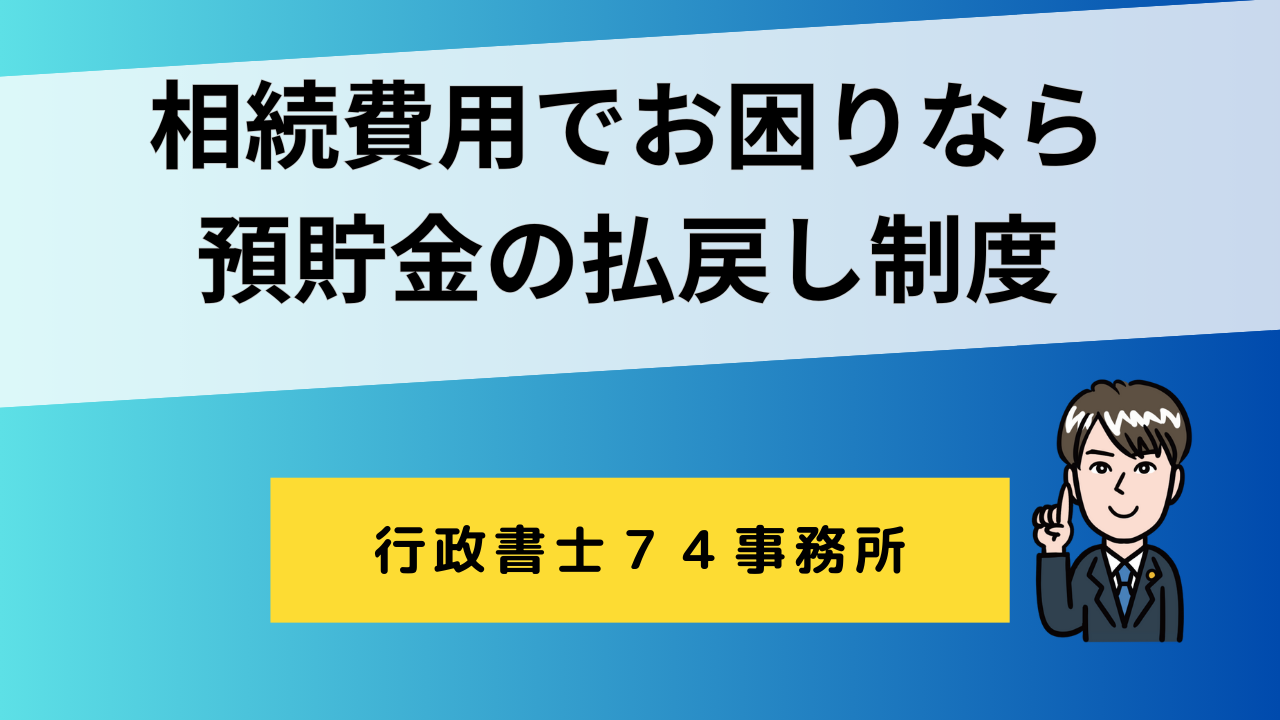
⑤ どうしても協力が得られない場合は家庭裁判所の調停へ
相続人の1人が完全に非協力的で、書類が一切返ってこない場合は、
✔ 家庭裁判所の「遺産分割調停」
を申し立てることで前に進められる可能性があります。
調停委員が間に入ることで、相続人同士の話し合いが整理され、解決に向かうケースも多いです。
■ ここで気をつけたい“やってはいけないこと”
協力しない相続人がいるとつい焦ってしまいますが、次のような行動は避けた方が良いです。
× 期限を強く迫る
→ 関係が悪化してさらに返事が遅くなることも。
× 一方的に書類を送り続ける
→ 相手が“拒否反応”を起こしてしまいます。
× 無理に話し合おうとする
→ 家族間の関係が壊れ、裁判に発展することも。
相続は“人と人との調整”が必要な場面が多いため、慎重に、落ち着いて進めることがスムーズな解決につながります。
■ まとめ
相続人の一部が協力してくれない場合、銀行相続の手続きは基本的に進みません。
しかし、段階的にアプローチすることで状況が動き出すことは十分あります。
- 分かりやすい説明
- 文書によるご案内
- 行政書士による事務サポート
- 預貯金の払い戻し制度の活用
- 家庭裁判所の調停
これらを組み合わせることで、最適な方法で前に進めることができます。
■ 忙しい方・相続人とのやり取りが難しい方へ
行政書士74事務所が銀行相続の手続きをサポートします
当事務所では、門司区・下関市を中心に、相続手続きを専門的にサポートしています。
- 相続人への書類案内のサポート
- 必要書類の作成代行
- 戸籍の収集
- 銀行の相続届出
- 複数の銀行口座の一括手続き
- 平日夜間・土日祝もご相談可能
- 門司・下関エリアは出張無料
- 24時間お問い合わせ可能
「相続人が協力してくれず困っている」
「どう進めたらいいかわからない」
そのような場合でも、状況に合わせた最適な方法をご提案しますので、お気軽にご相談ください。
無料相談申込とご依頼の流れは以下より
ご依頼の流れ

お電話・下記のお問い合わせフォームより
お問い合わせください。

【お電話の場合】
お客様のご都合を伺わせていただき決定します。
【お問い合わせフォームの場合】
お問い合わせの内容を確認次第、
こちらからご連絡させていただきます。
その際ご面談の日時や場所を
お客様のご都合を伺いながら決定します。

お客様のお悩みを伺い、最善の方法で
お悩みを解決できるようご提案いたします。

ご面談の内容に納得・合意頂けましたら
ご契約の手続きをします。

原則、着手金として基本料金をお預かりしております。
(業務に迅速に取り掛かるため3日以内に銀行口座へのお振り込みをお願いしています。)
※契約書に署名捺印していただいた方は後払い可

着手金のお振込みの確認若しくは委任契約の合意ができ次第、業務を開始します。

定期的(2週間に1回程度)に業務の進行状況等のご連絡をいたします。

業務が全て完了しましたら
その旨のご連絡をいたします。

手数料の合計と実費等の精算をしまして
5日以内に完了金をお支払いして頂きます。
5日以内にお支払いが難しい場合は、
臨機応変にご対応しますのでご相談ください。
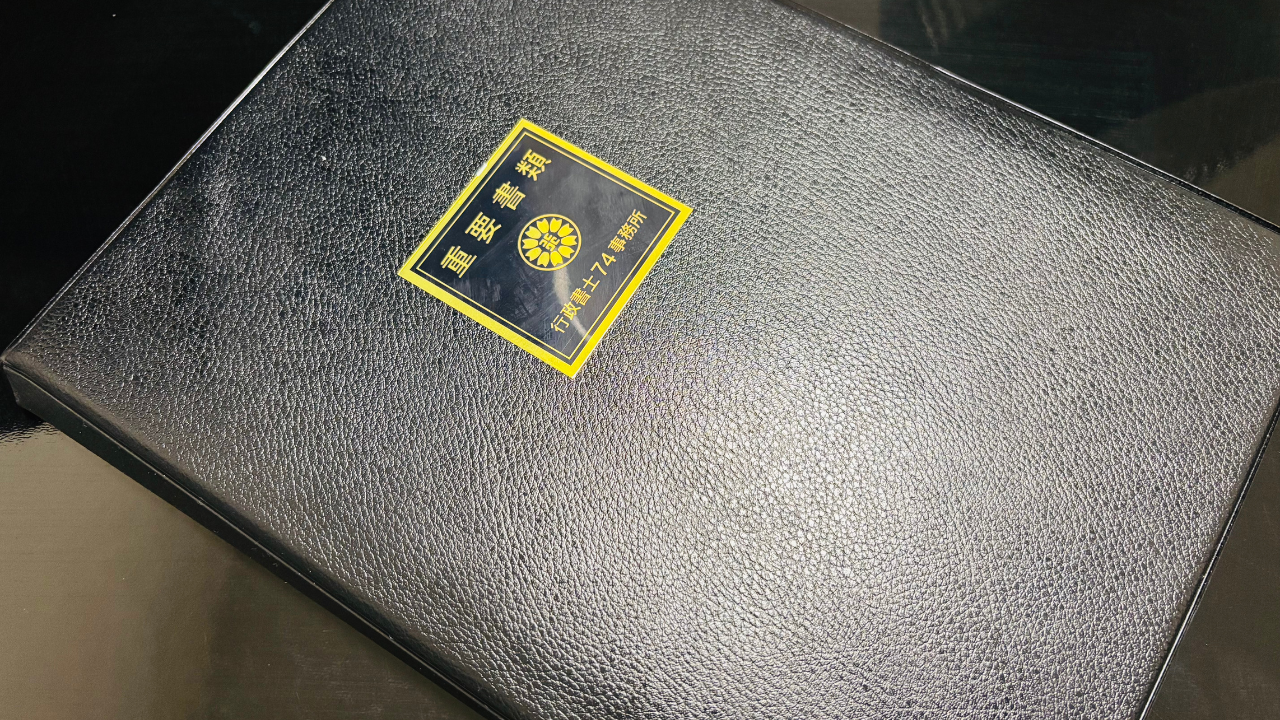
最終的に弊所が行った業務内容について
ご説明し書類等の納品をします。
お問い合わせフォーム
お電話もしくは下記お問い合わせフォームよりご連絡をお願いいたします。
LINEではトーク画面のメッセージからでもご相談可能です。
『相談希望』とメッセージください。