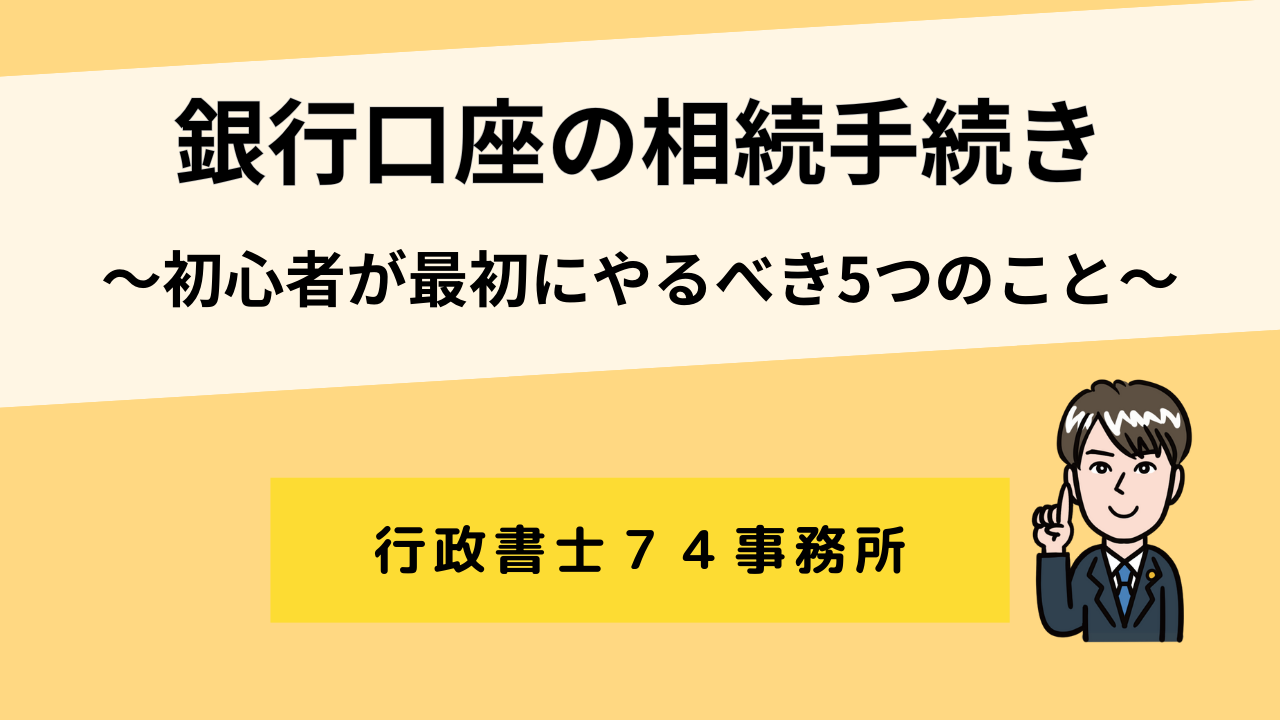はじめに 預金口座はどうなるの?
大切なご家族が亡くなった後、避けて通れないのが「相続の手続き」です。
中でも「銀行口座の相続手続き」は、ほぼすべての相続で発生する重要な手続きのひとつです。
しかし、いざ自分が手続きをする立場になると、
- 「何を準備すればいいの?」
- 「どのタイミングで銀行に連絡するの?」
- 「他の相続人とも話をまとめないといけないの?」
といった疑問や不安がたくさん出てきます。
この記事では、相続の初心者でも迷わず進められるように、「銀行の相続手続きで最初にやるべき5つのこと」をステップごとに分かりやすく解説していきます。
ステップ① 死亡届の提出と預金口座の凍結
まず、家族が亡くなったら市区町村役場に死亡届を提出します。
これは葬儀社が代行してくれることが多いです。
よくある誤解
死亡届を提出すると、金融機関にも「亡くなった」という情報が共有されるということを耳にしたことがあるかと思いますが、そのようなことはありません。
金融機関は、親族からの申し出がない限りは基本的に死亡の事実を知ることがないので、凍結されることもありません。
また親族からの申し出により、銀行が故人の死亡を確認すると、その口座は自動的に凍結され、預金の出し入れができなくなります。
「残ったお金を引き出して葬儀費用にあてよう」と思ってATMで引き出す方もいますが、死亡後に勝手に引き出すと「使い込み」とみなされる可能性があるので注意が必要です。
ステップ② まずは何がどこにあるかを調べる「財産調査」
銀行の相続手続きを始めるには、まずどこの銀行にどんな口座があるのかを把握しなければなりません。
調べ方の例
- 自宅にある通帳・キャッシュカード・郵便物を確認
- クレジットカードの引き落とし先の銀行を確認
- ご本人が使っていたスマホやPCのメモやアプリをチェック
- 年金や保険の入金先口座を見つける
場合によっては、複数の金融機関に口座が分散していることもあります。
全体を把握することで、今後の手続きがスムーズになります。
ステップ③ 戸籍を取り寄せて「相続人を確定」する
次に行うのが、「誰が相続人になるのか」を調べる作業です。
銀行は、相続人全員が関わる書類を必要とするため、まずは戸籍を集めて法定相続人を確定させる必要があります。
必要な戸籍の例
- 亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍
- 配偶者や子どもなどの戸籍(現在の戸籍)
市区町村の役所で申請すれば取得できますが、複数の自治体にまたがることも多く、1〜2週間以上かかることもあります。
ここでのポイント
相続人に「疎遠になっていた子ども」や「前の配偶者との子」がいるケースでは、手続きが複雑になる前に専門家に相談するのがおすすめです。
ステップ④ 各銀行に「相続手続きの申し出」をする
相続人が確定したら、該当の銀行に対して「相続手続きの申し出」を行います。
これによって、銀行から「必要書類一覧」や「相続手続きの流れ」などが案内されます。
銀行に提出する主な書類(一般的なもの)
- 相続手続き依頼書
- 相続人全員の戸籍・住民票
- 印鑑登録証明書
- 遺言書(ある場合)または遺産分割協議書
- 被相続人の通帳・キャッシュカード・本人確認書類の写し
銀行によって必要書類や手続きの様式が少しずつ異なるため、必ず個別に確認しましょう。
ステップ⑤ 遺産分割協議書を作成して、相続人全員の同意を得る
銀行口座の名義変更や解約には、相続人全員の同意が必要です。
もし遺言書がない場合は、相続人全員で話し合い、「誰が、どの口座の、いくらを相続するか」を取り決めて、遺産分割協議書を作成します。
協議書の内容の例
- どの銀行口座を誰が取得するか
- 代表相続人を誰にするか(手続きを進める人)
- 相続人全員の署名・実印押印
作成後は、相続人全員の印鑑証明書とともに銀行に提出します。
1人でも押印しない相続人がいると、手続きが進みません。
よくある質問(Q&A)
Q:相続人の中に連絡が取れない人がいる場合はどうする?
→ 家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てることで手続きを進められる場合があります。時間がかかるので、早めに対応をしましょう。
Q:遺言書がある場合でも、遺産分割協議は必要?
→ 原則として、公正証書遺言があればその内容通りに手続き可能。
自筆証書遺言がある場合は、家庭裁判所での検認が必要です。
Q:銀行によって提出書類は違うの?
→ はい、銀行ごとに必要書類や手続き方法が異なります。同じ三井住友銀行でも支店によって微妙に対応が違うケースも。
まとめ 迷ったら、早めに「専門家に相談」も選択肢に
銀行の相続手続きは、「書類が多い」「やることが多い」「人との連携が必要」なため、初めての方にとっては負担に感じやすい作業です。
しかし、今回ご紹介した5つのステップを押さえておけば、迷わず一歩ずつ進めることが可能です。
最初にやるべき5つのこと(まとめ)
- 死亡届を提出し、口座凍結に備える
- 財産調査で口座の所在を確認
- 戸籍を集めて相続人を確定
- 銀行に相続手続きを申し出る
- 相続人全員の同意を得て分割協議書を提出
もし「時間がない」「自分では難しい」と感じたら、行政書士などの専門家に相談するのも安心への近道です。
大切な人の遺産を正しく、そして円満に引き継ぐために。焦らず、丁寧に手続きを進めていきましょう。
必要書類も丸ごとサポート!銀行の相続手続き代行サービス
当事務所は、北九州市門司区を中心に、銀行の相続手続きに特化したサポートを行っております。
「相続手続きが難しくて進められない」「相続手続きをできるだけ早く完了させたい」とお考えの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。
当事務所では、銀行の相続手続きに特化した専門的な支援を行っており、北九州市内で唯一、銀行相続手続きに専門特化した行政書士事務所として実績を積んでおります。
これまで約5年間、北九州市および下関市内のほとんどの銀行で手続きをサポートして参りました。
必要書類の準備から窓口での手続きまで、迅速かつ確実に対応し、お客様のご不安を解消いたします。
お問い合わせは、お電話または下記のお問い合わせフォームからお受けしております。
また、公式LINEにてチャットでのご相談も無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
ご依頼の流れ
お電話・下記お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
【お電話の場合】
お電話でお客様のご都合を伺わせていただき決定します。
【お問い合わせフォームの場合】
お問い合わせの内容を確認次第、こちらからご連絡させていただきます。
その際ご面談の日時や場所をお客様のご都合を伺いながら決定します。
お客様のお悩みを伺い、最善の方法でお悩みを解決できるようご提案いたします。
ご面談の内容に納得・合意頂けましたらご契約の手続きをします。
原則、着手金として基本料金をお預かりしております。
(指定銀行口座へお振込み)
残額は業務完了後にお支払い頂きます。
(10万円未満の場合は全額を基本料として頂戴しております。)
着手金のお振込みの確認 若しくは委任契約の合意ができ次第、業務を開始します。
定期的に業務の進行状況等のご連絡をいたします。
業務が全て完了しましたらその旨のご連絡をいたします。
最終的に弊所が行った業務内容についてご説明し書類等の納品をします。
手数料の合計と実費等の精算をしまして3日以内に完了金をお支払いして頂きます。
お問い合わせフォーム
お電話もしくは下記お問い合わせフォームよりご連絡をお願いいたします。
LINEではトーク画面のメッセージからでもご相談可能です。
『相談希望』とメッセージください。