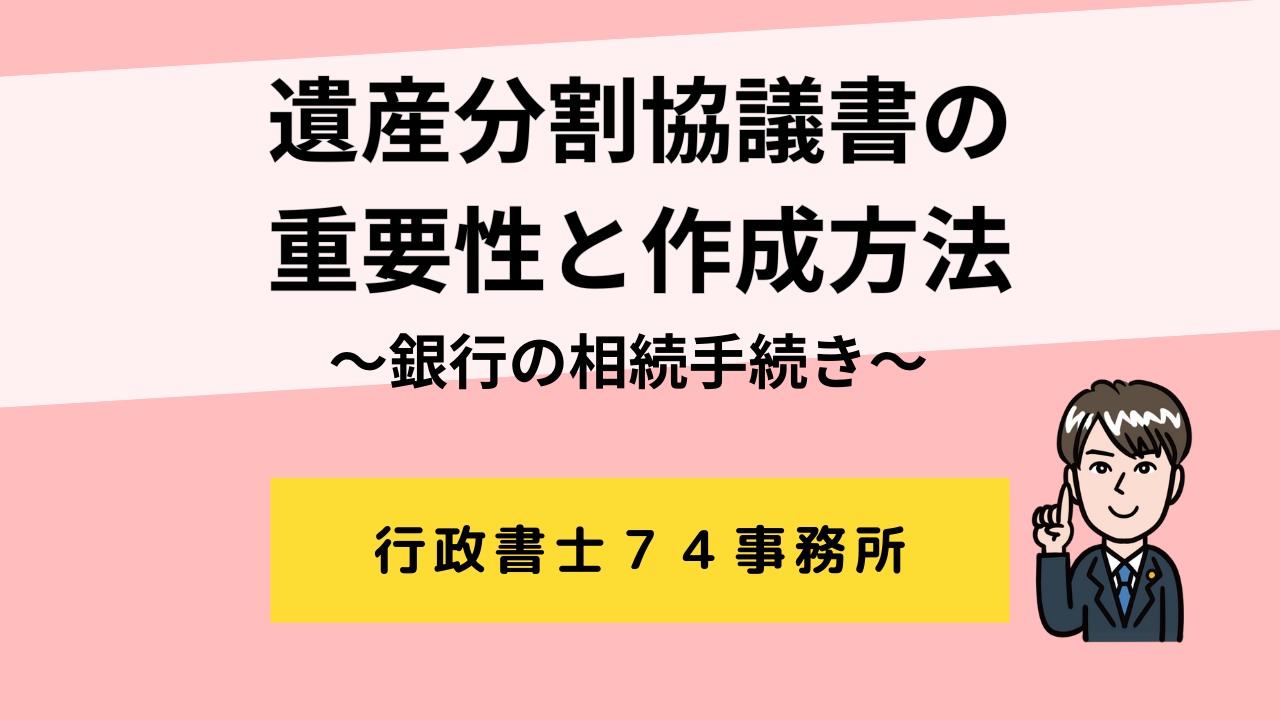遺産分割協議書は、亡くなった方(被相続人)の相続財産を、相続人がどのように分けるかを決めるために作成する重要な書類です。
遺産分割協議書を作成することにより、相続人間でのトラブルを防ぎ、法的にも問題なく遺産を分けることができます。
本記事では、銀行の相続手続きをする際の遺産分割協議書の必要性、作成の流れ、注意点について、分かりやすく解説していきます。
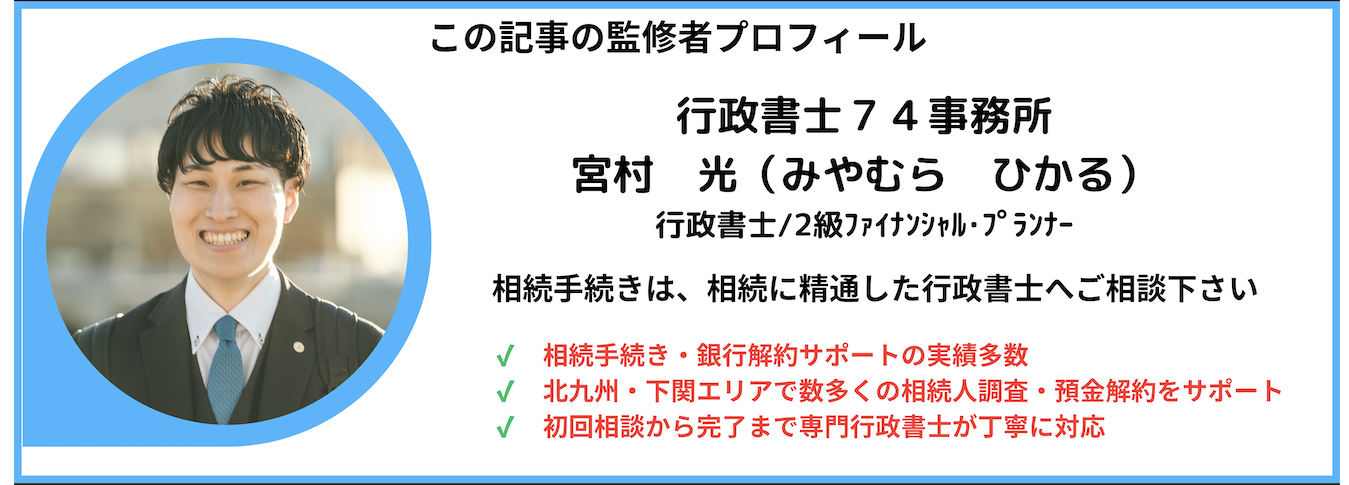
北九州市で銀行相続の手続きが必要な方へ
✔ 忙しくて役所・銀行に行く時間がない
✔ 必要書類が多くて準備できない
✔ 相続人が遠方で手続きが進まない
✔ 専門家に全て任せたい
このようなお悩みは、当事務所がワンストップで解決します。出張費無料で北九州全域に対応しています。
※今すぐ銀行の相続手続きを解決したい方は、お電話にてお問い合わせくださいませ。
1. 遺産分割協議書とは?
遺産分割協議書とは、亡くなった人の相続財産を相続人がどのように分けるかについて、全員の合意を記した書類です。
相続財産には不動産、現金、預貯金、株式など、さまざまな種類の財産が含まれます。
これらを相続人間で分けるためには、遺産分割協議(相続人間での話し合い)が必要です。
遺産分割協議をして相続人全員が合意した内容を遺産分割協議書にまとめて署名・捺印を行います。
2. 遺産分割協議書が必要な理由
遺産分割協議書がなぜ必要なのか、その理由は以下の3つに集約されます。
(1) 相続の意思を明確にするため
遺産分割協議書を作成することで、相続人間で相続財産をどのように分けるかについて、事前に合意を形成することができます。
この書類は、相続人全員の意思を反映したものとなり、後々の争いを防ぐために非常に重要です。
特に、遺産分割に関する合意がないまま相続を進めると、相続後に相続人間で揉める原因となります。
(2) 銀行口座の解約手続きをスムーズに進めるため
銀行の相続手続きを行うためには、基本的には遺産分割協議書が必要です。
しかし例外的に、遺産分割協議書がなくてもできる場合もあります。
それは、民法で規定されている法定相続分で相続する場合です。(※銀行によって取り扱いが違う)
逆を言うと、1人の相続人が全てを取得する場合や、特定の相続人に多く取得する場合などは遺産分割協議書を作成する必要があります。
遺産分割協議書を作成することにより、しっかり遺産分割の内容を銀行に示すことができるため、銀行口座の解約手続きがスムーズに進みます。
このように、遺産分割協議書は銀行口座の解約手続きを法的に進める上で不可欠な書類となります。
(3) 相続税の申告を正確に行うため
相続税を申告する際には、遺産分割協議書が必要となる場合があります。
遺産分割協議書は、相続税の計算に必要な遺産の評価額を確定させるための基礎となり、税務署に提出するための重要な資料となります。
特に、相続税の申告期限(通常は相続開始から10ヶ月以内)を守るためにも、遺産分割協議書の作成は必要不可欠です。
3. 遺産分割協議書の作成方法
遺産分割協議書の作成には一定の手順と注意点があります。ここでは、その流れを順を追って解説します。
(1) 相続人の確認
まずは、相続人が誰であるかを確認する必要があります。
相続人とは、亡くなった方の配偶者、子ども、父母、兄弟姉妹などが該当します。
相続人には、相続権の順位があるので、最初に必ず確認しましょう。
相続人の確認は、戸籍謄本や住民票などの公的書類をもとに行います。
もし相続人に養子がいる場合や、相続権を有するかどうか不明な場合は、専門家に相談することをお勧めします。
(2) 相続財産の内容を確認
次に、相続財産が何であるかを把握します。
不動産、預金、株式、保険金など、すべての遺産をリストアップし、その評価額を算出します。
評価額の算定方法は財産の種類によって異なります。
金融資産については、基本的には、被相続人が亡くなった日の残高になります。
不動産の評価額については、固定資産税評価証明書を確認したり、不動産鑑定士に依頼することが有効です。
(3) 分割方法の決定
遺産分割方法は、相続人間で話し合って決めます。
例えば、財産の全てを特定の相続人が相続する、もしくは各相続人が等分に分ける方法などがあります。
遺言がない場合、相続人全員が同意する必要があります。
合意が難しい場合は、弁護士に仲介を依頼することもできます。
(4) 遺産分割協議書の作成
遺産分割方法が決まったら、それを基に遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には、以下の内容を含めることが一般的です。
- 相続人の名前(全員分)
- 遺産の詳細(財産の種類、評価額)
- 各相続人が受取る遺産の内容
- 相続人全員の署名と捺印
特に重要なのは、相続人全員の署名と捺印をもらうことです。署名や捺印がないと、遺産分割協議書が無効になり、法的効力を持たなくなってしまいます。
(5) 公証役場での認証(任意)
遺産分割協議書を公証人に認証してもらうことも可能です。
公証人に認証してもらうことで、協議書が公的に証明されたことになります。
認証を受けることは必須ではありませんが、後々のトラブルを防ぐためには有効です。
4. 遺産分割協議書作成時の注意点
遺産分割協議書を作成する際には、いくつかの注意点があります。これを守らないと、後々法的な問題が発生する可能性があります。
(1) 遺産分割協議書は必ず全員の合意で作成すること
遺産分割協議書は、相続人全員の合意によって作成するものです。
もし1人でも協議に参加しなかったり、反対する相続人がいれば、その協議書は無効となります。
そのため、全員が納得できる内容にすることが非常に重要です。
(2) 正確に財産内容を記載すること
遺産分割協議書に記載する内容は、すべて正確に記載することが求められます。
特に不動産の情報や金融機関名、口座番号などは間違いがないように記入しましょう。
誤った情報を記載すると、後で訂正が必要になることがあり、手続きが煩雑になる場合があります。
(3) 期限を守ること
遺産分割協議書の作成は、相続税の申告期限や登記の手続きに影響を与えるため、できるだけ早めに作成することが重要です。
また、遺産分割協議書作成後は、必要に応じて税務署や登記所に提出することを忘れないようにしましょう。
5. まとめ
銀行の相続手続きで必要な遺産分割協議書は、相続人間で相続財産をどのように分けるかを決め、法的な手続きを進めるために必要不可欠な書類です。
これを作成することで、相続人間のトラブルを防ぎ、円滑に相続手続きを進めることができます。
第三者からの請求があった場合に証明する書類になりますので、自分の身を守る為にも作成しましょう。
遺産分割協議書を作成する際は、相続人全員の合意を得て、正確に内容を記載することが大切です。必要に応じて専門家の助けを借りながら、慎重に進めましょう。
銀行の相続手続きでお困りなら
行政書士74事務所では、北九州市門司区を中心に、銀行の相続手続きに特化したサポートを行っております。
「相続手続きが難しくて進められない」「相続手続きをできるだけ早く完了させたい」とお考えの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。
当事務所では、銀行の相続手続きに特化した専門的な支援を行っており、北九州市内で唯一、銀行相続手続きに専門特化した行政書士事務所として実績を積んでおります。
これまで約5年間、北九州市および下関市内のほとんどの銀行で手続きをサポートして参りました。
今回のような遺産分割協議書をはじめ、必要書類の準備から窓口での手続きまで、迅速かつ確実に対応し、お客様のご不安を解消いたします。
お問い合わせは、お電話または下記のお問い合わせフォームからお受けしております。
また、公式LINEにてチャットでのご相談も無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
ご依頼の流れ
お電話・下記お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
【お電話の場合】
お電話でお客様のご都合を伺わせていただき決定します。
【お問い合わせフォームの場合】
お問い合わせの内容を確認次第、こちらからご連絡させていただきます。
その際ご面談の日時や場所をお客様のご都合を伺いながら決定します。
お客様のお悩みを伺い、最善の方法でお悩みを解決できるようご提案いたします。
ご面談の内容に納得・合意頂けましたらご契約の手続きをします。
原則、着手金として基本料金をお預かりしております。
(指定銀行口座へお振込み)
残額は業務完了後にお支払い頂きます。
(10万円未満の場合は全額を基本料として頂戴しております。)
着手金のお振込みの確認 若しくは委任契約の合意ができ次第、業務を開始します。
定期的に業務の進行状況等のご連絡をいたします。
業務が全て完了しましたらその旨のご連絡をいたします。
最終的に弊所が行った業務内容についてご説明し書類等の納品をします。
手数料の合計と実費等の精算をしまして3日以内に完了金をお支払いして頂きます。
お問い合わせフォーム
お電話もしくは下記お問い合わせフォームよりご連絡をお願いいたします。
LINEではトーク画面のメッセージからでもご相談可能です。
『相談希望』とメッセージください。