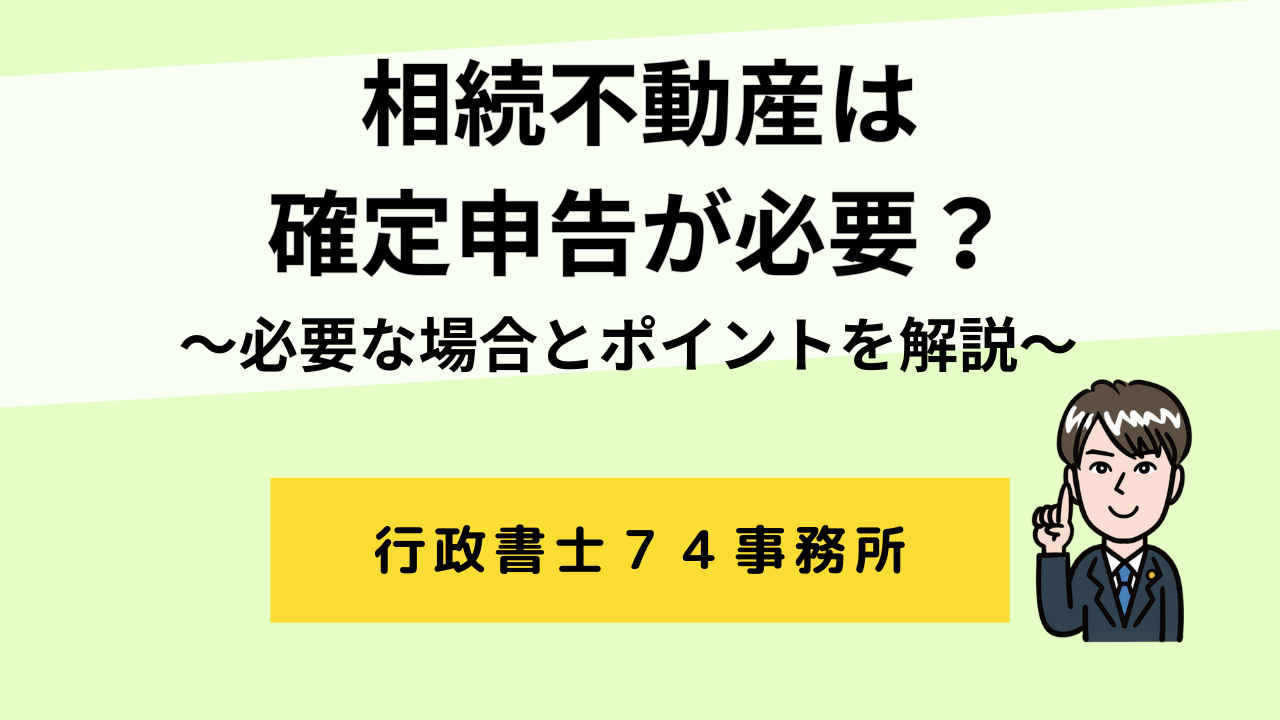はじめに
相続手続きをご依頼いただいたお客様から、よくご相談いただくのが、相続財産の確定申告の有無です。
特に相続した不動産についてのご相談が多いです。
今回は、相続した不動産の確定申告について、わかりやすく解説するために、まずは相続と不動産に関する基本的な知識をおさらいし、その後に確定申告の必要性や方法を詳しく説明します。
相続税や所得税の取り扱いに関連した内容を盛り込みながら、段階を追って解説します。
相続に関連する税務は、少し難しいと感じることが多い分野です。特に、相続した不動産についてはその後の処理が重要です。相続した不動産をどのように扱うかによって、税金の負担が変わることもあります。
中でも、相続した不動産に関しては、確定申告をする必要がある場合とない場合があるため、そのポイントを理解しておくことが大切です。
この記事では、相続した不動産の確定申告が必要なケースとその理由、また実際にどのような手続きを行うべきかについて解説します。
1. 相続と不動産の基本
相続とは、被相続人が亡くなった後に、その財産(遺産)を相続人が引き継ぐことです。
この財産には、現金や預金だけでなく、不動産(家屋や土地)も含まれます。
不動産を相続する場合、その不動産がどのような状態にあるか、またどのように利用されるかによって税務処理が異なります。
例えば、不動産を売却した場合、売却益に対して税金がかかることになります。逆に、不動産をそのまま所有し続ける場合には、固定資産税が毎年課せられます。
相続した不動産の確定申告が必要かどうかを理解するためには、まず「確定申告」とは何かを確認する必要があります。
確定申告とは、その年の収入や経費を申告し、税額を確定する手続きです。基本的に、個人は一定の条件下で確定申告を行う必要がありますが、その必要性が発生するのは、収入や所得に関連する場合です。
2. 相続した不動産に対する確定申告の必要性
2.1 不動産を売却した場合
相続した不動産を売却する場合、その売却益に対して「譲渡所得税」がかかります。
譲渡所得税とは、土地や建物を売却した際に得た利益に対して課せられる税金です。売却益の計算には、購入時の価格や売却時の価格に加え、経費(例えば仲介手数料や修繕費用など)も含まれます。
譲渡所得税は、確定申告を通じて支払う必要があります。税率は、売却からの期間(所有期間)や譲渡額に応じて変動します。
一般的に、所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得となり、税率が軽減されますが、所有期間が5年未満であれば短期譲渡所得となり、高い税率が適用されます。
確定申告が必要な場合
- 相続した不動産を売却して利益が出た場合(譲渡所得が発生した場合)
- 譲渡所得の申告を行わなかった場合、税務署から後日指摘される可能性があります
従って、不動産を相続した後にその不動産を売却する場合は、必ず確定申告を行う必要があります。
2.2 不動産を賃貸して収入を得ている場合
相続した不動産をそのまま賃貸し、家賃収入を得ている場合、その家賃収入は「不動産所得」として申告する必要があります。不動産所得は、収入から必要経費(管理費や修繕費、税金など)を差し引いた額が課税対象となります。
確定申告が必要な場合
- 賃貸収入を得ている場合
- その年に一定額以上の収入がある場合(基本的に20万円以上の不動産所得がある場合は申告が必要です)
賃貸物件の収入が少額であっても、一定の金額を超える場合には、確定申告を行わなければなりません。例えば、家賃収入が年間20万円以上であれば、確定申告を行う必要があります。
2.3 相続税申告の必要性
相続した不動産に対して相続税がかかる場合、その税額を計算するために相続税の申告が必要になります。相続税の申告は、相続開始から10ヶ月以内に行う必要があり、相続人がその不動産を取得した場合、相続税を支払う義務があります。
ただし、相続税の申告を行ったからといって、必ずしも確定申告が必要なわけではありません。相続税申告と確定申告は異なる手続きですが、相続税申告の際に不動産を評価して申告した場合、その後の税務手続きにおいて不動産に関連する部分で確定申告が発生する場合もあります。
3. 相続した不動産の確定申告を行う際のポイント
3.1 必要な書類
相続した不動産の確定申告を行う際には、以下の書類が必要となります。
- 譲渡契約書(売却した場合)
- 不動産の評価証明書(相続税申告時に評価した場合)
- 収入金額の証明書(賃貸収入がある場合)
- 経費の領収書(修繕費や管理費用など)
- その他、必要な税務関連書類
3.2 所得の計算
不動産所得や譲渡所得の計算方法を理解することが重要です。譲渡所得の計算式は次のようになります。
[ 譲渡所得 = 売却価格 – 取得費 – 譲渡費用 ]
取得費は、購入時にかかった費用を指します。譲渡費用には、売却時にかかった仲介手数料や登記費用などが含まれます。
賃貸収入については、収入から必要経費を差し引いて、課税対象となる所得を算出します。
4. 確定申告をしないとどうなるか?
もし相続した不動産に関連する確定申告を怠った場合、税務署から追加で税金を請求される可能性があります。
特に、譲渡所得の申告をしないと、後に税務署から指摘を受け、追加で税金を支払わなければならないことがあります。さらに、遅延税や加算税が課せられることもあるため、正確に申告を行うことが大切です。
5. まとめ
相続した不動産に関連する確定申告は、売却した場合や賃貸して収入を得た場合など、いくつかのケースに分かれます。
売却した場合には譲渡所得税、賃貸の場合は不動産所得に関して申告が必要です。相続税申告を行った場合でも、確定申告が別途必要になることがあります。
確定申告をしないことで不利益を被らないためにも、相続後の不動産処理において必要な税務手続きを理解し、適切に対応することが重要です。
銀行の相続手続き代行サービス
当事務所は、北九州市門司区を中心に、銀行の相続手続きに特化したサポートを行っております。
「相続手続きが難しくて進められない」「相続手続きをできるだけ早く完了させたい」とお考えの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。
当事務所では、銀行の相続手続きに特化した専門的な支援を行っており、北九州市内で唯一、銀行相続手続きに専門特化した行政書士事務所として実績を積んでおります。
これまで約5年間、北九州市および下関市内のほとんどの銀行で手続きをサポートして参りました。
必要書類の準備から窓口での手続きまで、迅速かつ確実に対応し、お客様のご不安を解消いたします。
また、今回のような税務相談についても、相続・確定申告のどちらにも強い税理士を無料でご紹介することが可能です。(相続手続きのご依頼がない場合でもご紹介いたします。)
これによりお客様は相続手続きから税務申告までワンストップで手続きを完了することができます。
お問い合わせは、お電話または下記のお問い合わせフォームからお受けしております。
また、公式LINEにてチャットでのご相談も無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
ご依頼の流れ
お電話・下記お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
【お電話の場合】
お電話でお客様のご都合を伺わせていただき決定します。
【お問い合わせフォームの場合】
お問い合わせの内容を確認次第、こちらからご連絡させていただきます。
その際ご面談の日時や場所をお客様のご都合を伺いながら決定します。
お客様のお悩みを伺い、最善の方法でお悩みを解決できるようご提案いたします。
ご面談の内容に納得・合意頂けましたらご契約の手続きをします。
原則、着手金として基本料金をお預かりしております。
(指定銀行口座へお振込み)
残額は業務完了後にお支払い頂きます。
(10万円未満の場合は全額を基本料として頂戴しております。)
着手金のお振込みの確認 若しくは委任契約の合意ができ次第、業務を開始します。
定期的に業務の進行状況等のご連絡をいたします。
業務が全て完了しましたらその旨のご連絡をいたします。
最終的に弊所が行った業務内容についてご説明し書類等の納品をします。
手数料の合計と実費等の精算をしまして3日以内に完了金をお支払いして頂きます。
お問い合わせフォーム
お電話もしくは下記お問い合わせフォームよりご連絡をお願いいたします。
LINEではトーク画面のメッセージからでもご相談可能です。
『相談希望』とメッセージください。