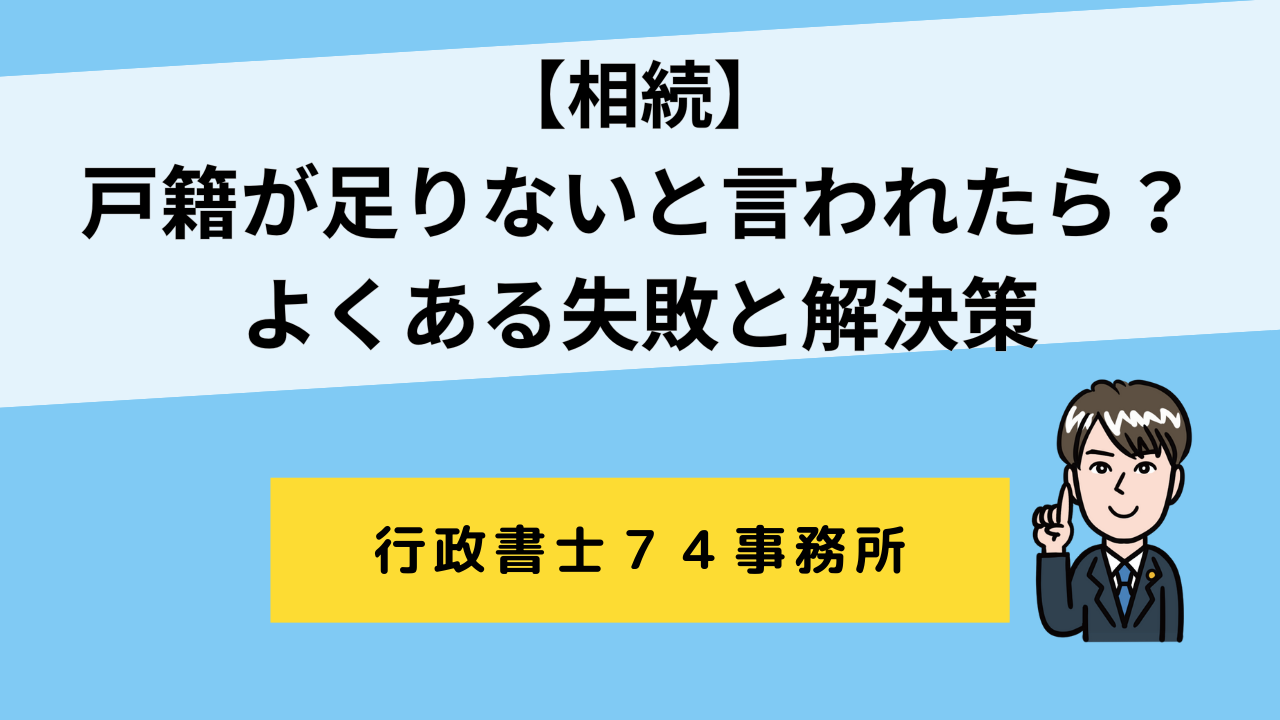はじめに 「戸籍がそろっていないと、手続きが進まない」って本当?
親が亡くなったあと、預金の解約や不動産の名義変更などをしようとすると、必ずといっていいほど必要になるのが「戸籍謄本」。
ところが、手続きを進める中でよく起こるのが、
「戸籍が足りません」
「まだ出生からのすべての戸籍がそろっていません」
…という金融機関や法務局からのストップ。
「え?亡くなった人の戸籍を取り寄せればいいんじゃないの?」と思った方、要注意です。
実は相続に必要な戸籍は1通や2通では足りないことが多く、手間も時間もかかるポイントのひとつ。
この記事では、相続手続きにおいて「戸籍が足りない」とされる理由や、何を・どこまで・どうやって集めるべきかを、初心者にも分かりやすく解説します。
なぜ「戸籍」が必要?相続の基本と戸籍の役割
戸籍は、「誰が相続人か」を証明するために使います。
例えば、亡くなった人に配偶者・子・親・兄弟姉妹など、誰が相続権を持つのかは、戸籍を確認しないと分からないのです。
相続で必要な情報
- 故人(被相続人)がいつ・どこで生まれ、誰の子どもか
- 結婚・離婚・子どもの誕生など家族の変遷
- 誰が相続人なのか(推定相続人の確認)
つまり、「被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて」そろえることで、相続人を特定できる証拠が完成するのです。
「戸籍が足りない!」よくあるつまずきの3パターン
① 出生からすべての戸籍を取っていなかった
多くの人が見落としがちなのが、「亡くなった人の出生からの戸籍が必要」という点。
例えば、現在の本籍地で最新の戸籍(除籍)だけを取っても、その前の戸籍がどこにあったのかは書かれていないこともあります。
そのため、【出生→死亡】までのつながりをたどるには、何度も戸籍が移動・改製されている場合、複数の市区町村から取り寄せる必要があります。
② 昔の戸籍が「読めない」「解読できない」
明治・大正・昭和初期の戸籍には、以下のような困難があります。
- 手書きのクセ字で読みにくい
- カタカナ交じりの旧字体で書かれている
- 改製原戸籍(かいせいげんこせき)で用語が難解
これにより、相続人の関係性を把握するのが困難となり、誤って戸籍を取り漏らすケースもあります。
③ 相続人が増えていた(隠れた相続人の存在)
戸籍をよく読んでみたら、前妻との子どもや認知した子どもが記載されていた…。
そんな場合、当初想定していた「相続人の数」が変わるため、再度戸籍を取り直す必要が出てくることがあります。
これもまた、「戸籍が足りない」=情報が不十分な状態を指す典型例です。
相続手続きに必要な戸籍はどこまで集める?
相続手続きで必要な戸籍は、大きく以下の3つに分かれます。
1. 被相続人の出生から死亡までの戸籍(全戸籍)
- 出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)
- その人がどこで生まれ、どこに本籍があり、何度戸籍を移してきたかをすべてたどる
2. 相続人の現在の戸籍謄本
- 相続人(配偶者・子どもなど)の最新の戸籍謄本
- 誰が相続人かを証明するために必要
3. 特殊ケースで必要になる戸籍
- 被相続人に子どもがいなかった場合 → 父母や兄弟姉妹の戸籍
- 養子縁組・離婚・認知がある場合 → その関係性を証明するための戸籍
戸籍の取り方と実務的な流れ
どこで取る?
- 本籍地のある市区町村役場(郵送請求 or 窓口)
- 改製原戸籍はデジタル化されていないこともあり、現地でしか取れないケースも
請求方法
- 戸籍謄本等交付申請書を提出
- 請求者が相続人であることを証明する必要あり(身分証や続柄のわかる戸籍添付)
手数料と時間
- 1通あたり数百円(450円が目安)※各市区町村で手数料が異なります
- 郵送請求は返信まで1週間〜10日ほどかかることも(急ぎの場合はレターパックがおすすめ)
実際にあったつまずき事例
【事例1】出生地が戦前の他県だった
70代男性が亡くなり、家族が戸籍を取り寄せようとしたが、現在の本籍地には出生時の記録がない。
調査の結果、戦前に戸籍があった県庁に改製原戸籍が残っており、そちらから取り寄せる必要があった。
→ 本籍地を遡る「戸籍リレー」が必要だった。
【事例2】認知していた子どもの存在を知らず、戸籍から発覚
故人の戸籍を見ていたところ、認知していた子(前のパートナーとの間)が記載されており、相続人が1人増加。
→ 当初進めていた遺産分割協議が白紙に戻り、やり直しに。
相続手続きをスムーズに進めるためのポイント
- まずは「死亡時の戸籍」から取り寄せ、前の本籍地を確認
- 古い戸籍ほど時間がかかると心得る(特に改製原戸籍)
- 読み解きが難しい戸籍は、専門家(行政書士等)に相談
- 被相続人の戸籍が出そろうまで、手続きを急がない
まとめ 「戸籍が足りない」を防ぐには、まず“たどる力”が大切
相続手続きにおいて、「戸籍を集める」という作業は、単なる書類集めではなく、被相続人の人生をたどる作業でもあります。
「戸籍が足りない」という状況を避けるためには、
- 出生から死亡までの戸籍の流れを理解すること
- 本籍地が移動している場合は、順にさかのぼること
- 少しでも不明点があれば、行政書士等に相談すること
が大切です。
相続は“知っていれば避けられるトラブル”の宝庫です。
「戸籍が足りない」と手続きを止めてしまう前に、この記事を参考に一歩ずつ進めていきましょう。
戸籍の収集でお悩みなら 相続人の調査代行サービス
行政書士74事務所では、北九州市門司区を中心に、相続人の調査手続きに特化したサポートを行っております。
「相続手続きが難しくて進められない」「相続手続きをできるだけ早く完了させたい」「戸籍の集め方が分からない」とお考えの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。
当事務所では、相続手続きに特化した専門的な支援を行っており、相続手続きに専門特化した行政書士事務所として実績を積んでおります。
これまで約5年間、北九州市および下関市内の相続でお悩みの方の相続手続きをサポートして参りました。
戸籍謄本や法定相続情報一覧図などの相続の必要書類を迅速かつ確実に対応し、お客様のご不安を解消いたします。
お問い合わせは、お電話または下記のお問い合わせフォームからお受けしております。
また、公式LINEにてチャットでのご相談も無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
ご依頼の流れ
お電話・下記お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
【お電話の場合】
お電話でお客様のご都合を伺わせていただき決定します。
【お問い合わせフォームの場合】
お問い合わせの内容を確認次第、こちらからご連絡させていただきます。
その際ご面談の日時や場所をお客様のご都合を伺いながら決定します。
お客様のお悩みを伺い、最善の方法でお悩みを解決できるようご提案いたします。
ご面談の内容に納得・合意頂けましたらご契約の手続きをします。
原則、着手金として基本料金をお預かりしております。
(指定銀行口座へお振込み)
残額は業務完了後にお支払い頂きます。
(10万円未満の場合は全額を基本料として頂戴しております。)
着手金のお振込みの確認 若しくは委任契約の合意ができ次第、業務を開始します。
定期的に業務の進行状況等のご連絡をいたします。
業務が全て完了しましたらその旨のご連絡をいたします。
最終的に弊所が行った業務内容についてご説明し書類等の納品をします。
手数料の合計と実費等の精算をしまして3日以内に完了金をお支払いして頂きます。
お問い合わせフォーム
お電話もしくは下記お問い合わせフォームよりご連絡をお願いいたします。
LINEではトーク画面のメッセージからでもご相談可能です。
『相談希望』とメッセージください。