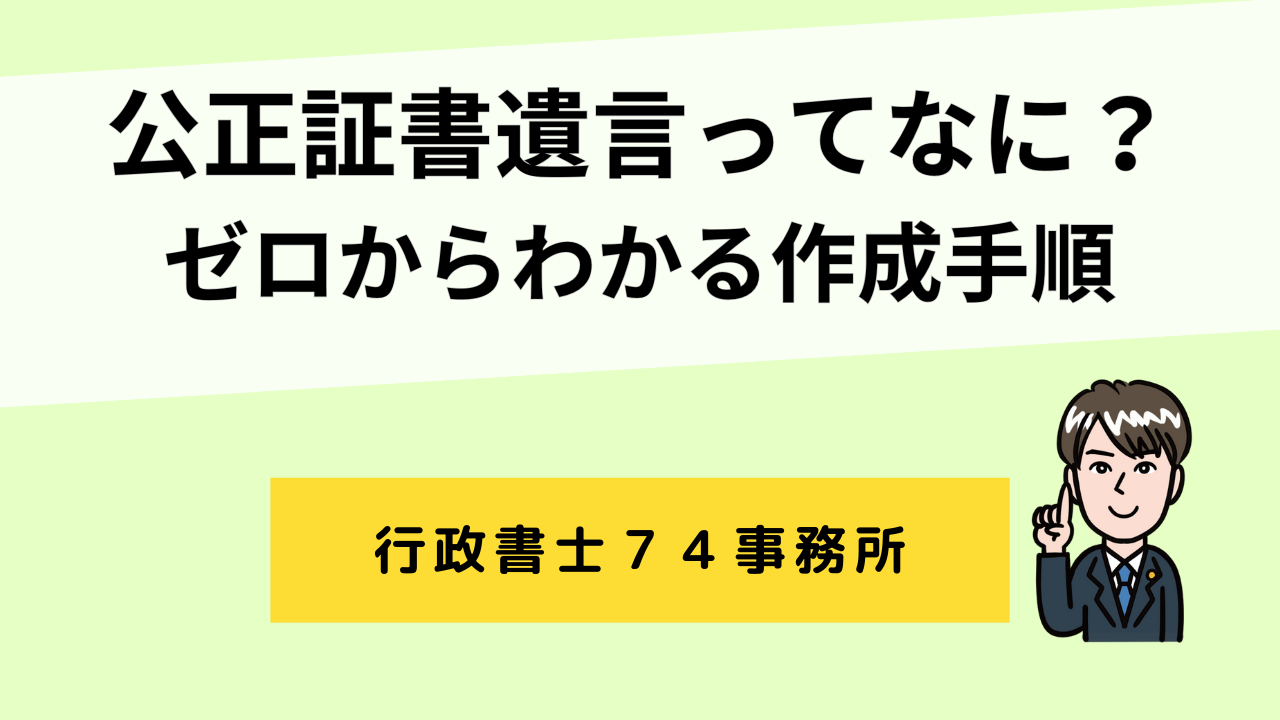高齢化が進む中で、「終活」という言葉が一般的になってきました。
なかでも注目を集めているのが「遺言書」の作成です。
特に「公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)」は、法的に強く、安全性の高い方法として多くの人に選ばれています。
今回は、「公正証書遺言とは何か」「どのように作るのか」といった基本的な部分から、実際の手続きの流れ、注意点までを初心者向けにわかりやすく解説します。
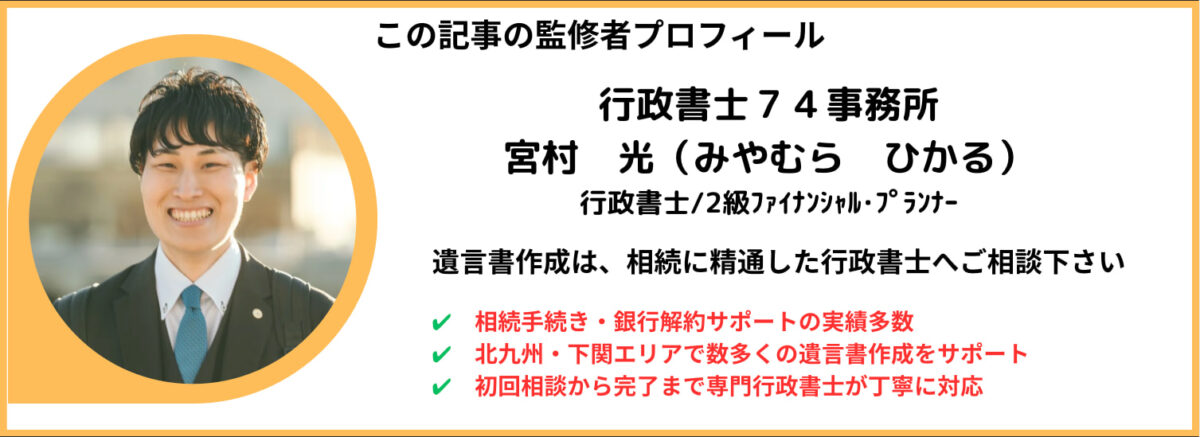
1. 公正証書遺言とは?
「公正証書遺言」とは、公証人という法律の専門家が関与して作成する遺言書のことです。
公証人が作成し、公証役場で保管されるため、偽造や紛失の心配がなく、法的効力も非常に強いのが特徴です。
他の遺言との違い
遺言にはいくつか種類がありますが、代表的なのが次の3つです。
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| 自筆証書遺言 | 自分の手書きで作成。費用はかからないが、無効になるリスクがある |
| 公正証書遺言 | 公証人が作成。確実性が高く、家庭裁判所の検認も不要 |
| 秘密証書遺言 | 内容を秘密にできるが、あまり一般的ではない |
初心者にとっては、公正証書遺言が一番安心・確実な方法といえるでしょう。
2. 公正証書遺言のメリット
公正証書遺言には、次のようなメリットがあります。
無効になるリスクがほとんどない
公証人が法的にチェックしながら作成するため、要件不備で無効になることがありません。
家庭裁判所の検認が不要
自筆証書遺言の場合、相続開始後に家庭裁判所で「検認」を受ける必要がありますが、公正証書遺言はこれが不要です。
紛失や改ざんの心配がない
原本は公証役場で厳重に保管され、副本や正本は本人と相続人が持つことになります。
高齢や病気の人でも作成しやすい
公証人が出張してくれる制度もあり、病院や自宅での作成も可能です。
3. 公正証書遺言を作成できる人
遺言を作成できるのは、満15歳以上の意思能力のある人です。
認知症や精神的な障害がある場合、内容によっては作成できないこともありますが、医師の診断書などがあれば対応可能な場合もあります。
4. 公正証書遺言の作成手続き
では実際に、公正証書遺言を作成する流れを見ていきましょう。
まずは、自分の財産や家族関係を把握し、誰に何を遺したいかを整理します。
- 不動産(持ち家、土地)
- 預貯金
- 株式や投資信託
- 借金があるかどうか
- 推定相続人は誰か
この段階で、行政書士に相談するのもおすすめです。
公正証書遺言を作成するには、以下のような書類が必要になります。
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 戸籍謄本(本人および相続人のもの)
- 財産の資料(登記簿謄本、通帳のコピーなど)
公証人に相談すると、具体的に必要な書類を教えてもらえます。
書類の取得は、行政書士などの専門家に依頼することもできます。
公証役場に連絡し、遺言内容をもとに原案を作ってもらいます。
この段階で、内容に不備がないか確認してもらえます。
公正証書遺言を作成するには、証人が2名必要です。証人には以下のような制限があります。
- 相続人やその配偶者、直系血族は不可
- 未成年者は不可
公証役場に依頼すれば、証人を紹介してもらえることもあります。
また、行政書士などの専門家に依頼すれば、原案の作成と一緒に証人にもなってくれます。
当日は、公証役場で、公証人と証人の前で内容を読み上げられ、内容に間違いがなければ、各人が署名・捺印します。
これで正式な公正証書遺言が完成です。
※体調が悪くて外出できない場合は、公証人に出張してもらうことも可能です(別途費用がかかります)。
5. 費用はどれくらい?
公正証書遺言の作成費用は、財産の額によって異なりますが、おおむね5万円~10万円程度が一般的です。
証人の謝礼(1〜2万円)や、専門家への相談料を含めると、合計で10万円〜20万円ほどになることもあります。
費用はかかりますが、その分「安心」「確実」な遺言を残すことができます。
残される相続人からすると、多少費用が掛かったとしても、自筆証書遺言よりも公正証書遺言で作成している方が、手間が掛からないため喜ばれます。
6. 注意すべきポイント
遺留分に配慮すること
一部の相続人(配偶者や子どもなど)には、最低限の取り分(遺留分)が法律で保証されています。
これを侵害すると、トラブルの原因になります。
定期的に見直す
家族構成や財産状況が変わったら、内容を見直すことが大切です。
新しい公正証書遺言を作成すれば、古いものは自動的に無効になります。
家族に伝えておく
遺言書の存在を家族が知らないと、せっかく作成しても意味がなくなります。
内容までは伝えなくても、「公正証書遺言を作ってある」ことは伝えておきましょう。
まとめ
公正証書遺言は、費用こそ多少かかるものの、安心・確実な遺言を残すためには最適な方法です。
特に相続トラブルを避けたい人、複雑な家族関係や財産状況がある人にはおすすめです。
早めの準備が、将来の不安を減らし、家族への最良の思いやりになります。
この機会に、一度ご自身の財産や家族構成を見直し、「遺言書を作ってみようかな」と考えてみてはいかがでしょうか?
自分では、手続きが手間に感じたり、どうしても準備が難しいこともあります。
そういうときは、相続の専門家に任せることも1つの手段です。
公正証書遺言 作成支援サービス
行政書士74事務所では、下関市・北九州市を中心に、相続専門の行政書士事務所として、遺言や相続に関するさまざまなサポートを行っております。
「一人で遺言書を作成するのは不安…」「手続きが複雑でよくわからない…」とお悩みの方もご安心ください。
相続に強い行政書士が、お客様に寄り添いながら丁寧にサポートいたします。
当事務所では、お客様に代わって
- 遺言書の原案作成
- 公証人との打ち合わせ
- 証人の手配
などをすべて一括で対応いたします。
ご相談・お問い合わせは、お電話または下記のお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。
また、公式LINEにて無料のチャット相談も受け付けております。
「ちょっと聞いてみたい」という内容でも構いませんので、お気軽にご利用ください。
ご依頼の流れ
お電話・下記お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
【お電話の場合】
お電話でお客様のご都合を伺わせていただき決定します。
【お問い合わせフォームの場合】
お問い合わせの内容を確認次第、こちらからご連絡させていただきます。
その際ご面談の日時や場所をお客様のご都合を伺いながら決定します。
お客様のお悩みを伺い、最善の方法でお悩みを解決できるようご提案いたします。
ご面談の内容に納得・合意頂けましたらご契約の手続きをします。
原則、着手金として基本料金をお預かりしております。
残額は業務完了後にお支払い頂きます。
(10万円未満の場合は全額を基本料として頂戴しております。)
着手金のお振込みの確認 若しくは委任契約の合意ができ次第、業務を開始します。
定期的に業務の進行状況等のご連絡をいたします。
業務が全て完了しましたらその旨のご連絡をいたします。
手数料の合計と実費等の精算をしまして3日以内に完了金をお支払いして頂きます。
最終的に弊所が行った業務内容についてご説明し書類等の納品をします。
お問い合わせフォーム
お電話もしくは下記お問い合わせフォームよりご連絡をお願いいたします。
LINEではトーク画面のメッセージからでもご相談可能です。
『相談希望』とメッセージください。