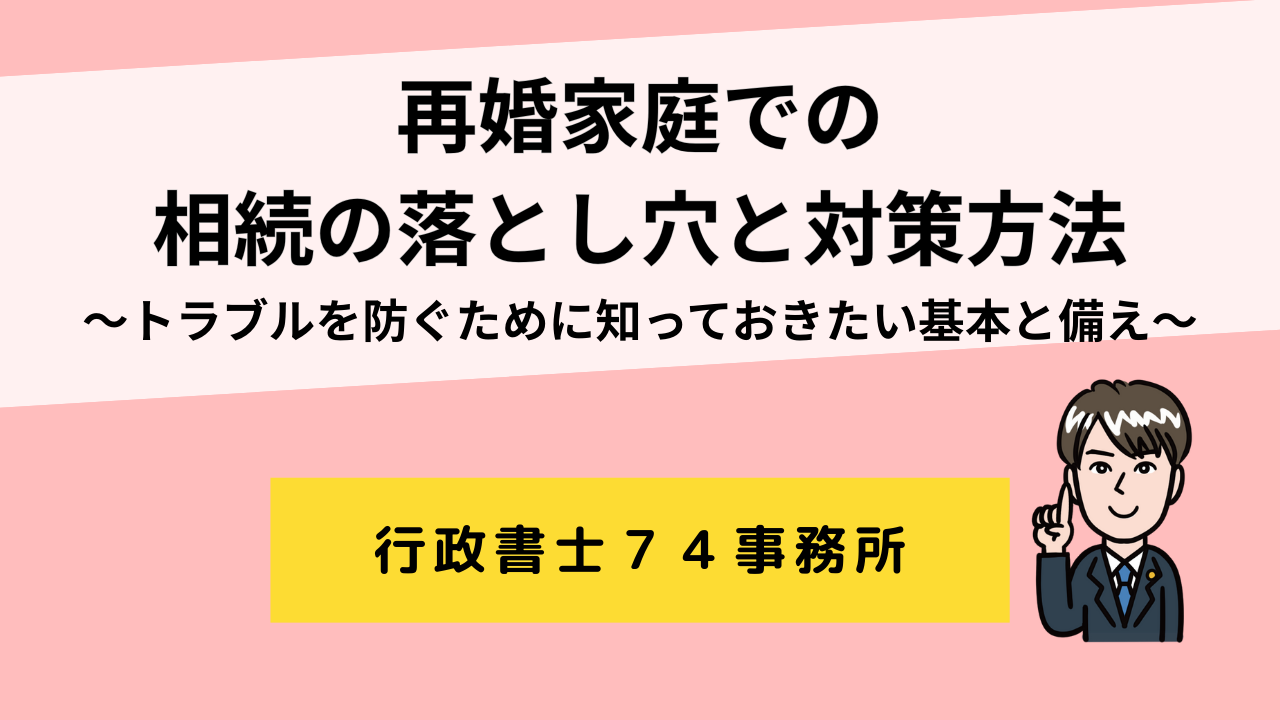はじめに 再婚家庭の相続は「特別な配慮」が必要です
家族の形が多様化する現代。再婚家庭(ステップファミリー)も珍しくなくなりました。
しかし、再婚家庭の相続では「普通の相続」とは異なる点が多く、何も準備せずにいるとトラブルに発展するリスクが高くなります。
「今の家族仲はいいから大丈夫」と思っていても、いざ相続が始まると、元配偶者との子どもや、再婚相手の子との関係が複雑に絡み合うことも。
この記事では、再婚家庭で起こりがちな相続トラブルの実例を紹介しながら、初心者でも理解しやすいように「落とし穴」と「対策方法」を解説します。
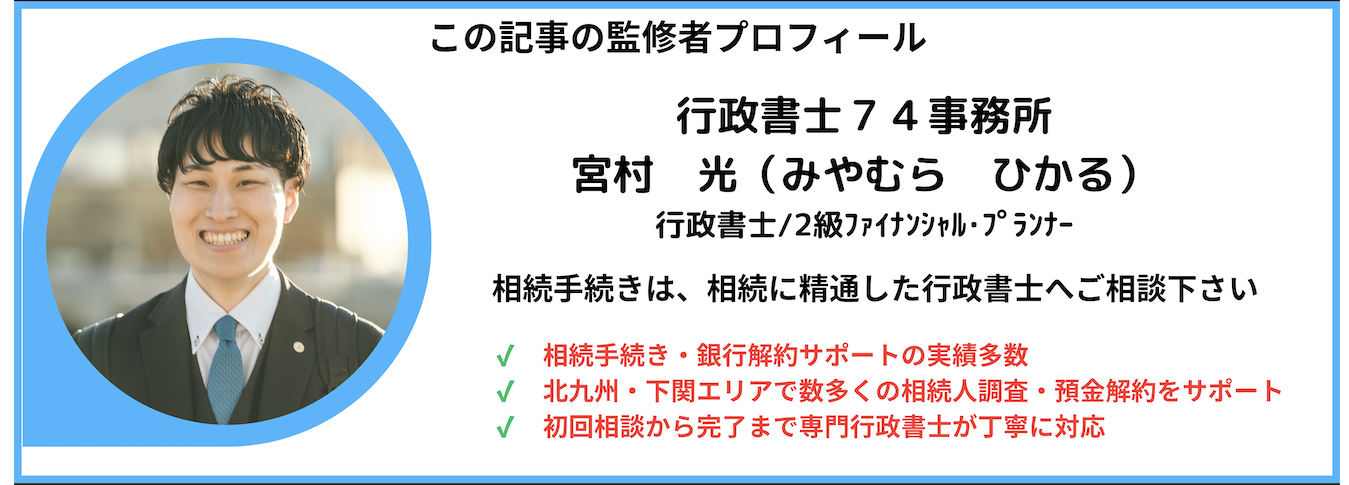
再婚家庭での相続が揉めやすい3つの理由
① 前の配偶者との子にも「相続権」がある
再婚前にもうけた子ども(前妻・前夫との子)も、法律上の相続人になります。
たとえその子と何十年も会っていなくても、相続の場では「実子」として平等な権利があります。
これを知らずに、再婚後の家族だけで相続の話を進めてしまうと、あとから前の子どもが異議を申し立てる可能性があります。
② 再婚相手の連れ子には「自動的な相続権」はない
逆に、再婚相手の子(いわゆる「連れ子」)は、養子縁組をしていなければ相続権がありません。
長年一緒に暮らしてきた実質的な「家族」であっても、法的には他人のまま。
この事実を知らずに「当然相続できるもの」と思い込んでいると、トラブルのもとに。
③ 遺産の配分で感情的なもつれが起きやすい
再婚家庭では、次のような感情の行き違いが起きやすくなります。
- 前妻との子 →「自分は忘れられたのか」「新しい家族に全部奪われるのか」
- 再婚後の子 →「ずっと一緒に暮らしてきたのに相続できないの?」
- 再婚相手 →「配偶者として支えてきたのに、前の家族に財産を取られるのは納得できない」
感情のズレと法律のギャップが、家族内の大きなトラブルを引き起こす原因になります。
実際にあった再婚家庭の相続トラブル実例
実例① 前妻との子が突然登場。相続協議が大混乱!
70代男性が亡くなり、再婚相手とその連れ子(20年以上一緒に生活)で相続の話を進めていた。
しかし、前妻との間にいた実子が現れ、「私にも相続権がある」と主張。
結果、財産分割のやり直し+遺産分割調停に。
ポイント
前妻の子どもにも、法律上は正当な相続権がある
事前にその存在や権利を認識しておく必要がある
実例② 連れ子を本当の子どもと思っていたが、相続できなかった…
ある女性が亡くなり、再婚相手と共に暮らしていた息子(夫の連れ子)が相続を希望。
しかし、養子縁組をしておらず、法的には親子関係がなかったため、相続人に含まれなかった。
ポイント
養子縁組をしていない連れ子は、相続人ではない
どれだけ長く一緒に暮らしていても、法的関係がなければ財産はもらえない
再婚家庭の相続トラブルを防ぐための5つの対策
① 遺言書を必ず作成する(できれば公正証書で)
再婚家庭では「遺言書の有無」が相続の明暗を分ける大きなカギになります。
「誰に、何を、どのくらい相続させたいか」を明確に書き残しましょう。
特に、連れ子に財産を渡したい場合、遺言書がなければ何も渡せません。
→ 公正証書遺言なら法的に安全性が高く、家庭裁判所の検認も不要です。
② 連れ子には養子縁組を検討する
連れ子にも法定相続人としての地位を与えたい場合、養子縁組をして法的な親子関係を築くことが必要です。
ただし、他の相続人(たとえば前妻との子)とのバランスを考慮する必要もあります。
③ 家族間で早めに相続の意思確認をしておく
- 財産を誰にどれくらい渡したいのか
- 連れ子をどう扱うのか
- 前妻との子と連絡を取る可能性はあるか
こうした点を、元気なうちに家族で話し合っておくことが何より大切です。
④ 相続人関係を整理しておく
相続が始まると、戸籍をたどって「相続人を確定」する作業があります。
再婚を重ねていたり、認知した子がいる場合など、関係が複雑になりやすいため、相続関係説明図などを生前に整理しておくと安心です。
⑤ 専門家に早めに相談する
再婚家庭の相続は「法的な問題」と「感情的な問題」の両方が絡みます。
行政書士、司法書士、弁護士、税理士など、相続に強い専門家に相談することで、事前にトラブルを回避する道筋が見えてきます。
まとめ|「うちは複雑だから…」こそ、準備が必須!
再婚家庭の相続では、普通の相続とは異なる複雑さや落とし穴がたくさんあります。
関係が良好なうちにこそ、きちんとした準備をしておくことが、家族を守る最大の優しさです。
最後にチェック 再婚家庭でやっておきたい相続対策リスト
- 遺言書の作成(特に公正証書)
- 連れ子との養子縁組の検討
- 家族全員での話し合い
- 相続人の関係整理(戸籍・家系図など)
- 専門家への早めの相談
家族のカタチが複雑になる今だからこそ、「円満な相続」は「計画的な備え」から。
不安がある方は、ぜひ一度専門家に相談してみてくださいね。
そういうときは、相続の専門家に任せることも1つの手段です。
相続のプロと作る!公正証書遺言 作成支援サービス
当事務所は、下関市・北九州市を中心に、相続専門の行政書士事務所として、遺言や相続に関するさまざまなサポートを行っております。
「一人で遺言書を作成するのは不安…」「手続きが複雑でよくわからない…」とお悩みの方もご安心ください。
相続に強い行政書士が、お客様に寄り添いながら丁寧にサポートいたします。
当事務所では、お客様に代わって
- 遺言書の原案作成
- 公証人との打ち合わせ
- 証人の手配
などをすべて一括で対応いたします。
ご相談・お問い合わせは、お電話または下記のお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。
また、公式LINEにて無料のチャット相談も受け付けております。
「ちょっと聞いてみたい」という内容でも構いませんので、お気軽にご利用ください。
ご依頼の流れ
お電話・下記お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
【お電話の場合】
お電話でお客様のご都合を伺わせていただき決定します。
【お問い合わせフォームの場合】
お問い合わせの内容を確認次第、こちらからご連絡させていただきます。
その際ご面談の日時や場所をお客様のご都合を伺いながら決定します。
お客様のお悩みを伺い、最善の方法でお悩みを解決できるようご提案いたします。
ご面談の内容に納得・合意頂けましたらご契約の手続きをします。
原則、着手金として基本料金をお預かりしております。
残額は業務完了後にお支払い頂きます。
(10万円未満の場合は全額を基本料として頂戴しております。)
着手金のお振込みの確認 若しくは委任契約の合意ができ次第、業務を開始します。
定期的に業務の進行状況等のご連絡をいたします。
業務が全て完了しましたらその旨のご連絡をいたします。
手数料の合計と実費等の精算をしまして3日以内に完了金をお支払いして頂きます。
最終的に弊所が行った業務内容についてご説明し書類等の納品をします。
お問い合わせフォーム
お電話もしくは下記お問い合わせフォームよりご連絡をお願いいたします。
LINEではトーク画面のメッセージからでもご相談可能です。
『相談希望』とメッセージください。