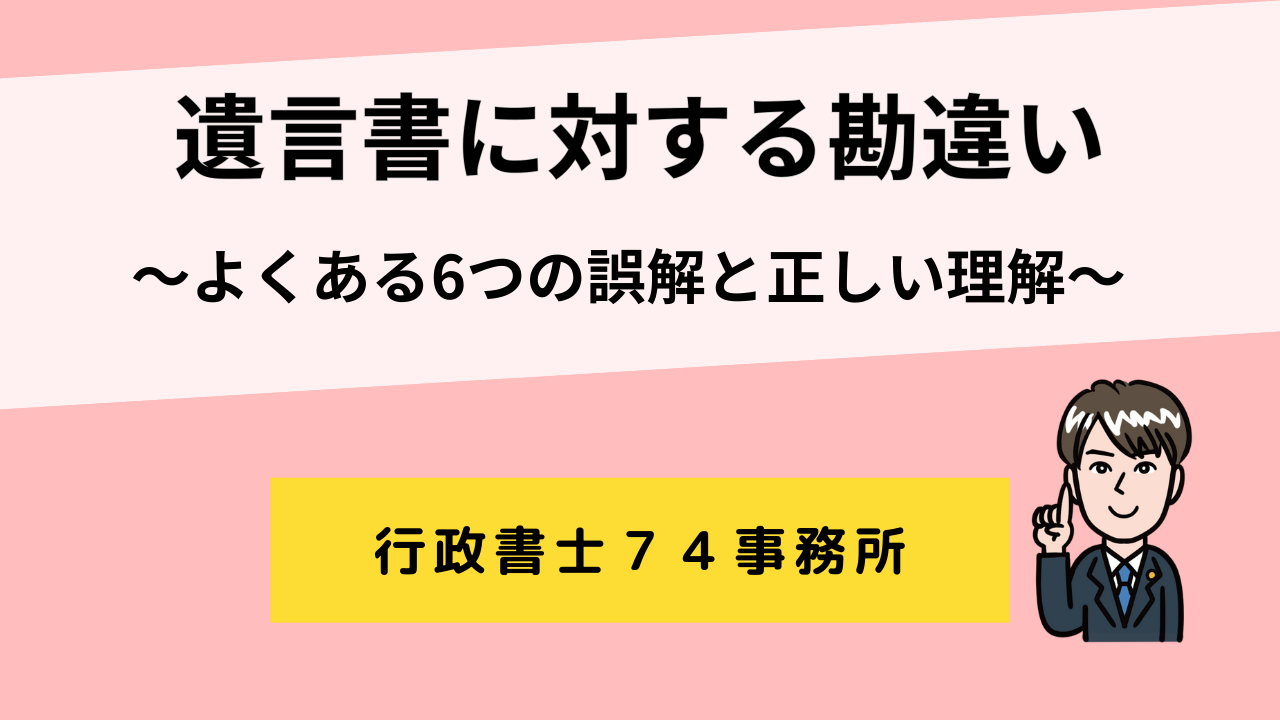遺言書に対する勘違い はじめに
「遺言書」と聞くと、なんとなく縁起が悪いもの、財産家だけが作るもの、あるいは最期に残す「遺書」と同じだと考えてしまう方も少なくありません。
しかし実際には、遺言書は誰にとっても大切な“将来の備え”です。近年では相続トラブルの増加に伴い、専門家の間でも「早めに遺言書を作成しておくこと」が強く推奨されています。
それでも世の中には、遺言書にまつわるさまざまな誤解や勘違いが存在します。本記事では、その中でも特によく見られる6つの勘違いを取り上げ、正しい理解を解説します。
勘違い① 「遺言書=遺書」だと思っている
まず最も多い誤解が、「遺言書」と「遺書」を混同するケースです。
- 遺書 …主に自殺などを前提に、家族や友人への気持ちを手紙形式で残すもの。法的効力はありません。
- 遺言書 …相続や財産分与についての意思を記し、民法で定められた要件を満たすことで法的効力を持つもの。
つまり、両者は似て非なる存在です。遺言書は「自分の財産をどう承継させたいか」を法律的に明確にするためのもの。残された家族の負担を軽くするために存在しています。
勘違い② 「財産が多い人だけが作るもの」
「自分には大した財産がないから、遺言書なんて必要ない」という声もよく耳にします。しかし実際には、財産の多少にかかわらず遺言書は役立ちます。
たとえば、次のようなケースです。
- 預貯金が数百万円しかなくても、相続人が複数いる場合には分け方を巡って揉めることがある。
- 実家の土地・建物を誰が相続するかで意見が割れ、売却か住み続けるかで家族が対立する。
- 「家業を継ぐ子どもに会社株式を残したい」という想いを明確にしておかないと、分散してしまい経営に支障をきたす。
財産が多い少ないではなく、「誰に何を残したいか」をきちんと意思表示しておくことが重要なのです。
勘違い③ 「高齢になってから作るもの」
遺言書=高齢者が作るもの、というイメージも広く根付いています。しかし、これも大きな勘違いです。
人はいつ病気や事故で判断能力を失うかわかりません。認知症になってしまえば、遺言書を作成することはできなくなります。まだ元気で頭もはっきりしているうちにこそ、作っておくことが安心につながります。
特に、
- 小さなお子様がいる方
- 再婚している方
- 家業や会社を営んでいる方
などは、早い段階で遺言書を準備しておくことで、想定外の事態に備えることができます。
勘違い④ 「仲が良いから遺言はいらない」
「うちの家族は仲がいいから大丈夫」と考える方も少なくありません。ところが、相続の場面では“仲の良さ”だけでは解決できない現実があります。
相続が発生すると、法律上は 相続人全員で遺産分割協議を行い、全員一致で合意しなければならない というルールがあります。仲が良くても意見が揃わなければ手続きが止まってしまうのです。
実際に、
- 兄弟姉妹の一人が「平等に分けたい」と主張する
- 別の兄弟姉妹が「長男が多く相続するのが当然だ」と考える
- 配偶者が生活を守るために強く希望する
といった状況で意見が対立し、時間も費用もかかってしまうケースは非常に多いのです。
遺言書があれば、あらかじめ「誰に何を残すか」が明記されているため、協議を経ることなくスムーズに手続きが進みます。
勘違い⑤ 「一度作ったら変更できない」
「若い頃に遺言を書いてしまったら、その後の事情変更に対応できないのでは?」と心配される方もいます。
実際には、遺言は 何度でも作り直すことが可能 です。
- 新しい遺言書を書けば、古い遺言は無効になり、最新のものが有効になります。
- 財産状況や家族関係に変化があった際には、定期的に見直しを行うのが望ましいです。
例えば、
- 孫が誕生した
- 財産を売却して現金に変えた
- 仲の良かった相続人と疎遠になった
こうした変化は誰にでも起こり得ます。人生の節目ごとに遺言をアップデートするイメージを持つと安心です。
勘違い⑥ 「遺言書を作ると財産が使えなくなる」
「遺言書に書いたから、もう自由にお金を使えないのでは?」と考えてしまう人もいます。しかし、これも誤解です。
遺言は あくまで死亡後に効力が発生するもの です。生前は財産の処分や使用に全く制限はかかりません。
- 遺言書を書いた後に旅行に行くために貯金を使っても構わない
- 家や土地を売却しても問題ない
- 財産が減った場合でも、残った財産について遺言は有効
つまり、遺言書を書いたからといって生活が窮屈になることはありません。安心して財産を管理し続けることができます。
遺言書に対する勘違い まとめ
遺言書は「特別な人だけが作るもの」ではなく、誰にとっても役立つ将来への備えです。多くの方が生命保険に加入しているように、将来の相続トラブルに備えて遺言書を作成しておくと安心です。
本記事でご紹介した6つの勘違いを整理すると
- 遺言書と遺書は全く別物である
- 財産の多い少ないに関係なく有効である
- 高齢者だけでなく、誰もが早めに準備すべきものである
- 家族仲が良くても相続ではトラブルが起こり得る
- 遺言は何度でも書き直し可能である
- 遺言を作っても財産の利用は自由にできる
ということになります。
遺言書は、残された家族を守るための「思いやりの形」です。誤解を正しく理解し、早めに準備することで、大切な人たちが安心して生活できる未来を残すことができます。(相続手続きをスムーズに進めることができます)
大切なご家族のことを考えると、作成しない手はないのではないでしょうか。
専門家に相談するメリット
遺言書は自分で作成することも可能ですが、形式を少しでも誤ると無効になってしまうリスクがあります。せっかくの想いを形にしたつもりでも、残された家族にとっては「効力のない紙切れ」になってしまうことも少なくありません。
遺言書作成支援の専門家である行政書士に相談することで、
- 法律で定められた要件を満たす正しい遺言書を作成できる
- あなたの希望を具体的に反映した内容を形にできる
- 公正証書遺言の作成や証人立会いなどもサポートしてもらえる
- 将来の相続トラブルを未然に防ぐことができる
- 亡くなった後、作成した遺言の内容を迅速に実現してもらえる
といった大きなメリットがあります。
行政書士74事務所の遺言書作成サポート
北九州市門司区にある行政書士74事務所では、遺言書の作成から保管方法のアドバイス、さらには相続発生後の手続きまで幅広くサポートしています。
- 初回相談は無料
- 平日夜間・土日祝日も柔軟に対応
- 地域密着でフットワーク軽くサポート
- 出張相談も可能なのでご自宅でも安心
「自分に遺言書なんて必要だろうか?」と悩んでいる段階でも構いません。まずはお気軽にご相談いただければ、あなたに合った方法をご提案いたします。
お問い合わせはこちら
遺言書は「いつか」ではなく「今」準備することが大切です。
将来の不安を少しでも減らすために、専門家のサポートを受けてみませんか?
「大切な人へ安心を残すために」行政書士74事務所が全力でサポートいたします。
お問い合わせフォーム
お電話もしくは下記お問い合わせフォームよりご連絡をお願いいたします。
LINEではトーク画面のメッセージからでもご相談可能です。
『相談希望』とメッセージください。