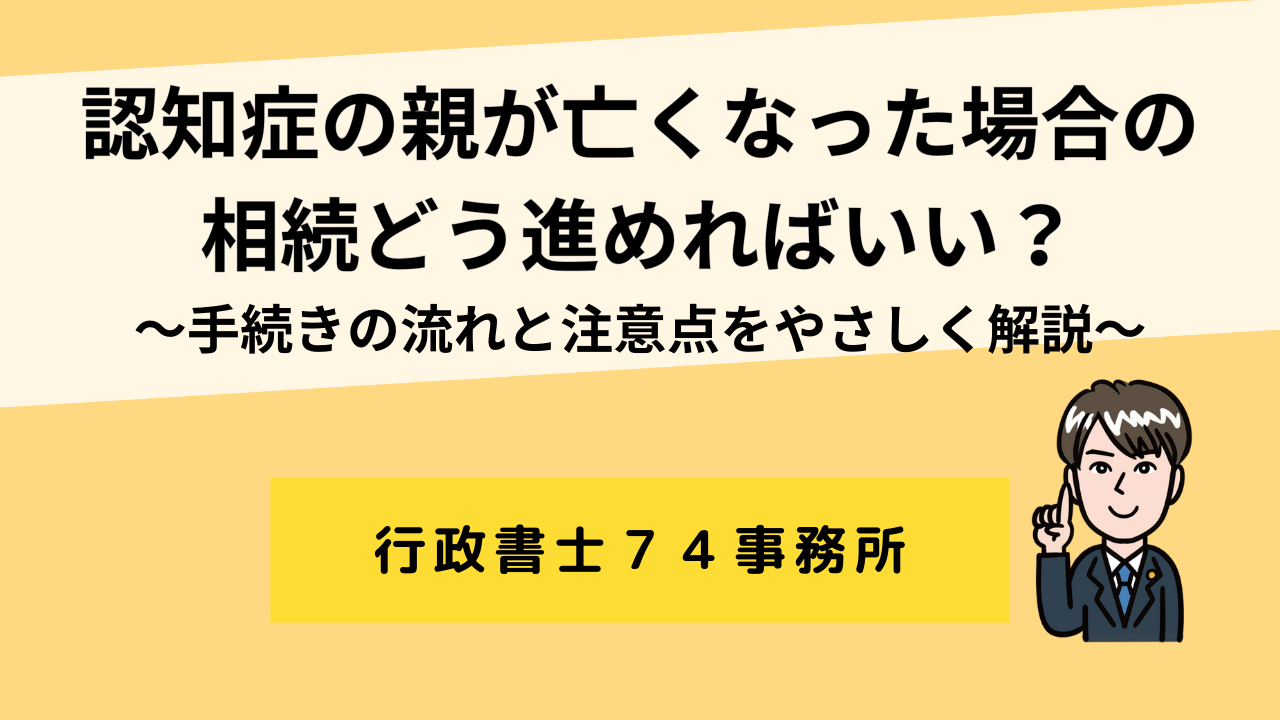はじめに 「認知症だった親」の相続、何が違うの?
親が亡くなったとき、避けて通れないのが「相続」の手続き。
もしその親が生前に認知症だった場合、「遺言書は?」「判断能力はあった?」「財産管理はどうなっていた?」など、通常の相続とは異なる注意点や確認すべきことが出てきます。
「どう手続きを進めたらいいのかわからない」
「遺産分割協議ってできるの?」
「成年後見制度って使うべきだったの?」
この記事では、認知症だった親が亡くなった場合の相続手続きの進め方を、初心者の方にもわかりやすく解説します。
1. まずは基本の確認!相続の流れとは?
認知症かどうかにかかわらず、相続の基本的な流れは共通しています。
一般的な相続の流れ
- 死亡届の提出
- 遺言書の有無を確認
- 相続人の調査(戸籍収集など)
- 相続財産の調査
- 相続放棄・限定承認の検討(3か月以内)
- 遺産分割協議
- 相続登記・預貯金の名義変更・保険金請求など
この一連の流れの中で、認知症の影響が出てくるのは主に「遺言書の有効性」や「生前の財産管理」に関する部分です。
2. 遺言書がある場合 認知症の影響に要注意!
遺言書が残されていた場合、相続手続きは比較的スムーズに進みます。
しかし親が認知症だった場合、「その遺言書、本当に有効?」という点が問題になります。
▶ ポイント① 遺言書作成時の「判断能力」がカギ!
遺言書は、作成したときに本人に“意思能力(判断能力)”があったかがとても重要です。
認知症が進行していた場合、「本人の意思で書いたとは言えない」と判断され、無効になることもあります。
▶ 対策 遺言書を作成するときは公正証書+医師の診断が安心
公証役場で作成する「公正証書遺言」なら、本人の意思能力を公証人がチェックします。
さらに、作成時に医師の診断書を添えることで、後から「無効」とされるリスクを下げることができます。
3. 遺言書がない場合 遺産分割協議を行う
遺言書がなかった場合は、法定相続人全員で「遺産分割協議」を行い、財産の分け方を話し合って決めます。
この際、問題となるのは「生前、認知症だった間にどう財産が管理されていたか」です。
4. 認知症の親の財産、生前にどう管理されていた?
親が認知症になると、銀行口座の管理、土地の売却、施設の支払いなどが必要になります。
しかし、本人に判断能力がない状態では、勝手に手続きを進めることができません。
▶ ① 任意後見・法定後見を利用していたか?
認知症の親に対して、成年後見制度(任意後見・法定後見)が使われていた場合、その記録や財産管理の内容が、相続手続きに影響します。
後見人がついていた場合、その後見記録を確認し、使い込みや不正がなかったか、相続人間でチェックすることも重要です。
▶ ② 後見制度を利用せず、家族が勝手に財産を動かしていた場合
親名義の口座から家族が現金を引き出して使っていた場合など、他の相続人から「使い込み」と指摘され、トラブルに発展することがあります。
【例】
「介護費用に使っていたつもりでも、使途が不明だと疑われる」
「特定の相続人だけが多くの財産を使っていた」
5. 相続トラブルになりやすいポイントと対策
認知症の親の相続では、次のようなケースが特にトラブルにつながりやすいです。
トラブル① 遺言書の有効性を巡る争い
→ 対策 生前の診断書・公正証書遺言で意思能力を証明できるようにしておく。
トラブル② 生前の財産の使い込み疑惑
→ 対策 後見制度の活用+家計簿や領収書などの記録を残しておく。
トラブル③ 財産内容が把握できない
認知症のため、どこに何の資産があるかわからないまま亡くなるケースも。
→ 対策 エンディングノートや財産一覧表を生前に家族と共有しておく。
6. 認知症の親の相続でやっておくべき事前準備
親がまだ存命で認知症が進みつつある…という場合、次の対策をしておくと安心です。
エンディングノートの活用
→ 財産の所在・希望・口座情報などを家族と共有する手段として有効
任意後見契約の締結
→ 判断能力があるうちに信頼できる人と後見契約を結んでおく
公正証書遺言の作成
→ 判断能力が残っているうちに、希望する相続内容を明確に書き残す
7. 専門家に相談するのも大切です
認知症の親に関する相続は、法律・制度・感情が複雑に絡み合います。
行政書士・司法書士・弁護士・社会福祉士などの専門家に早めに相談することで、スムーズな手続きとトラブル回避につながります。
まとめ 認知症の親の相続は、事前の備えがカギ!
認知症の親が亡くなった場合、相続では以下のポイントが重要になります。
認知症と相続のカギまとめ
- 遺言書の有効性(判断能力)が重要
- 生前の財産管理方法によってはトラブルに
- 成年後見制度の活用で安心感が増す
- 相続トラブルを防ぐには「記録」「準備」「話し合い」が不可欠
- 不安があれば早めに専門家に相談!
「認知症だからこそ、家族で準備する」ことが、残された人の負担を大きく減らします。できるうちに備えておきましょう。
そういうときは、相続の専門家に任せることも1つの手段です。
相続のプロと作る!公正証書遺言 作成支援サービス
当事務所は、下関市・北九州市を中心に、相続専門の行政書士事務所として、遺言や相続に関するさまざまなサポートを行っております。
「一人で遺言書を作成するのは不安…」「手続きが複雑でよくわからない…」とお悩みの方もご安心ください。
相続に強い行政書士が、お客様に寄り添いながら丁寧にサポートいたします。
当事務所では、お客様に代わって
- 遺言書の原案作成
- 公証人との打ち合わせ
- 証人の手配
などをすべて一括で対応いたします。
ご相談・お問い合わせは、お電話または下記のお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。
また、公式LINEにて無料のチャット相談も受け付けております。
「ちょっと聞いてみたい」という内容でも構いませんので、お気軽にご利用ください。
ご依頼の流れ
お電話・下記お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
【お電話の場合】
お電話でお客様のご都合を伺わせていただき決定します。
【お問い合わせフォームの場合】
お問い合わせの内容を確認次第、こちらからご連絡させていただきます。
その際ご面談の日時や場所をお客様のご都合を伺いながら決定します。
お客様のお悩みを伺い、最善の方法でお悩みを解決できるようご提案いたします。
ご面談の内容に納得・合意頂けましたらご契約の手続きをします。
原則、着手金として基本料金をお預かりしております。
残額は業務完了後にお支払い頂きます。
(10万円未満の場合は全額を基本料として頂戴しております。)
着手金のお振込みの確認 若しくは委任契約の合意ができ次第、業務を開始します。
定期的に業務の進行状況等のご連絡をいたします。
業務が全て完了しましたらその旨のご連絡をいたします。
手数料の合計と実費等の精算をしまして3日以内に完了金をお支払いして頂きます。
最終的に弊所が行った業務内容についてご説明し書類等の納品をします。
お問い合わせフォーム
お電話もしくは下記お問い合わせフォームよりご連絡をお願いいたします。
LINEではトーク画面のメッセージからでもご相談可能です。
『相談希望』とメッセージください。